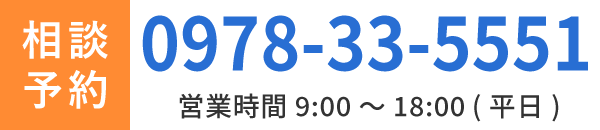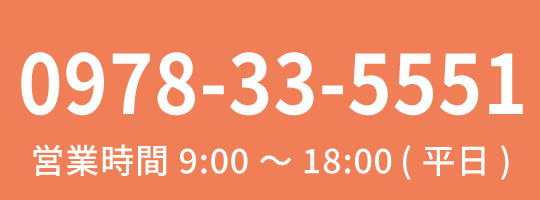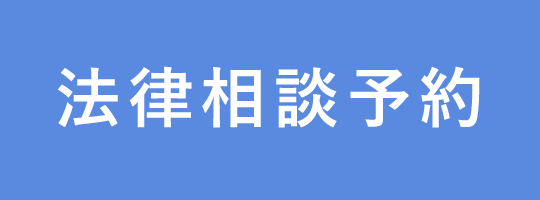はじめに
人が亡くなったことを銀行が知ると、亡くなった人名義の銀行口座は、預金の引出しや振込送金などが一切できなくなり、銀行口座が凍結されます。まずはじめにお伝えしておく必要があるのは、人が亡くなった瞬間から、その人の預金口座は相続財産であるため、自由に引き出すことができないということです。もっとも、急な葬儀費用の支出などが必要で、当座の仮払いでもよいので引き出すことはできないだろうかというニーズも存在します。
このページでは、「預金口座の凍結を解除するには」というテーマで、相続人が知っておくべき専門的で網羅的な情報を解説します。銀行口座凍結の法的根拠から解除方法、家庭裁判所での手続きや判例、想定されるトラブルへの対処策、そして弁護士に依頼するメリットまで、具体例を交えて説明していきます。
このページの目次
被相続人の死亡による銀行口座凍結の法的根拠と仕組み
口座凍結の法的根拠
人が亡くなると、その人名義の預金は相続財産となります。民法上、相続財産は相続人が複数いる場合には相続人全員の共有に属します(民法898条)。かつては銀行預金債権について「相続開始と同時に各相続人の法定相続分に応じて当然に分割される」という判例(最判昭和29年4月8日など)がありました。この旧来の考え方では、たとえば相続人が2人で預金が6000万円ある場合、法律上は各自が3000万円ずつ取得すると解釈されていたのです。
しかしこの解釈はのちに変更され、最高裁判所(大法廷)平成28年12月19日決定において「共同相続された普通預金債権等は相続開始と同時に当然に分割されることはなく、遺産分割の対象となる」との判断が示されました。要するに、預貯金も不動産など他の遺産と同様に遺産分割協議や調停で分け方を決める必要がある財産なのです。
この判例変更により、各相続人が単独で法定相続分の払戻しを請求することはできないという扱いが明確化されました。実務上も、金融機関は遺産分割が完了するまでは相続人の一人からの払戻し要求に応じない対応を徹底するようになっています。
口座凍結の仕組み
銀行は名義人の死亡を知ると、ただちに当該預金口座を凍結します。これは残された相続財産が勝手に引き出されて所在不明になることを防ぎ、遺産分割協議が公平に行われるようにする措置です。
そして、口座凍結されると現金の引き出しや振込など一切の取引が停止されます。公共料金の自動引き落としや給与・年金などの振込も受け付けられなくなるため、たとえば故人名義で光熱費等の引落しを設定していた場合は口座を変更する必要があります。
また、凍結を銀行に知らせず故人のキャッシュカードで現金を引き出すことは、後々大きなトラブルの元です。相続人間の不信感を招き、場合によっては不当利得返還や損害賠償を請求されるおそれもあります。銀行としても「なぜ勝手に引き出させたんだ」と他の相続人から責任を追及される事態を避けたいのが本音であり、死亡の事実を把握すれば直ちに口座を凍結するのです。つまり、銀行口座の凍結は法律上の相続財産管理の原則と、実務上のトラブル防止策に基づくものと言えます。
凍結された預金口座の解除・払戻し方法(遺産分割協議がある場合/ない場合)
口座が凍結された後、その預金を払い戻すためには相続手続き(遺産分割手続き)を完了させることが必要です。具体的な解除方法は、遺言書の有無や相続人全員の合意(遺産分割協議)の有無によって異なります。以下ではケースごとに必要な手順を説明します。
遺言書や遺産分割協議書がある場合の解除方法
被相続人が遺言書を残していた場合や、相続人全員で遺産分割協議書を作成し合意が成立している場合は、比較的スムーズに口座凍結を解除できます。
【遺言書がある場合】
銀行に遺言書を提出して故人の意思に従った相続手続きを行います。公正証書遺言であればそのまま有効ですし、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認済証明書を添えて提出します。遺言執行者が指定されている場合には、執行者が代理で銀行手続きを行うことも可能です。いずれにせよ、銀行は遺言の内容に基づいて預金を誰に引き渡すか判断しますので、遺言書が明確に預金の承継者を指定していれば解除までの時間も短くなります。
遺言書がなく相続人全員の協議が整っている場合
遺産分割協議書(または銀行所定の相続同意書)を用意します。遺産分割協議書には相続人全員(法定相続人全員)が参加し、預金を含む遺産を「誰がどれだけ相続するか」を取り決め、全員が署名捺印(実印)します。
銀行で手続きする際には、この協議書の原本またはコピー(原本証明付)とともに以下の書類を提出するのが一般的です:
- 被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡まで連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本(現在のもの)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の預金通帳、キャッシュカード(銀行によっては不要の場合も)
- 銀行所定の相続届出書(相続人代表者が記入し提出)
協議書が提出され、必要書類に不備がなければ、銀行は口座の解約・払戻しに応じます。
具体的な払戻し方法は銀行によって多少異なりますが、代表相続人の口座に相続預金を一括入金し、その後相続人間で分配する形をとることが多いです。
また、遺産分割協議は相続人全員が関与できる人物であることが条件です。例えば相続人の中に未成年者がいる場合は特別代理人を立てないと協議書が無効になりますし、行方不明者がいる場合もそのままでは手続きできません。
そうした問題がなければ、口座凍結解除の依頼から完了までの期間は提出後おおむね10日~3週間程度が目安と言われています。なお、銀行手続き自体に手数料は通常かかりません。
遺産分割協議が成立していない場合の解除方法
相続人全員の合意が得られていない場合(遺産分割協議書がない場合)、銀行は預金の払戻しに応じません。
この場合、口座凍結を解除するためには家庭裁判所での遺産分割調停・審判など法的手続きを経て相続方法を決定する必要があります。
まず相続人間で協議を試みたものの折り合いがつかない場合、各自または一方が家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行います(後述の「家庭裁判所での調停・審判による解除」の項で流れを解説します)。調停や審判で預金の分配方法が確定するまでは、銀行口座の凍結は原則解除できません。
ただし、協議書がない場合でも相続人全員が協力的なケースでは、銀行所定の「相続手続依頼書」や「相続人代表者指定届」などに相続人全員が署名押印することで手続きを進められる場合があります。
これは実質的に簡易な遺産分割協議と同じ意味を持ち、銀行ごとのフォームに全相続人の同意を得て払戻し先を決める方法です。
例えば「預金は長男〇〇が相続する」等の内容で相続人全員の実印を押し、印鑑証明書を添付すれば、正式な協議書がなくとも銀行は払戻しに応じることがあります。もっとも、この方法でも相続人全員の協力が前提です。一人でも反対者や連絡の取れない相続人がいると、このような銀行内部手続きでは対応できません。結局、そのような場合には家庭裁判所での手続をする必要が出てきます。
まとめると、銀行口座凍結の解除(預金払戻し)には: 1) 遺言書または相続人全員の合意(協議書等)による手続き、2) 合意不成立時は家庭裁判所での調停・審判による決着、という二つのルートがあります。次章では、調停・審判を利用する場合の具体的な流れと必要書類を見ていきましょう。
相続人全員が揃っていない場合の対応策:預貯金の仮払い制度等
相続人の協力が得られない場合は原則として調停・審判で決着するまで預金を動かせません。しかし、相続手続きが長引く間にも葬儀費用や当面の生活費は待ってくれません。そこで2019年の民法改正で新設されたのが「預貯金の仮払い制度」です。この制度を利用すれば、遺産分割が完了する前でも一定額の預金を引き出すことが可能となりました。相続人全員の合意が揃っていない場合の緊急措置として、次の2つの方法があります。
方法① 金融機関で直接仮払い請求をする
家庭裁判所を介さず、各相続人が直接金融機関に対して預金の一部払戻しを請求できます。
必要書類(被相続人の死亡の事実と相続人であることを証明する戸籍類、本人確認書類など)を提出すれば、各金融機関ごとに一定額まで仮払いを受けることが可能です。具体的な払戻し可能額は次の計算式で定められています:
- 払戻可能額 = 相続開始時の預貯金残高 × 1/3 × 請求者の法定相続分(ただし上限150万円まで)。
例えば、亡くなった方の口座残高が600万円で、請求者(相続人)の法定相続分が1/4(25%)の場合、600万円 × 1/3 × 1/4 = 50万円
となり、50万円を上限に仮払い請求ができます。
注意すべきは、この仮払いで受け取った金額は最終的な遺産分割の際に自身が取得する額の一部とみなされる点です(簡便のため先取りして受け取っているだけで、最終分配額から差し引かれると考えればよいでしょう)。
なお、金融機関によって必要な具体的手続きは多少異なります。一般的には各相続人の戸籍、印鑑証明書、相続人であることを証する書類を提出し、法定相続分に応じた仮払いを受ける形です。払戻しにあたって他の相続人の同意は不要なので、たとえ他の相続人と揉めていても、自身の法定相続分に応じた一定額は先に受け取れるわけです。
ただし、この制度にも限度があります。1つの金融機関から仮払いできる額は最大150万円までに制限されています。故人の預貯金が巨額であっても、150万円を超える分はこの方法では引き出せません。また、預金残高が少額の場合は「1/3×法定相続分」の計算結果が150万円未満となり、その計算額が上限となります。
方法② 家庭裁判所に仮払いの許可を申立てる
もう一つの方法は、家庭裁判所の許可を得て仮払いを受ける手続きです。
既に遺産分割の調停・審判を申し立てている場合に利用できます。具体的には、調停や審判の事件係属中に「預貯金の仮分割の仮処分」を家庭裁判所に申し立て、裁判所が相当と認める金額の払戻しを命ずる審判(仮処分決定)を出してもらいます。
この場合の払戻し可能額は、家庭裁判所が個別事案に応じて認めた額となります。金融機関で直接請求する方法とは異なり、計算式や150万円といった画一的な枠はありません。必要性が高いと判断されれば、150万円を超える額でも仮払いが許可される可能性があります。
もっとも、家庭裁判所が仮払いを認めるためには一定の条件があります。典型例として、「相続人の当面の生活費や医療費の支払いなど緊急の事情があり、仮払いの必要性が高いこと」「仮払いを認めても他の相続人の利益を不当に害さないこと」が求められます。
この審判書(または決定書)を銀行に持参すれば、銀行はその金額の払戻しに応じます。なお、家庭裁判所での仮払い手続きを利用するには調停・審判事件の係属が前提ですので、単に「仮払いだけしてほしい」という申立てはできません。一連の遺産分割手続きの中で、付随的に仮払いを求めるイメージです。
家庭裁判所での遺産分割調停・審判による解除の流れと必要書類
相続人間で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所における遺産分割の調停(話し合いの場)や審判(裁判官の判断)によって預金の分配を決めることになります。以下では、調停・審判を経て口座凍結を解除するまでの一般的な流れと、押さえておくべき必要書類について説明します。
① 遺産分割調停の申立て: 相続人の一人または複数が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。

② 調停手続き(話し合い): 家庭裁判所の調停委員会(調停委員2名と裁判官1名)が間に入り、相続人同士の話し合いをサポートします。調停期日は通常1〜2ヶ月に1回程度の頻度で開かれ、各当事者が別々に調停委員と話す形で進められます。預金を含む遺産の分け方について各相続人の希望や主張を出し合い、合意点を探ります。調停はケースによりますが半年から1年程度で合意に達することもあれば、揉め具合によっては1年以上長期化することもあります。

③ 調停成立 or 不成立: 話し合いの結果、相続人全員が合意すれば調停調書(調停成立の内容を記載した裁判所の公式文書)が作成されます。この調停調書は確定判決と同じ効力を持ち、預金を含む遺産分割の最終的な取り決めを証明するものです。調停調書には「〇銀行〇支店の預金口座○○号の預金残高全額を長男○○が取得する」「長女○○は長男に対し預金の中から△△円を支払う」等、具体的な分配内容が明記されます。調停が成立しなかった場合(相続人の一部が最後まで不同意だった場合)は、調停は不成立となり自動的に遺産分割審判に移行します。

④ 遺産分割審判(裁判官の判断): 調停で合意できなかった場合、家庭裁判所の審判手続で最終決定が下されます。審判では裁判官が法律に則り預金を含む遺産の分割方法を決定します。基本的には各相続人の法定相続分やこれまでの協議内容、寄与度・特別受益などを考慮して判断されます。

⑤ 凍結解除の手続き: 調停調書が作成された場合や審判が確定した場合、それをもって銀行口座の凍結解除手続きを行います。銀行には以下の書類を提出します:
- 調停調書謄本 または 審判書謄本(原本または正本)。審判書の場合は判決が確定したことを証明する審判確定証明書も添付。
- 預金を取得することになった相続人の印鑑証明書。
調停調書や審判書は公的な分割結果を示す書面ですので、銀行はそれに従って払戻しに応じます。
例えば調停調書に「当該預金口座の残高全額を長男が取得する」とあれば、銀行は長男に対して払戻しを行います。
家庭裁判所の手続きを経た場合、遺産分割協議書は不要であり、戸籍類も調停調書等で相続人が確定しているため簡略化されることがあります(銀行によっては補助的に戸籍提出を求めることもありますが、基本的には調書・審判書が最重要書類です)。調停・審判を利用したケースでは、手続完了までに相応の時間がかかりますが、正式な裁判手続きを経ている分、銀行手続き自体は書類提出のみで円滑に進む傾向があります。
口座凍結解除の際に想定される実務上のトラブルとその対応
預金口座の凍結解除手続きは、多くの書類を揃え相続人全員の協力を得て行う必要があるため、様々な実務上のトラブルが生じる可能性があります。ここでは典型的なトラブル事例と、その対処法を解説します。
他の相続人が協力しない場合
ケース: 相続人のうち一人でも、遺産分割協議に非協力的だったり、必要書類への署名押印を拒んだりすると、口座凍結の解除手続きは進みません。例えば長男と次男が相続人の場合で、長男が「預金は自分が全部使う」と主張して協議に応じない、といったケースです。
対処法: 家庭裁判所での調停や審判を利用するしかありません。一人でも同意しない相続人がいる限り、銀行は勝手に払戻しに応じることはできないためです。まずは調停申立てを行い、公正な第三者(調停委員)の下で話し合いを促します。それでも協力しない場合は審判で強制的に決定を下してもらいます。
調停・審判では、非協力な相続人にも呼出状が届きますので、裁判所から手続きに参加するよう促されます。他の相続人の協力が得られないまま放置すると預金は引き出せないまま凍結が長期化するため、弁護士の助力も得て法的手続きを検討することが望ましい場面が多くあります。
相続人の所在が不明な場合
ケース: 相続人の中に連絡先不明者・行方不明者がいる場合です。たとえば、被相続人の子の一人が長年音信不通でどこにいるか分からない、といった状況です。この場合も相続人全員の合意を得ることが物理的に不可能であり、通常の手段では口座凍結を解除できません。
対処法: 家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立て」を行います。不在者財産管理人とは、行方不明の人に代わってその財産を管理する人です。家庭裁判所が選任した管理人(通常は利害関係のない弁護士等)が不明者の代理人として遺産分割協議に参加し、不明者の代わりに同意・署名押印することで、有効に遺産分割協議を成立させることができます。
また、不明者が生死不明で7年以上経過している場合には「失踪宣告」の申立てを検討することもあります。失踪宣告が認められると不明者は法律上死亡したものとみなされるため、その相続人(例えば不明者に子がいればその子)が代わりに相続権を取得し、手続きを進められるようになります。ただし失踪宣告はハードルが高く時間もかかるため、現実にはまず不在者財産管理人で対応するのが一般的です。
相続人に判断能力を欠く人(未成年者・認知症高齢者)がいる場合
ケース: 相続人の中に未成年者や認知症などで判断能力に問題がある人がいる場合です。例えば、亡くなった父の相続人が母(認知症を患っている)と未成年の子2人であるケースなどが挙げられます。このような場合、その相続人は法律行為を単独で行えないため、遺産分割協議に有効に参加させるには特別な配慮が必要です。
対処法: 状況に応じて代理人や後見人を選任する手続きを取ります。
まず、未成年者の場合、通常は親権者が財産を管理しますが、その親権者自身が同一の相続に利害関係を持つ(例えば親も相続人の一人)場合は利益相反となります。このときは家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申立て、未成年者のために利害関係のない代理人(親族や弁護士等)を立ててもらう必要があります。特別代理人が選任されれば、その代理人が未成年者に代わって協議書に署名押印し、協議に参加します。特別代理人候補として身内の叔父・叔母・祖父母などを指定することもできますが、家庭裁判所が適任者を判断して職権で弁護士・司法書士を選任することも多いです。
一方、成年後見が必要な認知症高齢者などが相続人の場合は、家庭裁判所への後見開始の申立てを行い、成年後見人を選任してもらいます。成年後見人(親族や専門職後見人)は本人に代わって遺産分割協議に参加できます。ただし、後見人が本人に代わり遺産分割協議をする際には家庭裁判所の別途許可が必要とされており、後見人単独では勝手に協議内容を決められません。許可を得て合意が成立すれば、後見人が代理署名して協議書を完成させます。
なお、相続人全員がそのような代理人・後見人を含めて揃わないと銀行は手続きに応じませんので、未成年者や判断能力の不十分な相続人がいる場合は早めに家庭裁判所へ申し立てを行いましょう。
弁護士に依頼するメリット
預金口座の凍結解除手続きは、戸籍収集から相続人間の調整、銀行や裁判所への対応まで煩雑かつ専門的です。そこで相続問題に詳しい弁護士に依頼するメリットについて確認しておきましょう。専門家のサポートを受けることで、以下のような利点があります。
手続きの代理・代行
弁護士は相続手続き全般を代理人として進めることができます。銀行への届出や必要書類の収集、家庭裁判所への申立書作成・提出など、面倒な手続きを代行してもらえます。
例えば被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍・住民票など、多くの書類集めは専門家に任せることで迅速に完了します。ご自身で動く負担を大幅に軽減できるでしょう。
遺産分割協議や調停・審判での交渉力
相続人間の話し合いが難航している場合、弁護士の交渉力が状況を打開することがあります。他の相続人に法的な観点から冷静に説得を試み、円満解決に導くことが期待できます。
また、調停や審判では弁護士が代理人として出席し、依頼者の主張を法律的に整理して伝えてくれます。専門知識がなければ、自分に不利な提案を受け入れてしまっても気付かないことすらありますが、弁護士がいれば適切な遺産分割になっているかチェックしながら進められます。
想定外のトラブルへの対応
前述のような相続人の所在不明や未成年者の特別代理人選任、不在者財産管理人選任など特殊な事態にも弁護士は精通しています。状況に応じて必要な法的手続きをアドバイスしてくれるため、最善の解決策を逃しません。
例えば行方不明の相続人がいるケースでも、弁護士に依頼すれば代理人として所在調査や家庭裁判所への申立てを迅速に代行してもらえます。
手続きのスピードアップと安心感
弁護士に依頼することで、手続きの漏れや不備が防がれ、結果的にスムーズに相続手続きを終えられる可能性が高まります。書類の不備で銀行に何度も通う、といったロスも避けられます。
また法律のプロがついている安心感から、精神的ストレスも軽減されるでしょう。とくに相続人同士が直接やり取りすると感情的対立が深まるケースもありますが、弁護士が窓口になることで冷静な話し合いが期待できます。
紛争予防と将来のリスクヘッジ
弁護士は現在進行中の問題解決だけでなく、将来起こり得るトラブルを見据えて動いてくれます。例えば遺産分割協議書の文言を法的にチェックし、後から無効主張されないようにしたりします。
さらに、必要に応じて遺言書作成や生前贈与の相談に発展させ、将来の相続トラブルそのものを予防するサポートも可能です。
このように、専門的知識と経験を持つ弁護士に依頼することは多くのメリットがあります。特に預金口座の凍結解除について「何から手を付けていいか分からない」「相続人間でもめていて進まない」という場合、早めに専門家に相談されることをお勧めします。スムーズに相続手続きを完了し、ご自身の正当な相続分を確実に受け取るためにも、弁護士の力を上手に活用してください。
まとめ
預金口座の凍結は、相続が発生した際に避けて通れない手続きです。その法的根拠は相続財産の公正な管理にあり、解除するには相続人全員の合意かそれに代わる裁判所の判断が必要となります。遺産分割協議が整えば必要書類を揃えて銀行で手続きすれば解除できますが、協議がまとまらない場合は家庭裁判所での調停・審判で決着をつけることになります。
平成28年の最高裁決定以降、預貯金の取り扱いは厳格化されましたが、その反面、平成31年施行の新制度により遺産分割前でも一定額の仮払いを受け取れる道も開けました。相続実務では様々な困難が生じ得ますが、不在者財産管理人や特別代理人の制度を活用すれば対応可能です。
複雑なケースや争いがある場合は、ぜひ早めに弁護士等の専門家に相談し、適切な手順で円滑に預金を取り戻しましょう。家族の大切な遺産を正当に承継し、今後に備えるために、本記事の内容がお役に立てば幸いです。