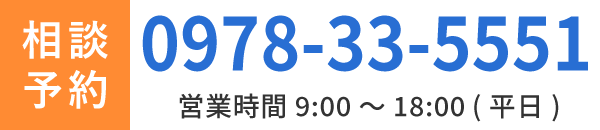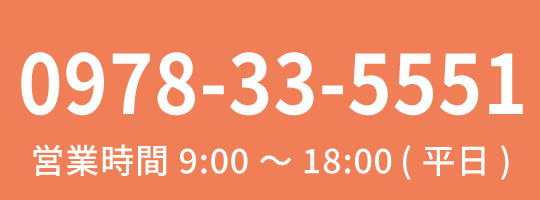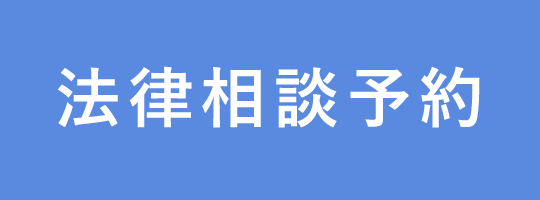BitTorrentやuTorrentなどのトレントソフトを使用して映像作品(映画やAVなど)をダウンロードしたとして、著作権者から発信者情報開示請求の意見照会書が届くことがあります。
当事務所ではトレントソフトによる著作権侵害事件を多数取り扱っており、日ごろからこのようなソフトに関する案件の対応や注意喚起を行っています。
このページの目次
トレントソフト利用で発信者情報開示請求を受ける理由
トレントソフトとは
近年、BitTorrent(ビットトレント)やνTorrentといったトレントソフトを使ったファイル共有による著作権侵害に対し、著作権者が法的措置をとるケースが増加しています。トレントソフトはP2P(ピア・ツー・ピア)方式でファイルをやり取りする仕組みであり、ファイルをダウンロードすると自動的にそのファイルを他のユーザーへアップロード(送信)してしまいます。
そのため、映画・アニメ・アダルト動画など著作物をダウンロードしただけのつもりでも、実際にはそのファイルの一部を他人に提供しており、公衆送信権(送信可能化権)侵害という違法アップロード行為を行っていることになります。著作権法では、権利者の許可なく著作物をアップロードする行為は違法です(著作権法23条)。
どのようにしてトレントソフトの使用が判明するのか
著作権者(映画会社や出版社、AV制作会社など)は、自身の著作物が違法に共有されているのを発見すると、専門の監視システム(例:P2Pファインダー等)を使ってアップロードに使用されているIPアドレスを特定し、そこから契約者情報を割り出す手続きに入ります。具体的には、当該IPアドレスの契約者を管理するインターネットプロバイダに対し、その契約者の氏名・住所などを開示するよう求めるのです。これを「発信者情報開示請求」といいます。
こうした発信者情報開示請求をプロバイダが受けると、プロバイダは契約者(インターネット利用者)に対し通知を行います。それが「発信者情報開示請求に係る意見照会書」と呼ばれる書面です。トレントソフトで著作物をダウンロードしてしまった方の元に突然この書面が届くことがあり、そこで初めて自身の行為が発覚し、法的手続きが進んでいることを知るケースが多いです。
発信者情報開示請求と「意見照会書」とは
発信者情報開示請求とは、インターネット上で権利侵害(著作権侵害や名誉毀損など)があった際に、被害を受けた権利者がプロバイダに対し加害者の情報開示を求める法的手続きです。プロバイダは「プロバイダ責任制限法」に基づき、権利侵害が明白で被害者が損害賠償請求等を行う正当な理由がある場合に、契約者(発信者)の氏名・住所などの情報を開示することができます。
しかしプロバイダは契約者のプライバシーにも配慮する必要があるため、いきなり権利者に情報提供はしません。まず契約者本人に対し「開示してよいかどうか」「異議があるか」を確認します。そのために送られるのが「発信者情報開示請求に係る意見照会書」(単に「意見照会書」とも呼ばれます)という書面です。
意見照会書には、開示を求めている権利者や対象となっている著作物・侵害行為の日時などが記載され、契約者であるあなたに対し、一定の回答期限までに開示に「同意」するか「不同意」(不同意=開示に反対)を表明するよう求めています。一般的にこの回答期限は通知到達から約2週間程度に設定されることが多いです。意見照会書が届いた段階で、著作権者側はすでにあなたの行為を把握し法的手続きを進めている最中です。そのため、この通知への対応を誤ると、裁判手続によって契約者情報が開示されてしまい、最終的に高額の損害賠償請求や刑事責任の追及に発展するおそれがあります。
意見照会書は単なる警告ではなく法的手続きの一環です。放置すれば手続きが進んでしまいます。次章で詳述するように、意見照会書を受け取ったら決して無視せず、適切な対応を取ることが極めて重要になります。
意見照会書が届いた場合の対応策
意見照会書を受け取った場合、まず決められた期限内に対応することが必須です。対応策としては大きく分けて以下の三つの選択肢があります。
- 開示に「同意」する(情報開示を受け入れる)
- 開示に「不同意」と回答する(情報開示に反対し異議を述べる)
- 何も「回答しない」(無視・放置する)
それぞれの場合に今後どうなるか、注意点は何かを見ていきましょう。
開示に同意する場合
意見照会書に対し「同意」と回答すると、プロバイダはあなたの契約者情報(氏名・住所等)を請求者である権利者側に開示します。つまり、あなたの氏名や住所が著作権者(またはその代理人の弁護士)に伝えられることになります。
開示に同意したからといって直ちに何らかの支払い義務が発生するわけではありませんが、その後は権利者から直接あなたに対する請求(損害賠償の要求)が行われる段階に進みます。一般的には、プロバイダから情報が開示されてしばらくすると、権利者の代理人弁護士からあなた宛てに内容証明郵便などで示談(金銭支払いによる和解)の提案が届くことになります。
もっとも、仮にアップロードしたことが事実であっても、全てのケースで必ずしも同意すれば早期に適切な解決ができるというわけではありません。
開示に同意することが適切な解決に必ずしも結びつかない場合や、そもそも開示されるべきではない場合もありえるため、開示し同意するかどうかについても、弁護士に相談すべき専門的な判断を要する項目であるといえます。
そのため、同意すべきであろうと思われる場合でも、念のため事前に弁護士への相談をすることが望ましいと考えられます。
開示に不同意と回答する場合
自分の情報開示に不同意(反対)の意思表示をすると、プロバイダはその回答も踏まえて開示に応じるかどうかの判断を行います。法律上、権利侵害が「明白」であり開示の必要性が認められる場合にはプロバイダは情報開示できると定められています。しかし契約者から不同意の回答があった場合、プロバイダとしては慎重を期すため、権利者に対しては直ちに開示せず、最終的には権利者側が裁判所に開示の仮処分命令申立て等の法的手続きをとって開示を実現する流れになることが多いです。
ただし、トレントによる著作権侵害の場合、ほとんどの場合で権利侵害の事実が明白であるため、不同意と回答しても最終的には開示が認められてしまうということがあります。
不同意回答の現実的な意味は、「開示までのプロセスを遅らせる(ハードルを一段階上げる)」ことにあります。トレントソフトを使用している方は、複数のファイルをダウンロードしていることも多く、使用状況や損害額の全容をある程度把握するためには、一定の期間が必要です。
そのため、不同意回答する間に意見照会書が複数回届くことを確認し、損害額の全容を予想しつつ示談交渉の準備を進めるということも場合によってはあり得ます。
もっとも、不同意の回答も、どのような理由でもかまわないわけではありません。
意見照会書の説明文にも記載がありますが、弁護士などの専門家に相談のうえ、代理人として記載してもらうことが望ましい場合も多いです。
そのため、意見照会書への回答についても、弁護士へ相談の上で行ったり、弁護士に依頼して回答してもらった方がよいとされています。
意見照会書を無視・放置した場合
意見照会書に対して何も回答せず無視した場合、プロバイダは回答期限までに契約者から意見が示されなかったものとみなし、特に異議がないものとして扱います 。その結果、あなたの情報は開示されてしまうと考えてよいでしょう。実質的には「開示に同意した場合」と同じ結果になります。
無視した場合の問題はそれだけではありません。権利者側から見ると、意見照会に何の回答もしないのは非常に不誠実な対応に映ります。したがって、意見照会書の放置はお勧めできません。
対応方針に悩んだら弁護士に相談を
意見照会書への対応はケースバイケースで最善策が異なります。上述のように、基本的には「権利侵害の事実があるなら最終的に示談交渉となる」というのが多数の場合に当てはまりますが、中には不同意で主張すべき事情があるケースも存在します。いずれにせよ、自分一人で判断するのが難しい場合は早めに弁護士に相談し、専門的見地からアドバイスを受けることを強くお勧めします。意見照会書が届いたタイミングで弁護士に相談することは非常に重要です。その段階であれば今後の戦略に幅が持てるため、被害を最小限に抑えるチャンスにもなります。
発信者情報開示後に起こり得ること
意見照会に同意するか否かにかかわらず、最終的にプロバイダから発信者情報(氏名・住所等)が開示されてしまった場合、次のステップとして想定されるのは権利者からの直接の請求です。情報開示後に権利者側で起こり得る主な展開を確認しましょう。
権利者からの損害賠償請求・示談交渉
プロバイダからあなたの情報を得た著作権者(またはその代理人弁護士)は、通常まず損害賠償請求の通知を送ってきます。これは多くの場合、「○○の著作物の違法アップロードによって損害を受けた。◯◯万円を支払って和解するよう求める」といった内容の書面です。ここには、請求額や支払い期限、連絡先などが記載されています。
この段階では、著作権者側もできれば裁判をせず示談(和解)による解決を望んでいることが多いです。したがって、「○日までに連絡をください」などと書かれ、話し合いの機会が提示されます。通知を受け取った側(あなた)は、その示談提案に応じて交渉するか、あるいは請求に納得できなければ交渉して減額等を求めるか、場合によっては争う(支払いを拒否する)かを判断する必要があります。
もっとも、多くの事案で、動画1本あたりの和解金、同一メーカーの動画に関する包括的な和解金がそれぞれ数十万円単位で示され、減額されないことも多いです。
何らの理由も示さずに、減額交渉等を行う事は現実的ではないといえるでしょう。
弁護士が代理人となった場合は、法的根拠のある請求額を検証し、交渉を行う事となります。
民事訴訟に発展する場合
権利者からの示談提案に応じず示談が成立しない場合、次の段階として考えられるのは民事訴訟です。権利者はあなたを相手取り、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起することになります。
場合によっては請求額が示談交渉段階よりも高額になる可能性もあります。ただし、日本の裁判実務では著作権侵害における損害額の立証は簡単ではなく、現実的には一定の相場に基づいて認定されることが多いです。
万一、訴訟提起も無視して放置してしまうと、裁判所は被告不在のまま審理を進め請求内容を認める判決を下します。請求どおりの損害賠償額の支払いを命じる判決が確定すれば、強制執行等により賠償金を回収されるリスクも生じます。
刑事上のリスクについて
著作権侵害は民事上の損害賠償問題であるだけでなく、刑事罰の対象ともなり得ます。実際に、BitTorrentを利用した大規模な海賊版配信事件で逮捕者が出た例も報道されています。著作権法119条は、著作権を侵害する行為に対し10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(またはその併科)という非常に重い法定刑を定めています。また、違法と知りながら著作物をダウンロードした行為にも2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科される可能性があります。
もっとも、全てのケースで直ちに逮捕・起訴されるわけではありません。権利者が被害届を提出し警察が捜査を開始しない限り、刑事事件には発展しません。個人が私的に行っていた違法ダウンロード・アップロード案件では、まず民事上の示談で解決が図られ、示談が成立すれば刑事追及を見送るということもあります。権利者側としても、損害賠償が得られれば刑事処罰までは望まないケースが多いでしょう。
複数の開示請求を受けた場合の注意点
トレントソフトを長期間利用していた方などは、複数の著作物について次々と開示請求を受ける可能性があります。例えば、あるAV動画で1件、人気漫画で1件、といった具合に別々の権利者から複数通の意見照会書が届くケースも珍しくありません。そのような場合の注意点を整理します。
まず、単一の著作物についての請求であれば示談金も数十万円程度で済むことが多いですが、作品数が増えると請求総額は積み上がる点に留意が必要です。これは個人にとって大変な負担です。
また、開示請求が同時期にまとまって来るとは限りません。ある権利者からの通知に対応しているうちに、数か月後に別の権利者から新たな通知が届くといったことも起こり得ます。
そのため、損害額や支払額、相手方の数が明確にならないうちは、早期に示談をするのは望ましくないというケースもあり得ます。これらについても状況を見極めながら判断する必要があるため、専門家である弁護士へ依頼するのが望ましいことが多いです。
一人で抱え込まず、早めに弁護士に相談して全体の戦略を立てることが重要です。当事務所でも「気付いたら次々に通知が届いて困っている」というご相談を多数受けていますが、個別案件ごとの対応策だけでなく全件のトータルで依頼者の負担が最小になる解決策を検討し、実行しています。
よくある質問(FAQ)
最後に、トレントソフトによる開示請求に関して寄せられるよくある質問と回答をQ&A形式でまとめました。同じような状況で悩んでいる方の参考になれば幸いです。
Q1. トレントソフトで動画をダウンロードしただけでも違法になるのですか?
A. はい、違法になる可能性があります。トレントソフトの場合、自動で他者へのアップロードが行われているため、「ダウンロードしただけ」のつもりでも実際には違法なアップロード行為をしています。したがって、権利者の許可なくトレントでファイルを入手すれば、その時点で著作権侵害(公衆送信権の侵害)に該当します。
Q2. 自分ではアップロードした覚えがないのですが、それでも責任を問われますか?
A. 残念ながら問われます。トレントソフトの仕組み上、一度ダウンロードに参加すると、自分が意図しなくても自動的にファイルの断片を他のユーザーにアップロードしてしまうためです。利用者本人にアップロードの意識がなくても、法律的にはアップロード(送信可能化)行為を行ったことになります。
実際、トレントソフトをインストールする際には「ダウンロードしたファイルを他者と共有する可能性がある」旨の注意が表示されます。そのため「知らない間にアップロードしていた」という言い訳は基本的に通用しません。このような弁解は裁判所でも認められないことが、高等裁判所の判例で示されています。
Q3. 「発信者情報開示請求に係る意見照会書」とは何ですか?
A. これはプロバイダ(インターネット接続業者)が、権利者から発信者情報の開示請求を受けた際に契約者であるあなたに送付する問い合わせ文書です。権利者(著作権者)が裁判手続きやプロバイダ責任制限法に基づき、あなた(発信者)の氏名・住所等の開示を求めたとき、プロバイダは直ちに開示する前に契約者の意見を聴くことになっています。そのために送られるのが意見照会書です。
意見照会書には、どの権利者がどの著作物について開示請求を行っているかが記載されています。そして「あなたの情報を開示してもよいか?」について、一定の期限までに「同意」か「不同意」か回答してくださいと求める内容になっています。要は「開示していいですか?」という質問状だと考えてください。回答期限はおおむね2週間程度に設定されていることが多いです(書面に具体的な日付が明記されています)。
Q4. 意見照会書を無視するとどうなりますか?
A. 無視(未回答)の場合、プロバイダは「発信者から特に異議はなかった」とみなして情報開示に応じることになります。したがって、期限まで放置すればあなたの氏名住所は権利者に渡ってしまうと考えてよいでしょう。その後、権利者から損害賠償請求が直接あなたに届く展開になります。
Q5. 「同意」するか「不同意」するか迷っています。どちらが良いでしょうか?
A. 迷った場合は、一度弁護士に相談して判断を仰ぐことを強くお勧めします。専門家であれば、不同意を主張すべき特殊な事情がないかを見極めた上で、今後の見通しも踏まえたアドバイスをしてくれるでしょう。
Q6. 発信者情報が開示された後はどうなるのですか?
A. あなたの氏名住所が権利者に知られると、次は権利者から直接あなたへの損害賠償請求が届きます。通常は権利者の代理人弁護士から特定記録郵便などで通知が来て、違法アップロードによって被った損害の金額を支払うよう要求されます。
通知書には請求額や支払い期限、連絡先などが記載されています。あなたとしては、示談に応じて支払うか、金額等に納得できなければ減額交渉を行うか、といった対応を検討することになります。多くの場合、話し合いによって示談が成立すれば訴訟は回避できます。示談に応じて請求額を支払えば、民事上の責任は果たしたことになり、相手方もそれ以上の追及(裁判など)はしてきません。
逆に、示談に応じなかったり連絡を取らず放置したりすると、相手は訴訟を検討する段階に入ります(詳しくは次のQ&A参照)。いずれにせよ、開示後は権利者と直接向き合う段階になるため、早めに弁護士に代理交渉を依頼することを検討すべきタイミングです。
Q7. 示談金(請求金額)はどのくらいになりますか?
A. ケースバイケースですが、一般的な相場は数十万円程度とされています。ただし、これは著作物1作品あたりの目安とお考えください。ダウンロード/アップロードした作品が複数ある場合、権利者ごとに請求が発生しますので合計金額は大きくなります。
なお、提示された金額がどうしても高すぎて支払えない場合でも、交渉による減額や分割払いに応じてもらえるケースは少なくありません。
Q8. 支払いに応じないで放っておくとどうなるですか?
A. 権利者からの請求を無視したり示談交渉に応じなかったりすると、民事訴訟を起こされる可能性があります。訴訟になれば、裁判所から訴状が届き法的な場で争うことになります。最終的に和解できず判決となれば、裁判所により損害賠償の支払い命令(判決)が下されます。
このように、請求を放置することは得策ではありません。どうしても請求内容に納得できず裁判も辞さないという場合以外は、やはり示談交渉による解決を図るのが一般的です。もし訴訟を起こされてしまった場合でも、裁判中に和解する余地はありますので、早めに弁護士に依頼して適切に対応するようにしてください。
Q9. 逮捕されたり刑事事件になる可能性はありますか?
A. 可能性はゼロではありませんが、多くの場合民事上の問題として処理され、刑事事件にまで発展しないのが実情です。著作権法違反は親告罪(被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪)ですので、権利者が警察に被害届を出し告訴しない限り刑事事件にはなりません。示談が成立すれば通常、権利者は告訴を取り下げるか見送ります。
ただし、例えば悪質な大規模共有(継続的に大量のファイルをアップロードしていたようなケース)では、示談如何にかかわらず刑事摘発が行われることもあります。
このように、弁護士に依頼することで法律面・交渉面・精神面で多くのメリットが得られます。一人で悩んで状況を悪化させる前に、ぜひ専門家の力を借りて早期解決を図ってください。
Q10. 弁護士費用が心配ですが、いくらくらいかかりますか?
A. 弁護士費用は依頼する内容や事件の難易度によって異なります。当事務所では明確な費用基準を設けており、例えば「意見照会書への回答のみ」のご依頼か「その後の示談交渉まで含めた依頼」かで料金プランが分かれています。詳しくは当事務所ホームページの弁護士費用のページに掲載しておりますのでご参照ください。
当事務所は九州全域の案件に対応中
当事務所では、IT企業などで法務部長経験のある弁護士が対応しています。
事務所は大分県宇佐市にありますが、IT関係やトレントソフトの案件については大分県全域や福岡県、熊本県など九州全域で対応しております。
遠方の方にはzoomによるオンライン相談も行っておりますので、遠方の方も安心してすぐにご相談いただけます。