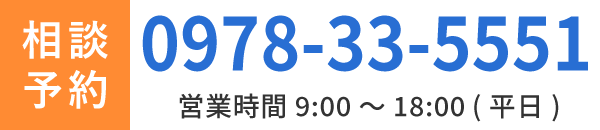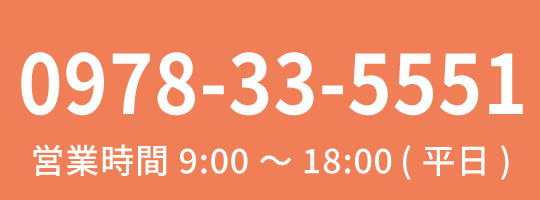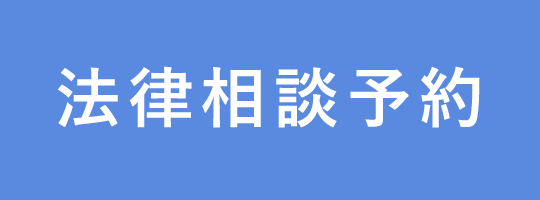相続が発生した際に、被相続人(故人)の銀行預金を無断で引き出すトラブルは後を絶ちません。また、相続前でも高齢の親の預金を家族が許可なく引き出してしまい、後に相続人間で問題となるケースも増えています。
ここでは「預金の無断引き出し」について、弁護士の視点から詳しく解説し、トラブルへの対処法や予防策を紹介します。最後には弁護士に相談するメリットも述べますので、ぜひ参考にしてください。
このページの目次
相続における預金の無断引き出しとは
預金の無断引き出しとは、本人や他の相続人の了承を得ずに銀行口座からお金を引き出してしまう行為です。状況として大きく二つに分かれます。
相続発生後に無断で預金を引き出すケース
被相続人が亡くなった後、本来は遺産分割や相続手続きが必要な預貯金を、一部の相続人が勝手に下ろしてしまう場合です。
例えば、父が亡くなった直後に長男が銀行から預金を引き出し、他の兄弟に知らせないまま自分の用途に使ってしまう、といったケースです。口座名義人が死亡すると銀行口座は原則凍結されますが、死亡届前にキャッシュカードや通帳を使って引き出されることがあります。このような遺産の使い込みは、他の相続人の取り分を侵害するため大きなトラブルに発展します。
相続発生前に家族が無断で預金を引き出すケース
被相続人がまだ存命中(生前)にもかかわらず、家族が本人の預金を許可なく引き出してしまう場合です。特に本人が高齢で認知症など判断能力が低下していると、子どもなどが預金管理を任されることが増えます。
しかし、中には親名義の口座から生前に多額の預金を無断で引き出し、自分の生活費等に流用してしまう例もあります。その結果、他の相続人から「勝手にお金を使い込んだのではないか?」と疑われ、紛争になることがあります。
問題点と具体例
これらの行為には法的な問題点とリスクがあります。まず、生前・死亡後いずれの場合も「無断」である以上、本人または他の相続人の権利を侵害している可能性があります。
💡 具体例:「祖母が亡くなり、相続人である伯母が祖母名義の預金を無断で引き出していた」というケースでは、他の相続人が発覚後に返還を求め、大きな争いに発展しました。最終的に訴訟となり、伯母は使い込んだ預金の一部である2000万円以上を返還する結果となった例があります。このように、無断引き出しは深刻な相続トラブルにつながるのです。
無断引き出しの法律上の扱い
無断で預金を引き出した場合、法律上どのように扱われるのでしょうか。相続人間の財産権の関係や、引き出した時期(生前か死亡後か)によって適用される法律や手続きが異なります。また、引き出し時の状況(本人の意思能力の有無など)も重要なポイントです。
共同相続人間の財産権と遺産の帰属
被相続人が亡くなると、その遺産(財産)は原則として相続人全員の共有状態になります(民法898条)。複数の相続人がいる場合、死亡と同時に各相続人が法定相続分に応じた権利を持つものの、遺産分割が完了するまでは特定の財産について単独で自由に処分することはできません。
かつての判例(最高裁昭和29年4月8日判決)では「預金債権のような可分債権は相続開始と同時に当然分割され各相続人に帰属する」とされていましたが、最高裁判所大法廷平成28年12月19日決定によりこの見解が変更されました。
しかし、現在では銀行預金も遺産分割の対象とされ、遺産分割前に個別の相続人が勝手に引き出すことは許されないとの判断が確立しています。つまり、相続開始後の預金は相続人全員の共有財産であり、一人の相続人が無断で引き出せば他の相続人の権利を侵害することになります。
預金者の意思能力(認知症の場合)と不当利得
被相続人の生前に預金が引き出されたケースでは、その行為が被相続人本人の意思に反していたかが重要になります。
もし引き出し時に本人が認知症などで正常な判断能力(意思能力)を欠いていた場合、本人の意思に基づく同意はなかったと考えられます。この場合、その無断引き出しは本人の財産権の侵害であり、法律上「不当利得」や「不法行為」に該当する可能性があります。
たとえば、判断能力が低下した親の預金を子が勝手に引き出して自分のために使っていた場合、親(被相続人)はその子に対して不当利得返還請求権(民法703条)や損害賠償請求権(民法709条)を取得し得ます。そして親が亡くなれば、その請求権は相続人に引き継がれます。つまり、他の相続人は引き出した本人に対して被相続人の権利を代わりに行使して返還を求めることができるのです。
重要なのは、「無断」であること、すなわち被相続人本人が同意していなかったことを証明できるかどうかです。本人が生前に「○○に〇万円渡した」と明確に了承・贈与していたのであれば問題は生じません。
しかし、認知症で判断能力が無い状態を利用して引き出していた場合や、本人は同意していないのに「介護費用だ」などと言い訳して引き出していた場合には、不当利得として返還義務が生じる可能性があります。実際の裁判でも、被相続人が高齢で判断能力が低下していた中、子が預金を管理し「生前贈与だ」と主張したものの証拠がなく、不当利得として返還義務を認めた判例があります。
なお、認知症などの際に意思能力を破断する指標として、長谷川式認知症スケール(HDS-R)というものが使用されることがあります。その説明は、以下のとおりです。
長谷川式認知症スケール(HDS-R)と意思能力の関係
HDS-Rの概要と評価基準
改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)とは、日本で広く用いられている認知症のスクリーニング検査です。質問項目は9つで、5分から10分ほどで行われます。満点は30点であり、21点以上を正常、20点以下を認知症の疑いとする基準が一般的です。ただし、HDS-Rは簡易検査であるため、認知症の確定診断に用いることは適切ではなく、あくまで補助的な指標として扱われています。
法律上の意思能力との関連性
法律行為が有効となるためには、当事者に意思能力(法律行為の意味や結果を理解し判断する能力)が求められます。認知症の高齢者の場合、この意思能力の有無が争点となることが多く、裁判上ではHDS-Rのスコアが重要な証拠として利用されています。一般的な傾向としては、20点以上であれば意思能力があるとされるケースが多く、15点前後になると判断が分かれ、10点未満では意思能力が否定される例が増えます。
もっとも、裁判所はHDS-Rの点数だけで意思能力を機械的に判断することはありません。意思能力の判断には、そのほかの医学的所見や日常の生活状況、当該法律行為の複雑さなどが総合的に考慮されます。例えば、大阪高裁平成22年9月15日判決では、「意思能力は個々の具体的状況に応じた実質的な判断が必要であり、画一的な基準に従うべきではない」と述べられています。
判例におけるHDS-R活用事例
東京地裁令和4年11月24日判決(遺言無効確認事件)では、遺言者が遺言作成の数か月前にHDS-Rが4点、その後は0点であったことなどから、高度な認知症によって遺言能力を欠いていたとして遺言が無効とされました。一方、東京高裁令和2年9月29日判決(生前贈与無効事件)では、HDS-Rスコアが7点前後であったにもかかわらず、当時の日常生活能力や他の医学的所見から意思能力が認められ、贈与契約は有効と判断されています。このように、HDS-Rの数値は重要な証拠資料となりますが、裁判所は必ずしもそのスコアだけに頼って判断するわけではありません。
無断引出し事件におけるHDS-R資料の重要性
預金の引出しが不当かどうかを裁判所が判断する際、引出時に本人がどの程度の意思能力を有していたかが争点となります。この判断材料として、HDS-Rの検査結果が利用されることがあります。例えば、東京地裁平成19年10月1日判決では、HDS-R15点のスコアについて、単独の結果のみでは意思能力の欠如を認定できないと判断し、無断引出しの主張を認めませんでした。
一方、東京地裁平成28年8月25日判決では、被相続人が重度の認知症であることが明確であり、引出した側が合理的説明を行えなかったため、無断引出しを認め、不当利得の返還を命じています。このように、HDS-Rの結果は認知症の程度を客観的に示す証拠として、重要な役割を果たします。
無断引き出しが発覚した際の対応策
もし遺産の預金の無断引き出しが発覚した場合、相続人としてどのように対処すればよいでしょうか。感情的に責める前に、冷静に事実確認と適切な手続きを進めることが重要です。以下に具体的な対応策を順を追って説明します。
①事実関係の確認
まずは本当に預金が無断で引き出されたのか、詳細を確認します。被相続人の通帳や銀行の取引明細をチェックし、死亡前後に多額の出金がないか調べましょう。銀行に問い合わせれば、相続人は亡くなった親の口座取引履歴を一定期間分取得できます(戸籍謄本などで相続人である証明が必要です)。
また、もし引き出したと疑われる相続人に委任状や代理権が与えられていた形跡がないかも確認します。たとえば、生前に被相続人から銀行手続きの委任状を受け取っていた、あるいは口座の共同名義人だったなどの事情があれば、引き出しに一定の正当性がある可能性もゼロではありません。
疑わしい出金が見つかった場合は、金額・日時・方法(ATMなのか窓口なのか)をメモし、証拠として保全しておきます。
②本人への事実確認と話し合い
次に、無断引き出しを行った疑いのある相手(相続人)に事情を確認します。相手が事実を認める場合もあれば、否認したり「○○に使った」「生前にもらったものだ」などというケースもあります。
話し合いの段階で、引き出したお金を遺産に戻す(返還する)ことで合意できれば理想的ですが、そのような事例はあまり多くはありません。話し合いで解決できる場合、遺産分割協議においてその分を差し引く形で調整することがあります(例えば、勝手に下ろした○万円をその相続人の取り分から減らすなど)。
③内容証明郵便での請求
話し合いで解決しないときは、内容証明郵便を使って正式に返還請求を行う方法があります。内容証明郵便とは、手紙の内容を郵便局が証明してくれるもので、後の法的手続きの証拠になります。
④調停や訴訟など法的手続き
内容証明を送っても相手が応じなかったり、回答が不十分な場合は、次のステップとして法的手段を検討します。具体的には以下のような方法があります。
遺産分割の調停・審判
相続人間の話し合い(協議)がまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停委員を交えて話し合いを行い、公平な解決を図ります。無断引き出しされた預金についても、前述の改正により調停の場で遺産に含めて取り扱うことが可能です。調停で合意できれば調停調書が作成され、裁判上の和解と同じ効力を持ちます。もし調停が不成立になれば審判に移行し、家庭裁判所が遺産分割方法を決定します。
しかし、無断引出しは後述のとおり不法行為や不当利得とみられるため、折り合いがつかなければ結局訴訟を提起して仕切り直す必要が出るほか、消滅時効が迫っている場合は訴訟の提起を先行させるのが一般です。
民事訴訟(返還請求訴訟)
調停とは別に、直接民事訴訟を提起する方法もあります。無断引き出しをした相続人に対し、不当利得返還請求や損害賠償請求の訴えを起こし、引き出された金銭の返還を求めます。裁判になった場合、第三者である裁判官に対して「預金を引き出した事実」「被相続人の承諾なく無断であったこと」「引き出したお金を私的に使い込んだこと」を証明する必要があります。
そのため、医療記録、通帳の記帳やATM記録、防犯カメラ映像、他の親族の証言などあらゆる証拠を集めて主張立証することになります。勝訴すれば判決に基づき返還を強制執行できますが、時間と費用がかかる点は覚悟しましょう。
以上のように、まずは証拠を押さえて話し合い、ダメなら内容証明で正式請求し、最終的には調停や訴訟とステップを踏んでいくのが一般的です。ポイントは、感情的にならず冷静に証拠を集め、筋道だった対応を取ることです。一連の対応に不安がある場合は、早めに専門家(弁護士)に相談することも検討しましょう。
無断引き出しに関する判例紹介
ここでは、預金の無断引き出しに関して参考になる裁判例(判例)をいくつか紹介します。最新の判例動向と、過去の代表的な判例から読み取れるポイントを押さえておきましょう。
銀行預金債権も遺産分割の対象となる決定
最高裁判所大法廷平成28年12月19日決定:銀行預金の相続に関する近年の最重要判例です。最高裁はこの決定で、従来の判例を変更し「銀行預金債権も遺産分割の対象となる」との判断を示しました。先に触れたとおり、以前は昭和29年の判例に基づき「預金債権は各相続人に当然分割される」と考えられていました。
しかし、本決定により預金は遺産分割前には相続人全員の共有に属することが明確化されました。その結果、相続人の一人による無断引き出しは他の相続人の承諾なしには認められないという法的基盤が強まりました。この最高裁の判断を受け、2018年の民法改正で先述の民法906条の2が制定されるなど、立法面でも無断引き出しへの対処が整備されています。
無断使い込みを巡る地裁判決
東京地方裁判所平成28年8月25日判決:被相続人の長期間にわたる預金管理を一手に引き受けていた相続人(被告)が、生前に多額の預金を引き出していた事案です。他の相続人(原告ら)は被告に対し、不法行為に基づく損害賠償か悪意の受益者としての不当利得返還を求めました。裁判所は、被告が引き出した金額の使途を具体的に説明できず、また「生前贈与だった」とする主張にも根拠がないことから、被告の財産管理行為には違法性があり、法律上の原因なく利得していると認めました。
東京地方裁判所平成25年3月28日判決:一方で、無断引き出しを主張したものの認められなかった裁判例もあります。この事案では被相続人名義の通帳を管理していた相続人(被告)が亡くなる前に預金155万円を引き出していました。他の相続人(原告)は無断で使い込まれたと訴えましたが、裁判所は「その引き出し行為が亡くなったX(被相続人)の意思に反して行われた不法行為であると認める証拠がない」こと、また「引き出した現金を自己の用途に費消した事実を認めるに足りる証拠もない」ことから、被告の不法行為責任を否定しました。
つまり、無断ではなかった可能性(被相続人の了承があった、または被相続人のために使われた可能性)が排除できず、原告の請求が棄却されたケースです。この判例は、証拠の重要性を示しています。無断引き出しを主張する側は、被相続人の意思に反していたことや私的流用された事実をしっかり立証しなければ、請求が認められないことがあるのです。
判例から読み取る実務上のポイント
以上の判例から導けるポイントとして、まず無断引き出しを立証するためには証拠固めが不可欠だということがあります。特に生前の引き出しについては、被相続人が認知症などで意思能力がなかったことや、引き出された金銭が本人の利益のためではなく引き出した者自身の利益に使われたことを示す証拠が重要です。
例えば、介護施設に入所中で本人がATMに行けない状況だったとか、引き出しと同時期に相続人本人の口座に同額が入金されている、といった客観的資料があれば有力な証拠となります。実際の裁判でも、医療記録や介護記録、銀行のATM記録などが証拠提出されることがあります。
また、最高裁平成28年決定以降は預金の扱いが「遺産そのもの」となったため、相続開始後の無断引き出しは遺産分割手続きの中で解決を図る方向になっています。調停や審判で遺産に組み込んで調整することも可能になりました。ただし、それでも話し合いがつかない場合は判例が示すように結局は民事訴訟で決着をつけることになるため、やはり紛争化させないことが一番です。
判例紹介の最後に強調すると、無断引き出しは明確に違法行為であり、裁判例でも不当利得返還や損害賠償が認められる傾向にあります。無断引き出しをした側が「生前にもらった」などと主張しても、それを裏付ける証拠がなければ認められません。逆に、追及する側も感覚だけで疑うのではなく、しっかり証拠を揃えて主張することが求められます。
弁護士に相談するメリット
相続における預金の無断引き出し問題は、法律知識や証拠収集、他の相続人との交渉など専門的な対応が求められます。こうしたトラブルに直面したとき、早い段階で弁護士に相談することには多くのメリットがあります。
交渉・調停・訴訟におけるサポート
弁護士は法律のプロとして、交渉段階からサポートします。相手との直接の話し合いは感情的になりがちですが、弁護士が代理人として間に入ることで冷静かつ的確な交渉が可能です。特に身内の問題では対立が深まると修復が難しくなるため、第三者である弁護士がクッション役となることは大きな利点です。
また、家庭裁判所での調停手続きや審判、地方裁判所での訴訟手続きでは、専門的な書類の作成や主張立証が必要になります。弁護士に依頼すれば、調停申立書や訴状の作成、証拠書類の整備、裁判所や調停委員への説明など、手続き全般の法的サポートを受けることができます。
依頼者本人は精神的負担を軽減でき、自分の主張すべきポイントを見失わずに済むでしょう。裁判になった場合も、弁護士が適切な法的構成(不当利得か損害賠償か等)を考え、判例や法律に照らした主張を展開してくれるため、勝訴や有利な和解の可能性が高まります。
証拠収集・調査のノウハウ
無断引き出しの立証には、銀行の取引履歴やATMの利用記録、資金の流れの解明など高度な証拠収集が必要になる場合があります。弁護士に依頼すると、こうした証拠収集のノウハウを活用できます。
例えば、弁護士は相続人の代理人として銀行に対し、過去10年分の取引明細を取り寄せる対応などをします。さらに日付ごとの出金状況を分析し、ATMからの引き出しなのか窓口なのか、どの支店で行われたかなど詳細を調べます。必要に応じて弁護士会照会(弁護士が裁判所外で行える調査請求手段)を使い、引き出されたお金がその後どの口座に移されたかといった追跡調査も可能です。
これらは一般の相続人にはハードルが高い作業ですが、弁護士なら迅速かつ合法的に進めることができます。また、医療記録や介護施設の記録の取り寄せ、関係者から事情を聞き取る聞き取り調査なども弁護士が代行します。こうして集めた証拠を整理・分析し、裁判になれば説得力のある証拠資料として提出します。証拠固めがしっかりしていれば、相手も途中で非を認めて和解に応じるケースも多く、早期解決につながることも多いです。
さいごに
預金の無断引き出し問題は、誰にとっても気持ちの良いものではありません。しかし、適切な法律知識を持って冷静に対処すれば、解決への道筋は見えてきます。重要なのは早期に手を打つことと、必要に応じて弁護士の力を借りることです。
他の相続人との話し合いや法律手続きに不安がある方は、一度相続問題に詳しい弁護士に相談してみてください。専門家のアドバイスによって自分の権利を守り、円満な相続解決への一歩を踏み出しましょう。無断引き出しという相続トラブルに直面したときこそ、プロの知恵と経験を活用することを強くおすすめします。安心して相続手続きを進めるためにも、ぜひ早めに弁護士への相談をご検討ください。
当事務所では、大分県宇佐市だけでなく、中津市、豊後高田市、杵築市など周辺のエリアから、預金の無断に引出しや相続に関するご相談を多数頂いております。相続で疑問が生じた方は、ひとりで悩まずにご相談頂ければと存じます。