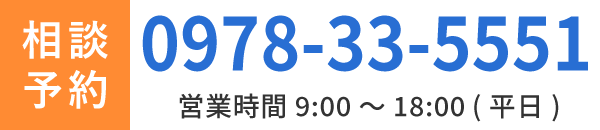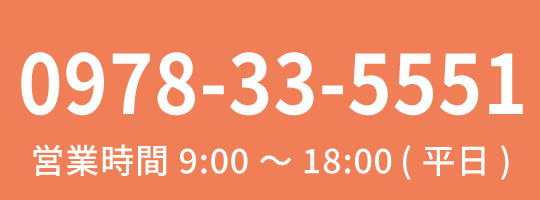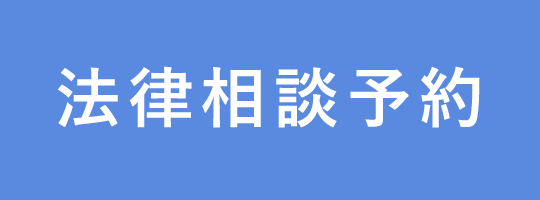ニーズに合わせた事業継承を弁護士がサポートします。
- 子供の代に事業を引き継がせたい
- 従業員に事業を引き継がせたい
- 事業を他社へ売却したい
士業で連携してワンストップで完結
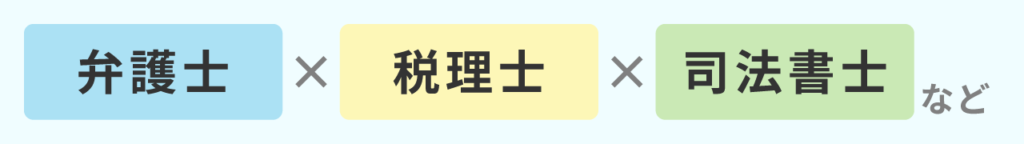
このページの目次
経営者のニーズに合わせた最適な事業承継を、経験豊富な弁護士がワンストップでサポートします。
- お子様の代に事業を引き継ぎたい
- 従業員に会社を託したい
- 事業を第三者(他社)に売却したい
当事務所では、税理士・司法書士など他の専門家(士業)と連携しながら、上記のような経営者様の様々なご要望に対応し、事業承継をトータルに支援いたします。地域の事情に精通した弁護士が窓口となり、親族内承継からM&Aによる第三者承継まで、安心してお任せください。
事業承継とは
事業承継とは、現在の経営者から次の世代の経営者へ事業のバトンを引き継ぐことをいいます。中小企業の社長交代や医院の院長交代など、会社組織だけでなく個人事業でも事業承継は発生します。経営者の高齢化が進む中で事業承継は避けて通れない課題であり、円滑に世代交代を行うことは事業の存続と発展に不可欠です。
中小企業は日本企業の99%を占め、雇用や技術の担い手として社会を支える重要な存在であることから、そのバトンを次世代へつなぐ事業承継は日本社会にとっても大変意義のある取り組みと言えます。
事業承継では、会社の経営権(人の承継)だけでなく、株式・事業用資産など財産の承継、さらには経営理念や取引先との信頼関係といった知的資産の承継も伴います。そのため、単に株式を譲るだけではなく、会社のノウハウや信用も次世代に受け継ぐための準備が必要です。
事業承継を成功させるためには、後継者に経営に必要な資産や権利を集中させることが重要ですが、何の対策もないまま相続が発生すると法定相続分どおりに財産が分散してしまい、円滑な承継が難しくなります。そこで、事業承継においては早めに弁護士などの専門家へ相談し、計画的な対策を講じることが大切です。
事業承継の3つの種類
事業承継の方法は大きく分けて次の3種類に分類できます。それぞれメリット・デメリットがあり、会社の状況によって適切な手段を選ぶ必要があります。
1. 親族(子ども)への承継
社長の地位や株式などをお子様やご親族に引き継がせるケースです。中小企業では最も一般的な事業承継形態で、株式や事業用資産を後継者となる親族に生前贈与したり、経営者が亡くなった際の相続によって承継させたりする方法があります。
親族内承継は会社の事情に精通した身内が後を継ぐため、従業員や取引先からも受け入れられやすい利点があります。先代経営者の理念や会社の文化を後継者が理解しやすく、企業のDNAを維持できるという強みもあります。血縁の後継者であれば周囲も納得しやすく、従業員や取引先にとっても馴染みのある方が継ぐことで安心感が生まれます。
しかし、後継者となる相続人が複数いる場合には注意が必要です。誰が会社を継ぐか決まっていない状態で経営者が亡くなると、会社の株式は法定相続人全員で共有する形になり、遺産分割協議で揉めるおそれがあります。
例えば、社長の子どもが二人いて両方とも事業に関わっているような場合、それぞれが自分こそ後継者にふさわしいと主張し、株式の取り分を巡って深刻な争いに発展する可能性があります。このような経営権争いが起きると、事業自体も停滞して最悪の場合会社が分裂・倒産するリスクもあります。
こうした事態を避けるには、事前の対策が欠かせません。
具体的には、経営者在任中に遺言を作成しておき、後継者に会社の株式や事業用資産を集中相続させることが有効です。遺言書によって後継者に必要な財産を確保すれば、先代経営者が遺言を残すことは事業承継対策の第一歩と言えます。遺言がないまま相続が発生すると、相続人間の話し合いだけが頼りとなり、一人でも反対すれば遺産分割が成立しないため、後継者に経営資源を集約できなくなってしまいます。
もっとも、遺言で後継者に株式を集中させると、他の相続人の遺留分(法律上保障された最低限の取り分)を侵害してしまう可能性があります。
遺留分を侵害する内容の遺言でも法律上は有効ですが、後で他の相続人から遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)を行使され、結局会社の財産を分け渡す事態になれば事業承継に支障が出ます。
そこで、必要に応じて後継者以外の相続人には保険金や現預金などで代償措置を用意したり、相続人全員の合意に基づいて遺留分を放棄・緩和する民法特例(経営承継円滑化法による遺留分に関する特例)を活用したりすることも検討すべきです。
事前に弁護士に相談し、これらの法的手段を組み合わせることで、親族内での円満な事業承継を実現できます。なお、親族内に適切な後継者が見当たらない場合でも、有能な人材を養子縁組によって法定相続人に迎え入れ、実質的に親族承継とする方法もあります。例えば、娘婿や親族外の従業員を養子とすることで、血縁の子どもと同様に事業を継がせるケースも見られます。
2. 親族外(従業員・第三者個人)への承継
親族に適任者がいない場合や、あえて社内の従業員や社外の有能な人材に経営を託すケースもあります。いわゆるMBO(マネジメント・バイアウト)や従業員承継と呼ばれる方法で、現在の会社役員・従業員、あるいは取引先など信頼できる第三者個人に事業を引き継いでもらいます。
この場合、後継者となる人に会社の株式や事業用資産を買い取ってもらう形で承継を行うのが一般的です。買い取りの資金をどう用意するかが課題となりますが、オーナーからの分割払い(役員退職金の充当等)や金融機関からの融資利用、事業承継ファンドの活用など、状況に応じたスキーム(仕組み)を構築する必要があります。
また、従業員承継では新社長となる人の経営手腕や周囲の協力体制も重要です。特にオーナー経営者から従業員への承継では、親族外とはいえ社内の人間関係が影響しますので、現経営者が在任中に十分な引継ぎ期間を設け、経営ノウハウを伝授するとともに従業員や取引先の信頼を引き継ぐ工夫が求められます。従業員承継は社内からの抜擢となるため社員の士気向上につながり、会社全体の一体感を維持しやすいというメリットもあります。ただ、新社長となる人の経営手腕や周囲の協力体制も重要です。
従業員や第三者個人への承継では、株式譲渡契約や事業譲渡契約の締結など法律手続きも必要になります。事前に弁護士や税理士を交えて株式評価や税務対策を行い、適正な価格で承継を行うことが重要です。譲渡対価の支払い方法やスケジュールについても当事者間で明確に合意しておくことで、後継者への負担を調整し円滑な事業引継ぎを実現します。
3. 他社への事業売却(M&A)
後継者となる親族や社内人材がいない場合、会社そのものを第三者に売却する選択肢もあります。近年は中小企業でもM&A(企業の合併・買収)による事業承継が注目されており、自社を買い取ってくれる他社を見つけて事業を託すケースが増えています。
M&Aによる承継方法には、会社の株式を譲渡する方法(株式譲渡)、事業の一部または全部を切り離して譲渡する方法(事業譲渡)、会社同士が合併する方法など様々なパターンがあります。それぞれ法的な手続や税務上の扱いが異なるため、専門家のサポートのもと自社に最適なスキームを検討する必要があります。
第三者への売却では、買い手となる企業・投資家を探すところから始まり、交渉・契約締結・クロージングに至るまで多岐にわたるプロセスが発生します。買収側によるデューデリジェンス(事業調査)に対応し、自社の財務内容や法務リスクを開示・是正するといった準備も欠かせません。不利な条件で買いたたかれないよう、会社の価値評価を適切に行い、契約条件を法的にチェックすることが重要です。弁護士はM&A契約書の作成・レビューや条件交渉のサポートを通じて、経営者様が安心して会社を託せるようお手伝いいたします。
近年、事業承継先のない会社に対してM&Aを打診し、「書面上の話でしかないので」などといって、不利な条件の買収契約を締結させられたといったトラブルも増加しています。このスキームをとる場合は、事前に弁護士にへのご相談をお勧めいたします。
というのも、後になって「やはりなかったことにしたい」といっても、特に打てる手立てがなくなってしまっているケースがあるからです。
事業承継は早めの対策が必要です
対策が遅れると廃業のおそれがあります
事業承継は一朝一夕には成し遂げられません。相続対策や株式譲渡など検討すべき事項が多岐にわたる上、後継者育成にも時間がかかるため、多くのケースで準備開始から完了までに3~5年程度は要すると言われています。もし対策に着手する前に経営者に万一のことが起これば、承継プロセスが途中で止まってしまい、会社が宙に浮いた状態になりかねません。
実際、日本全国で後継者不在のために廃業する企業は後を絶ちません。中小企業庁の試算によれば、2025年までに70歳以上となる中小企業経営者は約245万人に達し、そのうち約半数の127万人が後継者未定とされています。このまま事業承継が進まなければ、今後中小企業の大量廃業が現実となり、雇用約650万人・GDP約22兆円が失われる可能性があるとも指摘されています。
では、具体的に対策が遅れると企業にどのようなリスクが生じるのでしょうか。
一つは、経営空白のリスクです。経営者が高齢だからといって事業承継の準備を先延ばしにしている間に、突然病気や事故で倒れてしまうケースも現実に起こり得ます。
例えば、ある同族会社では創業社長が後継者を決めないまま急逝したため、残された株式が長男・長女ら相続人全員の共有状態となり、会社の経営方針を巡って親族間で争いが起きました。最終的に裁判所の遺産分割審判により、次期社長である長男が会社株式を単独で取得するのが相当と判断されましたが、このように裁判に持ち込まれるまで紛争が拡大すれば、経営の混乱によって会社の信用は大きく損なわれてしまいます。
また、承継対策が遅れると従業員や取引先の流出を招くおそれもあります。
社長の高齢化や後継者不在が周知の事実になると、社員が将来に不安を感じて退職したり、有望な人材の採用に支障が出たりします。取引先にとっても、先行き不透明な会社とは長期的な取引関係を結びにくくなり、重要な契約を打ち切られるリスクも高まります。つまり、経営者が現役で動けるうちにしっかりと事業承継の道筋を示しておかないと、事業価値そのものが時間とともに低下してしまうのです。
このように、事業承継の準備を怠ることは廃業のおそれが生じることがあります。裏を返せば、早め早めに対策を打つことで、会社を存続・発展させるチャンスが生まれます。
実際、事業承継をきっかけに新たな投資や組織改革を行い、業績を向上させた中小企業も多く報告されています。
例えば、ある地方の製造業では、経営者が60代前半から事業承継の準備を開始しました。後継者である長男を役員に迎えて経営を実践的に学ばせる一方、公正証書遺言で長男に自社株の大半を相続させ、他のご家族には生命保険金を活用して代償分割資金を用意する相続対策を実行しました。その結果、70歳という節目でスムーズに世代交代が実現し、交代後も従業員の離職や取引先の離反を招くことなく事業を継続できています。将来の不安を先送りにせず、ぜひお早めに弁護士など専門家へご相談ください。
最適な承継方法を選ぶには綿密な検討が必要です
事業承継の進め方は企業ごとに千差万別です。先述のとおり、承継パターンには親族内承継・従業員承継・第三者への売却など複数の選択肢がありますが、どれが「正解」となるかは会社の状況によって異なります。現経営者や後継者候補の意向、企業の財務内容、将来の展望、関係者の数など、様々な要因を総合的に考慮して最適解を見つける必要があります。
例えば、親族内承継を選ぶにしても、後継者となる子息に会社経営の力量が備わっているか、他の相続人とのバランスをどう取るかといった課題があります。従業員承継であれば、自社株の評価額や資金調達方法によって現経営者のリタイア後の生活設計にも影響するため、無理のないスキーム設計が求められます。第三者への売却では、売却条件に加えて売却後に社名や雇用を維持するかなど、会社の「譲れない点」を事前に整理しておくことが重要です。
さらに、事業承継に伴って発生する各種税金(相続税・贈与税・譲渡所得税など)にも注意が必要です。自社株評価額が高額になる場合、相続税負担が後継者の重荷となり事業継続を困難にするケースもあります。
そのため、納税猶予などが受けられる事業承継税制の適用を検討したり、生前贈与のタイミングを工夫したりと、税務面での対策も含めた綿密なプランニングが求められます。
当事務所では、近隣の税理士とも連携体制を確保し、複数士業でのワンストップ解決を目指しています。
また、国や自治体も中小企業の事業承継を支援する制度を設けています。例えば、中小企業庁の事業承継・引継ぎ補助金では、M&Aに係る専門家費用や承継後の設備投資費用等に対して最大600万円の補助金が交付されます。こうした公的支援策もうまく活用しながら、費用面の不安を軽減して計画的に事業承継を進めることが大切です。
事業承継のサポート内容と当事務所の強み
当事務所が提供する事業承継支援サービス
当事務所では、中小企業の事業承継に関する法律実務をサポートしています。具体的には、以下のようなサービスを提供しております。
- 事業承継プランの立案支援(承継計画書の作成や関係者との調整を含みます):現状の課題やご要望を伺い、適切な承継方法(親族内承継・MBO・M&Aなど)の選定からスケジュール策定まで、弁護士がプランニングをお手伝いします。
- 遺言書・各種契約書の作成(遺言書は公正証書での作成を推奨):後継者に株式を相続させるための遺言書作成、公正証書遺言の立会い手配、株式譲渡契約書・事業譲渡契約書・会社分割契約書といった必要書類の作成・チェックを行います。
- 相続・税務対策(税理士等と連携して対応):税理士等と協力し、株価対策、生前贈与、事業承継税制(納税猶予制度)の活用検討、遺留分対策など、承継に伴う相続税・贈与税の問題についてアドバイスします。
- M&A法務支援(秘密保持契約や基本合意書の締結支援を含む):第三者への事業売却を検討する場合、秘密保持契約の締結、意向表明書(LOI)の作成支援、デューデリジェンス対応、最終契約交渉・クロージングまで一貫してサポートします。
- 紛争予防・調整(承継前後のトラブル防止策の提案):親族内承継における親族間の調整や、従業員承継での株主間契約の策定、承継後のトラブル(例:遺留分請求や債務保証の問題)についての予防策・解決策を講じます。
上記のように、法律専門家として事業承継のあらゆる局面で経営者の皆様を支援いたします。「何から手を付ければいいかわからない」という段階でも構いませんので、まずは現状のお悩みをお聞かせください。
ビジネス経験のある弁護士が対応します
事業承継のご相談は、ビジネスの現場を経験した弁護士が直接対応いたします。当事務所の弁護士(貞永憲佑)は、かつてゲーム会社で事業部責任者として事業部門に携わった経歴を持ち、自ら新規事業の立ち上げや組織マネジメントを行ってきました。また、東証一部上場企業グループで法務部長・社内弁護士を務めた経験もあり、企業法務と事業運営の双方に精通しております。
このように経営者目線を理解できる弁護士が対応することで、単なる法律手続の支援にとどまらず、「会社の実情に即した本当に役立つ提案」を心がけています。法律上可能な選択肢を示すだけでなく、「どの方法が御社の経営にとって最適か」「承継を機に事業をさらに発展させるにはどうすればよいか」を共に考えながら、実行支援まで一貫して伴走いたします。必要に応じて弁護士自ら企業様に出向き、社内の会議や関係者との調整に加わるなど、経営者の「右腕」として実務面まで踏み込んだリーガルサービスの提供を目指しています。
なお事業承継はデリケートな問題ですので、相談者である経営者様のお気持ちに寄り添い、秘密厳守はもちろん、プライバシーにも最大限配慮して進めてまいります。初めての方でも安心して相談できる雰囲気づくりを心がけておりますので、些細な不安でもどうぞご遠慮なくお話しください。
重点対応地域
当事務所は大分県北部の法律事務所として、主に大分県内およびその周辺地域の中小企業の事業承継案件を数多く手がけております。とりわけ、大分県北部(宇佐市・中津市・豊後高田市など)から大分市・別府市、その近隣の日田市・杵築市・速見郡日出町といったエリアまで、幅広い地域の経営者様からご相談をいただいております。福岡県京築地域(豊前市・行橋市など)をはじめ、北部九州エリアからのご相談にも対応しております。
よくある質問(FAQ)
事業承継の準備は何歳から始めるべき?
Q: 事業承継の準備は何歳頃から始めるのが良いでしょうか?
A: 一般的には、経営者が60歳前後になったら本格的に事業承継の準備を始めることが望ましいと言われています。平均的な中小企業経営者の引退年齢は70歳前後とされるため、少なくともその5~10年前には後継者選びや承継計画の策定に着手するのが理想です。
早めに動き出すことで、後継者育成に十分な時間を確保できるほか、相続税対策や関係者との調整も余裕をもって行えます。反対に着手が遅れると、突然の体調悪化に対応しきれずトラブルが生じるリスクが高まりますので、「まだ元気だから」と先延ばしにせず、60代に入る前にはぜひ一度ご相談いただくことをお勧めします。
事業承継は弁護士に相談する必要がありますか?
Q: 事業承継の相談先として、税理士や会計士ではなく弁護士に依頼する必要はあるのでしょうか?
A: 事業承継には相続、契約、会社法など法的な課題が不可避であり、弁護士に相談することでこれらの問題を的確に解決できます。例えば、遺言書の作成や株式譲渡契約の締結、遺留分への対処といった手続には高度な法律知識が必要です。
また、承継過程で利害が対立する場面が生じた際には、紛争をよく知る弁護士の役割が重要となります。当事務所では、税理士や司法書士とも連携体制を広げていっており、総合的な戦略立案から紛争対応まで一貫してサポートすることを心がけております。
後継者が決まっていない場合はどうすればいいですか?
Q: 親族や従業員に後継者がいない場合、事業承継は諦めるしかないのでしょうか?
A: いいえ、後継者が社内外に見当たらない場合でも、事業承継を諦める必要はありません。近年は第三者への事業引継ぎ(M&A)が盛んで、他社に事業を譲渡したり、新たな起業家に会社を買い取ってもらったりする選択肢があります。
また、各都道府県には事業引継ぎ支援センター(大分県にも設置)という公的機関があり、後継者候補とのマッチング支援など専門的なサポートを行っています。外部に譲渡することで会社名や従業員の雇用を残せるケースも多く、一時的に廃業するよりも価値ある「第二のスタート」を切ることができます。当事務所でも、適切な譲渡先の選定や交渉を法務面からサポートいたしますので、後継者不在でお悩みの場合もまずはご相談ください。
事業承継には遺言書が必要ですか?
Q: 事業承継を考えるにあたり、遺言書は作成しておいた方が良いのでしょうか?
A: 円滑な事業承継のためには遺言書を作成しておくことが強く推奨されます。遺言によって後継者に株式など必要な財産を集中相続させることで、相続人間の争いを予防できます。
遺言がない場合、法定相続分に従って財産が分散し、後継者が十分な持分を得られない可能性があります。自筆の遺言も有効ですが、形式不備や紛失のリスクがあるため、公証人役場で作成する公正証書遺言が確実です。当事務所では事業承継に適した遺言書の作成もサポートしております。