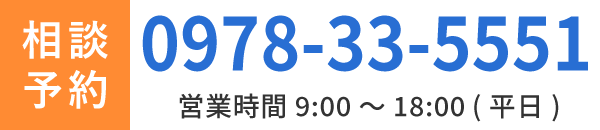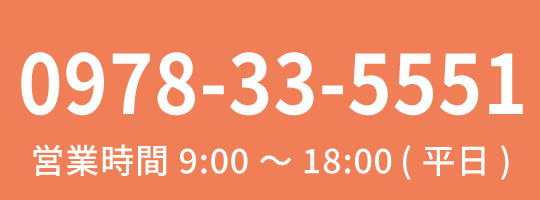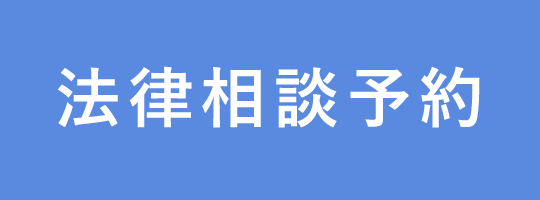このページの目次
突然弁護士から内容証明郵便が届いたら
不倫・浮気(不貞行為)の慰謝料請求は、ある日突然、弁護士からの内容証明郵便が届くことから始まることが多いです。ほとんどのケースで、配偶者との不貞行為があった事実と共に、200万円から330万円の慰謝料請求がされることが多いかと思います。
しかし、不倫・浮気が事実だったとして、必ずしも高額の慰謝料を払わなければならないということではありません。「そんな金額はとても払えない…」と思ったとしても、相手方の弁護士に連絡を取って交渉する前に、こちら側もプロである弁護士に相談することをおすすめ致します。
不倫・不貞行為の慰謝料請求とは?
慰謝料請求とは、不法行為による精神的苦痛に対する損害賠償請求です。不倫・不貞行為は法律上「不法行為」(民法709条)に該当し、配偶者の権利(平穏な婚姻生活を維持する権利)を侵害する行為として、加害者に慰謝料支払義務が生じ得ます。典型的には、配偶者の不倫相手(第三者)に対し、不貞行為をされた配偶者が慰謝料を請求するケースが想定されます。また、不倫した配偶者本人に対しても慰謝料請求(離婚時の財産分与や離婚慰謝料として請求する形など)が行われることがあります。
弁護士に依頼された場合、慰謝料請求は通常、内容証明郵便による請求書の送付から始まります。例えば、弁護士から「○年○月頃から○月頃まで不貞行為があった。慰謝料として○○万円を◯日以内に支払え」といった内容の書面が届くことが多いです。このように請求の意思を正式に伝えることで、話し合い(示談交渉)や法的手続きへの第一歩となります。
ただし、不倫の慰謝料請求が認められるには満たすべき条件や限界もあります。肉体関係の有無は重要で、基本的に配偶者以外との肉体関係があった場合に慰謝料請求が認められます。肉体関係がなければ原則として不法行為は成立せず慰謝料を支払う必要はありません。また、婚姻関係の破綻状況も重要です。例えば、不倫が始まる前にすでに夫婦仲が完全に破綻していた場合には、第三者である不倫相手に対する慰謝料請求は認められないとの最高裁判例があります。これは、婚姻関係が実質的に破綻していた場合には不倫相手の行為が婚姻破綻の原因といえず、不法行為責任を負わないと判断されたものです。
さらに、請求期限(時効)にも注意が必要です。不貞行為に基づく慰謝料請求権の消滅時効は、「被害者(不倫された側)が不貞の事実および不倫相手を知った時から3年」です(民法724条)。発覚から3年以上経過すると、加害者に「時効だから支払わない」と主張されてしまう可能性があります(※不貞行為の時から20年が経過した場合も請求権は消滅します)。したがって、浮気が発覚したら早めに行動することが大切です。
以上のように、不倫の慰謝料請求は「法律上認められる条件」を満たした場合に可能となります。以下では、不倫された側(被害者)が具体的に慰謝料を請求する際の手順や注意点を説明します。反対に、不倫をして請求されてしまった側の対応策についても後ほど解説します。
不倫をしてしまった側の対応
「ある日突然、見知らぬ弁護士から内容証明郵便が届いた」というケースは、不倫してしまった側にとって大きな動揺があると思います。
しかし、不倫・浮気が事実であっても、請求された金額をそのまま支払わなければならないとは限りません。相手方が提示してくる金額は、あくまで先方の希望額・要求額にすぎず、法的に適正かどうかはこれからの交渉や裁判で決まります。相手の言いなりに支払う前に、まずはこちらも専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談・依頼すべき理由
自分に非がある状況では「後ろめたいし、弁護士なんて頼んだら悪いのでは?」と尻込みするかもしれません。確かに不倫は社会的に許されない行為です。しかし、それとこれとは話が別です。適正な範囲を超える過剰な請求まで無条件に受け入れる義務はありません。法的には、自らの過ちに対する賠償はあくまで適正な金額に限定されるべきだからです。
弁護士に依頼すれば、代理人として相手方と直接交渉してもらえます。これは大きなメリットです。自分で相手(または相手の代理人弁護士)とやり取りする必要がなくなり、精神的負担が大幅に軽減されます。不倫発覚後、被害者側との連絡におびえながら日々を過ごすのは大変な重圧ですが、その窓口を弁護士に任せることで日常生活を取り戻すことができます。
さらに、弁護士は法的根拠に基づいて減額交渉を行えます。不倫した事実は変えられませんが、例えば「請求額が相場を超えて高すぎる」「法律上、支払い義務のないケースに該当する可能性がある」など主張すべき点があります。不倫問題に詳しい弁護士であれば過去の判例や裁判例を踏まえて交渉に臨み、感情的な争いを避けつつ冷静に議論することができます。当事者同士では怒りや恨みで話し合いにならないような場合でも、代理人同士であれば建設的に進められることが多いです。
また、法的に見ると慰謝料請求交渉は「示談による権利義務の処分」にあたり、代理交渉できるのは弁護士だけです(弁護士法72条)。友人や親族に間に入ってもらうことはできますが、正式な代理人として交渉できるのは弁護士のみとなります。適正な解決のためには、専門家に任せるのが得策といえるでしょう。
慰謝料の相場と高額請求への対応
相手から提示された金額が法外に思える場合でも、まず冷静に一般的な慰謝料の相場と比較してみましょう。前述のとおり、不倫慰謝料の相場はケースによりますが概ね50万~300万円程度とされます。特に夫婦が離婚に至らなかったケースでは50~100万円台、離婚に至ったケースでは100~200万円台といった例が多くなっているようです(とはいえ、事実関係によって結論は異なります)。
慰謝料額が決まる主な要素は次のとおりです。
- 不貞行為の期間・回数・頻度: 長期にわたる継続的な関係や回数の多さは増額要因になります。反対に、一度きり・短期間の場合は減額要因となりえます。
- 婚姻期間の長さ: 相手方夫婦の結婚生活が長いほど、それを壊した影響は大きいと判断され増額につながります。逆に結婚後すぐの不倫で婚姻期間が極めて短い場合は減額の可能性があります。
- 未成熟子の有無・年齢: 未成年の子供がいる家庭を崩壊させた場合、「子への影響も含めた精神的苦痛」が考慮され増額することがあります。子供がいない場合や成人して独立している場合はその分減額要素となり得ます。
- 不倫発覚後の結果: 不倫が原因で別居や離婚に至ったか否かは大きなポイントです。離婚まで至れば相手の受けた精神的苦痛は一層大きいと判断され額が上がる傾向があります(※ただし後述の判例のように法律上の制限もあります)。別居に留まり婚姻関係を継続している場合は、離婚時よりは低い額が認められるでしょう。
- 不倫発覚後の態度: あなた(不倫した側)が発覚後に取った行動もいくらかは考慮されます。真摯に謝罪し反省している場合と、開き直ったり相手を侮辱するような言動をとった場合とでは、最終的な慰謝料額に差が出ても不思議ではありません。裁判例でも、不倫発覚後に誠実な対応をしたか否かが説示されることがあります。
- その他個別事情: 不倫に至った経緯で、例えば相手(配偶者)の方にも落ち度があるような場合は考慮されることもあります(夫婦関係が冷え切っていた等)。また、いわゆるW不倫(双方既婚者の不倫)だった場合、お互いの配偶者がそれぞれ相手方に慰謝料請求できる関係になります。双方同程度の請求が想定される場合、結局夫婦間でお金が行き来するだけになりプラマイゼロになるため、お互い請求を控える可能性もあります。
これらの要素を踏まえれば、相手方から提示された金額が適切かどうかある程度判断できます。明らかに相場より高い要求であれば、「法的にはその額は認められないのではないか」と交渉で主張すべき場面です。実際、弁護士が交渉に入ることで「仮に裁判になってもこの金額は高すぎて認められないでしょう」といった見通しを示し、大幅な減額に成功するケースも多々あります。当事務所の実績でも、請求500万円を70万円に減額して和解した例や、請求300万円を50万円に減額した例があります。いずれも弁護士が事実関係を精査し、裁判例に基づいて適正額を主張した結果、大幅な減額に至っています。
慰謝料を支払わなくて済む可能性があるケース
不倫をしてしまった側でも、状況によっては慰謝料の支払い責任が生じない、または減額される場合があります。以下のようなケースが考えられます。
- 婚姻関係が不倫前から破綻していた場合: 前述のとおり、夫婦仲が完全に壊れていた後の不倫については、法律上慰謝料請求自体が認められません。実際に最高裁平成8年3月26日判決でも「夫婦関係がその当時既に破綻していたとき」は不倫相手の不法行為責任は負わないと明言されています。ただし、「破綻していたかどうか」は裁判でも厳格に判断されますので、相手が単に「もう夫婦関係は終わっていた」と主張しているだけでは不十分です。客観的に見て同居実態がなかった、離婚協議中だった等の証拠が必要でしょう。
- 肉体関係がなかった場合: 肉体関係を伴わない関係であれば、原則として慰謝料支払い義務は発生しません。デートや食事を重ねていた程度ならば「不貞行為」に該当しない可能性があります。ただし、度重なる深夜の外出やキス以上の親密行為などがあれば「婚姻の平和を乱した」とみなされるリスクはあります。いずれにせよ、一線を越えていないのであれば反論できる余地があります。
- 不倫相手が既婚者だと知らなかった場合: 交際当初からお相手(不倫していたお相手の配偶者)が結婚していると全く知らされておらず、普通に接していても気付かなかったような場合です。法律上、不法行為が成立するには加害者に少なくとも過失(過失=注意すれば違法だと分かったはずの状態)が必要です。相手に配偶者がいることを本当に知らず、かつ知らなくても無理はない状況であれば、「故意・過失がなかった」として責任を否定できる可能性があります。ただ現実には、「独身だと聞いていた」「妻とは別居中で破綻していると聞かされていた」といっただけでは裁判で通りにくいのも事実です。この点について詳しくは、こちらのページをご覧下さい。
- 慰謝料請求の時効が完成している場合: 不倫が発覚してから既に3年以上経過している場合や、不貞行為から20年が経過している場合は、法的には時効消滅を主張できます。たとえば5年前の不倫について今更請求されたようなケースでは、「時効による消滅」を盾に支払いを拒否することが可能です。ただし、一度支払うと約束してしまったり(一部でも払うと時効が更新する可能性があります)、内容証明が届いて放置しているとその後6か月間延長されるなど時効には法律的な細かい規定があります。時効が絡む場合は弁護士に判断を仰ぐとよいでしょう。
- 証拠がない場合: 極端な話ですが、相手が不貞の証拠を全く持っておらず「浮気しているに違いない」という疑念だけで請求してきている場合です。証拠がなければ裁判で慰謝料を勝ち取ることは困難です。あなたとしては事実無根であれば断固否定すべきですし、事実であっても証拠が出てこない限りは相手は法的措置を取れないかもしれません。ただし、探偵の調査報告など裏付けを掴まれている可能性もあるため、軽率に動かないよう注意しましょう。
離婚した場合の慰謝料と最近の判例動向
不倫の結果、相手方夫婦が離婚に至った場合、慰謝料額が上がりやすい傾向があります。裁判所も「離婚という重大な結果を招いた」という事情を考慮に入れるためです。そのため離婚ケースでは200~300万円前後の高額になることもありえます。しかし、この点に関して近年重要な判例が出されています。
最高裁平成31年2月19日判決では、配偶者の不倫が原因で離婚に至った場合であっても、不倫相手に「離婚そのもの」に対する慰謝料(離婚による精神的苦痛)を請求できるとは限らないことが示されました。判決の要旨によれば、不倫相手に離婚慰謝料まで求められるのは「不倫相手が当該夫婦を離婚させることを意図して婚姻関係に不当干渉するなど、離婚に至らしめたと評価すべき特段の事情」がある場合に限られるとされています。簡単に言えば、不倫相手がただ配偶者と関係を持っただけでなく「積極的に離婚させようと画策した」ような特殊なケースでないと、離婚そのものの慰謝料までは認められないということです。
この判例を踏まえると、今後は不倫による慰謝料の考え方がやや整理されると考えられます。すなわち、不倫相手が賠償すべきなのは基本的に不倫による精神的苦痛であり、離婚したこと自体の責任は原則として不倫した配偶者本人(夫婦間)で解決すべき、という方向です。
ただ実務上は、不倫で離婚になった場合は結果として慰謝料額が高額になるケースが引き続き多いでしょう。裁判でも「離婚という結果になった以上、精神的苦痛が大きい」として上限に近い額(〜300万円程度)が認定される可能性があります。
なお、不倫相手であるあなたと、当事者である配偶者(あなたと関係を持った人)は共同不法行為者とされます。被害者であるその配偶者の夫/妻(請求者)に対しては、法律上どちらも連帯して責任を負う立場です。一方で、仮にあなたが被害者に慰謝料を支払った場合、あなたは求償権という権利を取得します。求償権とは、共同不法行為者の一方が被害者に賠償したとき、他方に対して自分が負担すべき以上の額を後から請求できる権利のことです。不倫の場合、あなたが支払った後で配偶者本人に「あなたも責任半分あるのだから○割負担して下さい」と請求する権利が発生し得るということです。
ただし現実には、示談の場で「求償権を行使しない(求償権の放棄)」ことを条件に支払額を減額してもらう交渉が行われることがあります。例えば「本来あなたの夫(妻)にも責任がありますが、私からはそちらへ求償しません。その代わり慰謝料は◯◯万円に減額してください」という具合です。被害者側からすれば、自分の配偶者が後から請求されるリスクを避けつつ早期解決できるメリットがあり、加害者側からすれば支払う金額を減らせる可能性があります。ただこのあたりの駆け引きは法律知識が必要ですので、弁護士に任せるのが安心でしょう。
裁判になった場合の対応
交渉が折り合わない場合、被害者側は訴訟(裁判)という法的手段に踏み切ることがあります。内容証明を送っても支払いに応じなかったり、交渉が決裂したりすると「〇月〇日までに支払いがなければ法的措置をとります」と宣言され、そのまま地方裁判所に提訴されるケースです。
もし訴訟を起こされた場合でも、適切に対処すれば必要以上に恐れることはありません。 裁判では証拠に基づき公平に判断が下されますし、こちらにも言い分や反論の機会が与えられます。訴状が届いたら放置せず、速やかに弁護士に相談してください。依頼する場合は、弁護士が代理人として答弁書を提出し、以後の裁判手続きを進めます。
訴訟になった場合、先述の求償権に関連して「訴訟告知」という手続きをとることも検討されます。訴訟告知とは、裁判の当事者ではない第三者に対し「今こういう裁判をやっているので、関心があれば関与してください」と通知する制度です。不倫の慰謝料請求訴訟では、被告(不倫相手)からその共犯者である配偶者に対して訴訟告知を行うことがあります。
こうすることで、後日あなたが配偶者に求償権を行使する際に有利になることがあります。具体的には、裁判で認定された事実関係(不貞行為があったことや慰謝料額など)について、訴訟告知を受けた配偶者にもその効力(参加的効力)が及ぶため、後の求償請求で争いにくくなるのです。簡単に言えば、「あなたにも関係ある裁判だから知らせておきますよ」と配偶者に伝えることで、その配偶者は裁判結果から逃げられなくなるということです。
もっとも、多くの慰謝料請求事件は裁判に至る前に示談で解決しています。裁判になればお互いに時間も費用もかかるため、どこかで妥協点を見つける方が双方にメリットが大きいからです。実際に当事務所で扱ったケースでも、訴訟まで想定して準備はしましたが「裁判にしてもお互い得るものがない」と説得し、受任から1ヶ月ほどで早期和解に至った事例があります。適正な範囲で折り合えるなら、早期解決を図ることが望ましいでしょう。
判例などに基づいて主張し落としどころを提示することで、早期解決を実現することができました。