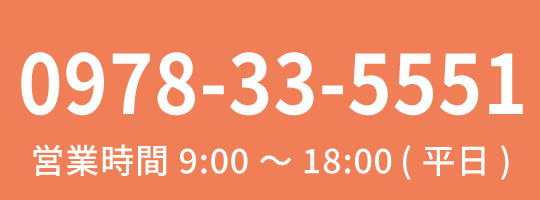このページの目次
遺留分とは何か
遺留分とは、遺言などによっても奪うことができない、最低限の相続分のことをいいます。
たとえば、遺言によって「すべての遺産を長男に相続させる」という内容が定められていても、他のきょうだいの相続分は直ちにゼロということにはなりません。
遺留分が侵害されている場合は、以下に述べる遺留分侵害額請求をすることによって、遺産の一部を金銭で請求することができます。
遺留分を持っているのは誰か
遺留分を有するのは、民法1042条1項に「兄弟姉妹以外の法定相続人」であると定められています。
つまり、以下の人が遺留分を持っています。
- 配偶者(妻や夫)
- 子ども
- 子どもが先に死亡している場合、その子ども(代襲相続人)
- 子どもが以内場合の、親など直系尊属
遺留分の割合はどのくらいか
民法1042条1項には、遺留分の割合について以下のように定められています。
- 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
- それ以外の場合 2分の1
つまり、相続人が被相続人の配偶者と子どもである場合や、子どものみである場合は、遺留分は相続分の2分の1ということになります。
例えば、被相続人がその妻と子3人で、長男に全財産を相続させるという遺言があった場合、遺留分はそれぞれ以下のとおりとなります。
妻:1/2×1/2=1/4(本来の相続分は1/2)
子:1/2×1/3×1/2=1/12(本来の相続分は1/6)
遺留分侵害額請求権とは
遺留分侵害額請求権というのは、令和元年7月1日に民法が改正されて生まれた権利です。
それまでは、遺留分減殺請求権と言う権利が定められていましたが、遺贈又は贈与が遺留分を侵害する限度において失効すると定められており、金銭だけの請求ができる場合だけではありませんでした。その結果、株式や不動産が共有となる可能性が残ってしまっていました。
しかし、この制度は事業承継の際などに使い勝手が悪いとされていたことなどから、法改正により遺留分侵害額請求権が定められ、権利行使の際に金銭の支払いのみで解決を図ることができるようになりました。
具体的には、以下に定める手続によって、金銭の支払いを、遺言によって遺贈などを受けた人に対して請求できるということになります。
遺留分侵害額請求をするには
1 内容証明郵便によって請求の意思表示をする
遺留分には、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内という短い消滅時効が定められています(民法1048条)。
そこで、遺留分の請求は、遺言などが見つかって自分の遺留分が侵害されていることが分かったらすぐにしなければなりません。
このとき、遺留分侵害額請求をするという通知が相手に届いていればよく、遺産の総額がいくらで、そのうちいくらが遺留分であるなどと具体的に判明していなくても、まずは遺留分侵害額請求をするという意思表示をすれば、この1年の消滅時効にはかかりません。
もっとも、そのような請求をしてから5年以内に具体的な金銭債権として請求せずにいると、今度はその請求債権が消滅時効にかかってしまうため、注意が必要です(民法166条1項1号)。
郵便を送る方法は、内容証明郵便で送ることをお勧めします(弁護士が行う場合はこの方法をとります)。
というのも、相手に郵便が届いていないなどと後になって言われても、内容証明郵便であれば自分のところにも同じ郵便が届き、郵便局にもその文書が残ります。さらに、そこに配達証明をつけておけば、遺留分侵害額請求の意思表示が到達したことを証明することができます。
このようなことから、遺留分減殺請求の意思表示は、内容証明郵便で送る必要があります。
そして、この意思表示を端緒として、遺産の総額を明らかにし、遺留分相当額を支払う交渉が成立することもあり得ます。
2 遺留分侵害額の請求調停
遺留分減殺請求事件は、法律上、調停を専攻させるべきであるとされています(調停前置主義)。
もっとも、話し合いの余地がまったくなく、調停が成立する見込みがないことが明らかな場合は、調停を経ずに訴訟を提起してもよい場合も存在します。
例えば、事前に一切の支払をしないことを文書で伝えられていて、客観的に調停が調わないことが明らかである場合などは、相手方が遺産をすべて使ってしまったりしないように、すぐに訴訟を提起すべき場合などもありえます。
また調停は話し合いの手続ですので、金銭のみで請求できるという法律の定めがあっても、土地や株式という現物の交付を受けることで解決するという方法も、場合によっては模索することができます。
3 遺留分侵害額請求訴訟
調停が調わない場合や、調停が成立する見込みがないことが明らかな場合は、遺留分侵害額請求訴訟を提起します。
この場合、遺留分侵害の事実を証拠により立証することになります。
遺留分侵害の事実は、例えば遺産の総額を立証するために、金融機関の残高証明書や、固定資産税評価証明書などを提出する必要があります。
訴訟手続については弁護士に依頼していれば、ご本人が出席する必要は原則としてなく、弁護士に任せることができることもメリットです。
最後に~遺留分の侵害があることに気づいた方へ~
遺留分は始めに述べたとおり、相続人に認められた法律上の権利です。
たとえば、幼少期に親が離婚してまったく接点がなかったとか、親とのソリが合わなかったという事情があった場合でも、一律に認められます。
法律上の権利である以上、「幼少期から接点がないから、請求してはいけないのではないか」と躊躇される方もいますが、必ずしもそのように考えるべきではないことは多くあります。
相続事件は法律上の議論だけでなく、さまざまな思いも巡る問題です。
当事務所では、なるべく頼っていただく方の意思や価値観に寄り添った弁護活動をできればと考えております。
もちろん、弁護士として取るべき方策をお進めすることや、必ずしもご依頼者の方にとって得にならないと考えることは、そのように意見を述べることもありますが、まずはご相談者・ご依頼者の皆様との対話を通して、よりより解決を実現できるよう、尽力してまいる所存です。