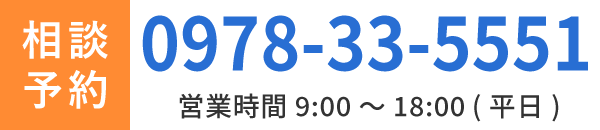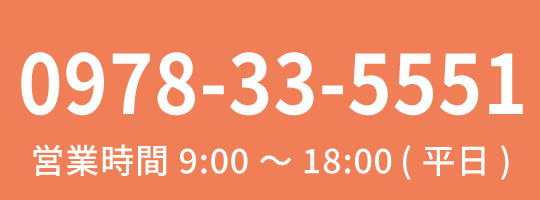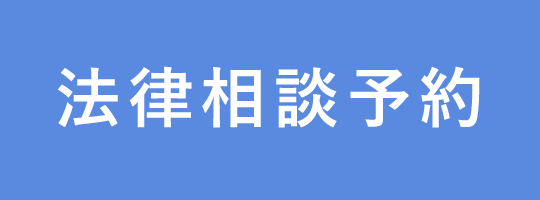このページでは、入通院の慰謝料について説明しています。
慰謝料は、弁護士が交渉するか否かで、金額が大きく変わることの多い項目の一つです。
このページで入通院慰謝料についての知見を深め、交通事故の賠償金が適切かどうかを確認していただければと存じます。
このページの目次
入通院慰謝料の定義と対象
交通事故による入通院慰謝料(傷害慰謝料)とは、事故で負ったケガの治療のために入院・通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛への補償金です。
簡単に言えば「ケガに対して支払われるお金」であり、入院・通院中の痛みや苦しみに対する慰謝料になります。入院または通院を前提とする慰謝料なので、事故後まったく医療機関にかからなかった場合には基本的に請求できません。
対象となるのは、交通事故でケガを負い実際に病院等へ入院・通院した期間であり、入院のみ・通院のみの場合も含まれます。リハビリのための通院も治療の一環として慰謝料算定の対象に含まれます。なお、医師が「症状固定」と判断するまでの治療期間が対象で、症状固定後のリハビリは通常含まれません。
また、交通事故の慰謝料には入通院慰謝料のほかに後遺障害慰謝料・死亡慰謝料があり、症状固定前の治療期間に対応するのが入通院慰謝料、症状固定後に残った後遺障害に対するのが後遺障害慰謝料と明確に区別されています。
入院期間中の慰謝料は通院よりも高めに算定されるのが通常で、裁判基準(弁護士基準)では入院期間の慰謝料額は通院のみの場合の約2倍程度になることが多いとされています。
計算方法(基準ごとの違い)
交通事故の入通院慰謝料を算出する際には、大きく分けて「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準(弁護士基準)」という3つの基準があります。
同じケガでもどの基準を用いるかで金額に大きな差が生じ、一般に自賠責保険基準が最も低額、裁判基準が最も高額、任意保険基準はその中間(自賠責よりやや高い程度)とされています。
以下、それぞれの基準の算定方法と特徴を整理します。
自賠責基準(強制保険の基準)
被害者救済のため最低限の補償額を定めた基準です。入通院慰謝料については1日あたり4,300円と定められており、事故から治療終了までの治療期間(日数)と実通院日数(入院日数+実際通院日数×2)を比較し、いずれか少ない方の日数に日額を掛けて算出します。
例えば治療期間90日で実通院日数50日の場合、「実通院日数×2=100日」となり治療期間90日の方が短いため、90日分として計算されます。
この基準では被害者1人につき120万円までという傷害損害全体の支払上限があり、治療費や休業損害等と合計して120万円を超える部分は任意保険から支払われることになります。
自賠責基準はあくまで最低補償額であり、後述の他基準による算定額より大幅に低い点に注意が必要です。
任意保険基準(保険会社の社内基準)
加害者側の任意保険会社が独自に定めている慰謝料算定基準です。詳細な基準額は各社非公開ですが、概ね自賠責基準から多少上乗せした程度の金額が用いられているとされています。
保険会社としては支払額を抑えたい意向があるため、被害者が弁護士に依頼せず交渉する場合、提示される慰謝料は自賠責基準~任意保険基準レベルの低めの金額に留まる傾向があります。
明確な算定式は公表されませんが、後述の裁判基準より低額になるよう調整されています。
裁判基準(弁護士基準)
裁判所が認める慰謝料水準に基づく算定基準で、過去の判例をもとに日弁連交通事故相談センターが公表する「赤い本」「青本」等の算定表が指針として利用されています。
弁護士に依頼して示談交渉する際は通常この基準が用いられ、入通院期間(月単位の期間と入通院の態様)に応じて定型化された慰謝料額を算出します。
具体的には、ケガの程度により「むち打ちなどの他覚所見なし用」と「それ以外の重傷用」の2つの別表があり、入院○ヶ月・通院○ヶ月の組み合わせごとに相場額が定められています。
裁判基準による慰謝料額は任意保険基準より大幅に高く法的妥当性も高いため、被害者が本来得るべき適正額とされています。
基準を比較すると、裁判基準で算定した慰謝料は自賠責や任意保険基準より高額になり、自賠責基準の約1.5~1.8倍に達するケースもあるとされています。
実際、通常のケガで3ヶ月通院した場合、裁判基準では約73万円(軽傷なら約53万円)の慰謝料が認められるのに対し、自賠責基準では約34万円程度にとどまるという比較例があります。
日数ごとの相場
入通院慰謝料の金額は、治療期間の長さや入通院の態様(入院の有無・日数、通院日数)によって変動します。
以下に通院期間・入院日数ごとのおおよその相場例を示します(後遺障害が残らなかった場合)。なお自賠責基準はケガの程度によらず日数計算により一律のため、軽傷・重傷の別は裁判基準の場合の目安です。
ただし、これは裁判を実際にした場合の金額を記載しており、裁判外の交渉では一定の減額をして示談することがほとんであることにも、注意が必要です。
- 通院のみ1ヶ月(約30日間): 自賠責基準では約8万6,000円(4,300円×20日)。裁判基準ではむち打ちなどの他覚所見がない場合で約19万円、他覚所見のあるケガで約28万円が最大となります。
- 通院のみ3ヶ月(約90日間): 自賠責基準では約25万8,000円。裁判基準ではむち打ちなどの他覚所見がない場合で約53万円、通常のケガなら約73万円が最大です。
- 通院のみ6ヶ月(約180日間): 自賠責基準では最大で約77万4,000円(治療期間180日・実通院日数90日以上の場合)。裁判基準ではむち打ちなどの他覚所見がない場合で約89万円、骨折等の重傷例なら約116万円が最大となります。
裁判基準では入院を伴う場合、慰謝料が上記より高額になります。
例えば「1ヶ月入院+5ヶ月通院」のように入院期間を含むケースでは、同じ通院期間のみの場合より増額され、入院期間部分の慰謝料は通院の約2倍程度に算定されます。
実際の算定では、入院○ヶ月・通院○ヶ月の組み合わせごとに定められた金額をもとに調整されます。例えば重傷で半年間入院と通院を合わせて治療した場合、裁判基準の慰謝料は200万円を超える水準となることもあります(個別事情で増減あり)。
軽傷むち打ち等の場合は異なる基準が適用され相場が低めになりますが、それでも任意保険基準よりは高額になるケースが多いです。
示談交渉時の注意点
適正な慰謝料を受け取るため、保険会社との示談交渉では次の点に注意が必要です。
提示額の基準を確認する
保険会社から提示された慰謝料がどの基準で算定されたものかをチェックしましょう。保険会社の提示書面に「自賠責保険基準」や「任意保険基準」「弊社基準」などの記載があれば、低い基準で計算されている可能性が高いです。
その場合、そのまま受け入れると本来もらえる適正額より低い金額で示談してしまうおそれがあります。提示額に疑問があれば、遠慮なく計算根拠を尋ねたり、弁護士に相談して裁判基準で再計算してもらうことが望ましいです。
保険会社の早期打ち切り要請に注意
加害者側保険担当者から「そろそろ治療を終了して示談しませんか」「120万円を超えるとこちらも支払いが厳しくなる」等と治療の早期終了を促される場合があります。慰謝料額は治療期間の長さに比例するため、保険会社は支払額を抑える目的で治療の打ち切りを誘導することがあるのです。
しかし、治療終了の時期を判断するのは医師であって保険会社ではありません。症状が残っているうちは主治医と相談のうえ治療を継続し、保険会社から終了を打診されても鵜呑みにせず必要性を根拠に延長交渉することが望ましいです。
適切な期間治療を続けることが、適正な慰謝料を得ることにつながります。
低すぎる示談金への対処
明らかに低額な慰謝料提示を受けた場合は、すぐに妥協せず増額交渉を検討しましょう。例えば「入通院慰謝料は日額4,300円で計算しています」といった提示は自賠責基準そのものなので、その金額で応じるべきではありません。
保険会社提示額は初回では適正額より低いことが多いため、まずは被害者側で裁判基準相当の金額を把握し、根拠を示して増額を求めます。
具体的には、「通院◯ヶ月の場合、裁判基準では〇〇万円程度が相場です」と資料をもとに主張したり、示談金の妥当性について弁護士の意見書を出すなどの方法があります。
交渉を有利に進める工夫
慰謝料増額交渉では、被害者自身の治療状況の記録や態度も重要です。事故後はできるだけ早く病院を受診し、初診時に痛む箇所や症状を漏れなく医師に伝えて記録してもらいましょう。
痛みを我慢して通院間隔が空くと「実際にはケガの重大性はないのではないか」と考えられ、実通院期間より短い期間で慰謝料を計算されてしまうことがあります。
適切な頻度で定期的に通院することが大切です。また、整骨院等に通う場合は、原則として医師の指示が必要であるため、特に注意が必要です。事前に保険会社に相談するだけでなく、医師にも報告しておきましょう。
こうした点に留意しつつ、自分でも資料を揃えて交渉に備えることで、適正な慰謝料額の獲得に近づけます。
入通院慰謝料の増額事例
保険会社提示額から裁判基準へと慰謝料が増額された事例は数多く報告されています。
弁護士に相談するきっかけの多くは「示談金額が低すぎると感じた」「提示額の妥当性が判断できない」といったものですが、結果的に適正額への増額に成功したケースが多く見られます。実際、弁護士基準で計算し直すことで慰謝料が1.5~2倍近くに増額した例も珍しくありません。
増額の具体例
あるケースでは、被害者が右足の指および踵骨折の重傷を負い約10ヶ月間(入院1.3ヶ月+通院9.4ヶ月)治療したところ、保険会社から当初約99万円の慰謝料等が提示されました。
しかし弁護士が介入して交渉した結果、最終的に約150万円まで増額して示談成立した例があります。
この事案では入通院慰謝料を中心に約60万円もの増額が実現しており、裁判基準に近い水準まで引き上げられました。
増額が見込めるポイント
慰謝料増額が認められるかどうかには、いくつかの要素が影響します。
まず通院期間・頻度は重要です。先述のとおり通院頻度が低すぎると慰謝料を低く見積もられるおそれがある一方、適切な頻度で医師の指示どおりしっかりと治療を続ければ、その通院期間に見合った慰謝料が認められやすくなります。
次に治療内容や苦痛の程度も増額の考慮要素です。例えば手術を要する大怪我であれば入通院期間中の苦痛も大きいため、裁判基準の定型額より20~30%程度増額されるケースもあります。
生命の危機を伴う重篤な状態や、麻酔なしの手術・複数回の手術を受けた場合などは、入通院期間の長短にかかわらず特別に慰謝料が上乗せされることもあります。
また、治療の結果残念ながら後遺障害が残った場合は、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料を請求でき、トータルの賠償額が大幅に増える要因となります。後遺障害等級の認定を適切に受けることで、その等級に応じた慰謝料が追加で支払われるため、適正な等級認定も見逃せないポイントです。
さらに、被害者の年齢や職業、事故の態様など個別事情によって保険会社が独自に減額を主張している場合でも、弁護士が法的根拠を示しつつ交渉することで適正額まで引き上げられた例があります。
総じて、示談段階で提示された慰謝料が低額に感じられる場合は、増額の余地がないか専門家に確認し、通院状況や治療内容など増額につながる要素を適切に主張することが重要です。
以上のように、入通院慰謝料は事故による治療期間中の精神的苦痛への賠償であり、計算基準によって金額が大きく異なります。
被害者としては各基準の違いと相場を把握したうえで、自身のケースに照らした適正額を見極め、安易に低い提示に応じないよう注意することが大切です。
適切な期間・頻度で治療を続け客観的資料を揃えるとともに、必要に応じて弁護士と協力して交渉に臨めば、裁判基準に近い十分な慰謝料を獲得できる可能性が高まります。