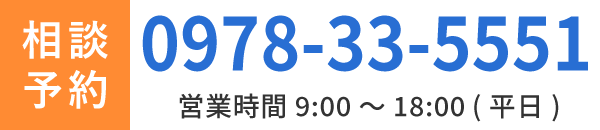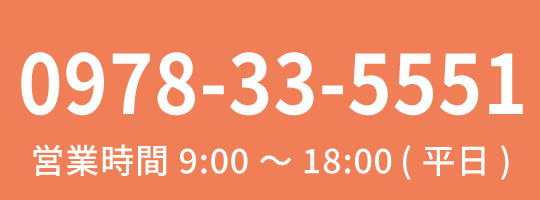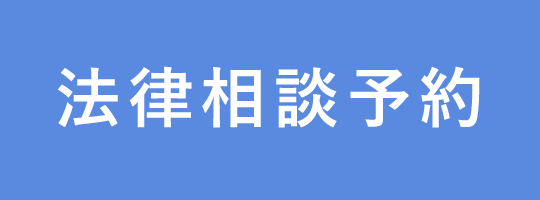このページでは、示談提案が保険会社から送られた場合に、どのように対応すべきかを説明しています。保険会社は裁判基準とは異なる独自の基準で提示を行うため、安易に示談することは避けることが望ましいです。弁護士への無料相談を行うなどして、金額の妥当性を確認する必要があります。
このページの目次
1. 示談の流れと基本的な進め方
示談とは
示談(じだん)とは、裁判などの法的手続きを経ずに当事者同士の話し合いで損害賠償の内容を決める解決方法のことです。要するに賠償金の支払い方法を取り決める一種の契約であり、いったん成立すると当事者の一方的な都合で破棄することはできません。
保険会社から示談書(免責証書)が送られてきて被害者が署名押印して返送すると、その内容で契約が成立し、記載された金額しか受け取れなくなります。
示談交渉の流れ: 交通事故発生から示談成立までの大まかな流れは以下のとおりです。
1. 事故発生・初動対応
事故が起きたら警察に連絡し(交通事故証明書の取得のため必須)、現場の記録や相手の連絡先・保険情報の確認など初期対応を行います。自身の加入する保険会社にも事故発生を連絡します。

2. 治療・通院
怪我を負った場合、病院で治療に専念します(入院・通院)。加害者側の任意保険会社と連絡を取り、治療費の支払いなどの手続きを進めます。車両の修理交渉など物的損害の対応も並行して行います。

3. 症状固定 or 完治
一定期間治療を続け、ケガが完治するか、またはそれ以上治療を続けても改善が見込めない状態(症状固定)になります。保険会社が独自判断で「もう症状固定です」と言ってくる場合もありますが、医師が必要と判断する限り治療を継続すべきです。症状固定を急ぐと十分な治療ができず、後の補償にも影響するため注意してください。

4. 後遺障害等級認定(必要な場合)
症状固定と診断されても体に痛みや障害が残っている場合、自賠責保険を通じて後遺障害等級の認定申請を行います。これは将来に残る障害の程度を公的に認定する手続きで、認定されると後遺障害慰謝料や逸失利益など追加の賠償項目が発生します。
適切な等級を得るため、医師に作成してもらう後遺障害診断書の内容を確認し、不明点があれば弁護士に相談しましょう。

5. 保険会社からの示談提案・交渉開始
治療が終了し(後遺障害がある場合は等級認定後)、請求すべき損害額が確定できる段階になれば、加害者側の保険会社との示談交渉を開始できます。
通常、相手方保険会社の担当者から示談金の提案(示談案)の連絡が来たり、示談書案が郵送されてきます。提示内容に対し、被害者側の要望や妥当な金額を伝えて金額や条件の交渉を行います。
話し合いは電話や対面で行われることもありますが、記録を残すためできるだけ書面やメールでやり取りすることが望ましいでしょう。

6. 示談の合意・示談書の締結
損害賠償の金額や過失割合など交渉内容に双方が合意できたら、示談成立です。通常は保険会社が示談書あるいは免責証書を作成し被害者に送付します。被害者がその書面に署名押印して返送すると契約が正式に成立します。
示談書には賠償内容の詳細や「本件に関する一切の請求権を放棄する」旨の条項(清算条項)が含まれるので、内容をよく確認する必要があります。

7. 賠償金の支払い
保険会社は署名済みの示談書(免責証書)が返送され次第、被害者指定の口座へ賠償金を振り込みます。送付から支払いまではおおむね1~3週間程度であることが一般的です。支払いが完了すれば事故案件は解決(示談終了)となります。
示談成立までにかかる期間の目安
示談交渉に要する期間は事故内容や怪我の程度によって様々ですが、示談交渉開始から合意成立まで概ね3か月~1年程度が目安とされています。
軽い怪我で後遺障害が残らないケースでは3~6ヶ月ほどでまとまることも多い一方、重い後遺障害が残る事故や死亡事故では解決まで半年~1年程度かかることが多いようです。
治療期間が長引けばその分示談開始も遅れ、解決まで長期化しますが、逆に不当に急いで示談すると必要な補償を見落とす危険があります。焦らず適切なタイミングで交渉を始めることが大切です。
示談成立後、保険金の支払い自体は通常迅速で、書類返送後おおよそ2週間以内には振り込まれるケースが一般的です。
2. 示談金額の適正性の確認方法
賠償額算定の3基準
交通事故の損害賠償額には大きく分けて「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」という3つの算定基準があります。
それぞれ算出される金額に大きな差があり、自賠責基準は自賠責保険による最低限の補償額、任意保険基準は各保険会社が独自に定めた社内基準、そして弁護士基準(裁判所基準)は裁判例に基づき算定される最も高額な基準です。
任意保険基準の詳細は公開されていませんが、自賠責基準より多少高い程度で、実際には自賠責とほぼ同額かそれ以下の提示となるケースもあります。
一方、弁護士基準は裁判所で認められる水準であり、入通院慰謝料(ケガの慰謝料)が自賠責基準や任意基準の1.5~1.8倍程度になることもあるなど、はるかに充実した金額になります。
例えば後遺障害慰謝料では、保険会社基準だと弁護士基準の2分の1~3分の1程度にまで減らされるケースが多いと報告されています。また入通院慰謝料も保険会社基準では大幅に低く抑えられ、専業主婦の休業損害なども低額に見積もられがちなので注意が必要です。
保険会社提示額の適正性判断
加害者側保険会社が提示する示談金額は、多くの場合このうち任意保険基準にもとづいて算定されています。
任意保険基準は前述の通り金額が低めに設定されていることが多く、保険会社からの示談案の金額は法的に妥当な水準よりかなり低いのが現状です。そのため初めて示談交渉をする被害者は「こんなものか」と思って応じてしまいがちですが、実は適正額より低い提案であるケースが多々あります。
示談金の相場を知らないと、提示額が適切か判断できずに知らぬ間に不利な条件で示談してしまうおそれがあります。逆に言えば、保険会社提示額の適正性を確認するには弁護士基準で計算し直してみることが有効です。
弁護士が介入せず被害者本人で交渉している限り、保険会社はまず弁護士基準では支払いませんが、仮に裁判になった場合の金額を算定して比べてみれば、多くのケースで「本来もらえるはずの金額」が見えてきます。保険会社の提示額がその水準とかけ離れて安ければ適正とは言えません。
各損害項目ごとの相場確認
示談金の内訳には、治療費・通院交通費、休業損害、入通院慰謝料(傷害慰謝料)、後遺障害慰謝料、逸失利益など様々な項目があります。それぞれについて妥当な金額かチェックしましょう。
例えば慰謝料の相場は、治療期間や内容によって算定されます。自賠責基準では通院1日あたり4,300円という計算式がありますが、裁判基準では怪我の程度に応じて1日6,000~7,000円超程度になることもあります。
また休業損害は、事故による収入減を補填するものです。会社員なら事故前の給与水準から日額を算出し、休業日数を掛けて計算します。
専業主婦(家事従事者)の場合でも法律上は職業主婦とみなされ、賃金センサス等にもとづく日額(女性平均賃金相当額)で算定するのが裁判基準ですが、保険会社はしばしば自賠責基準の日額6,100円という低い金額で計算した額しか提示しないことがあります。
後遺障害慰謝料(後遺症が残った場合の慰謝料)は等級ごとに裁判基準額の目安(いわゆる赤本の基準額)が定められており、例えば最も軽い14級でも裁判基準では110万円前後と言われますが、自賠責基準では32万円と大きな差があります。
保険会社提示額がどの基準に基づくかで大きく異なるため、各項目について「本来の相場」と照らし合わせて適正か判断することが重要です。自信がなければ、法律事務所の無料示談査定などを活用し弁護士にチェックしてもらうのも有効でしょう。
3. 示談前に確認すべきポイント
示談に応じてしまう前に、以下の点をしっかり確認しましょう。
過失割合の適正性
保険会社から提示された過失割合(事故の責任の割合)が妥当か確認します。加害者側保険会社は被害者にも過失があるとして割合を高めに主張し、賠償金を減額しようとする傾向があります。法律の知識がない被害者だと、提示された過失割合が本来より不当に高くても気づかず受け入れてしまうおそれがあります。
事故の状況や信号の有無、スピード違反の有無などから適正な過失割合を算出し、提示と比べて不当に不利でないかをチェックしてください。必要に応じて過失割合の根拠(判例タイムズの基準など)を示し、保険会社に修正を求めましょう。不安がある場合は、弁護士に依頼して交渉することが有効な場合も多いです。
損害賠償の内容と対象範囲
示談書に盛り込まれる損害賠償の項目が漏れなく適正かを確認します。
賠償の内訳として一般に、治療費・治療関係費(通院交通費、薬代、装具代等)、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益、物損(修理費や評価損)、そして場合によっては付添看護費や雑費、葬儀費用などが含まれます。
保険会社の提示額ではこれらの項目で本来支払われるべき費目が抜け落ちていないか、金額が低すぎないかを細かく確認しましょう。
たとえば「入院中の付添看護費用が認められていない」「休業損害が実収入に見合っていない」「逸失利益が失業中だったことを理由にゼロにされている」等のケースもあります。
自分では見落としがちな点も多いので、示談書の損害項目を一つひとつ確認し、不明な点は担当者に質問するか専門家に相談するのが望ましいです。
特に逸失利益(後遺障害による将来の収入減)は計算が複雑なので、等級や労働能力喪失率、基礎収入額の設定が正しいか注意しましょう。
後遺障害の有無と等級認定手続き
示談を結ぶ前に、自分のケガに後遺症(後遺障害)が残りそうかどうか必ず確認します。
交通事故による怪我が完全に治りきらず症状が残っている場合、すぐ示談せず先に「後遺障害等級」の認定申請を行うことが重要な場合があります。
後遺障害等級は症状固定と診断された後に申請し、認定されると等級に応じた慰謝料と逸失利益が賠償されます。
ところが保険会社からはその案内がないまま示談提案がなされることもあり、被害者が知らずに応じてしまうと本来得られるはずの後遺障害分の補償を逃す結果になりかねません。
また、症状固定のタイミングもポイントです。保険会社から「そろそろ症状固定では」と打診されることがありますが、これは保険会社が賠償額を抑える目的で早期打ち切りを図っている可能性があります。担当医がまだ治療の必要ありと判断するうちは、安易に症状固定とみなさず治療を続けましょう。
正式に症状固定となった後、後遺障害診断書を書いてもらい、自賠責へ等級認定の申請をします。等級認定の結果が出るまで示談しないことが重要です。もし認定されなかった場合でも異議申立ての道があります。
後遺障害が残るか微妙なケースでは、主治医とよく相談し将来に残る症状がないか確認しましょう。等級認定前に示談してしまうと、その後に後遺症が判明しても原則追加請求はできません。
交通事故後の経過と症状固定の確認
治療の経過を自分でも把握し、医師から「もう治療を続けても改善しない」と言われ症状固定となったタイミングを確認しましょう。
症状固定前に示談しないことが鉄則です。
まだ痛みや不調が残っているのに示談に応じてしまうと、その後に症状が悪化したり長引いた場合でも追加補償を受けられなくなります。保険会社の中には治療中にもかかわらず早期に示談を勧めてくる場合がありますが、「治療継続中なので示談できない」旨をはっきり伝えてください。
特にむち打ちなどは後から症状が出ることもあるため、交通事故から十分な時間が経ち、症状が安定してから示談交渉を始めることが大切です。
経過中に保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合も、主治医と相談のうえ必要であれば治療を継続しましょう(健康保険や自費で継続し、後で請求することを検討することもあります)。
示談前には主治医の診断書で現在の後遺症の有無・症状固定日を明記してもらい、今後かかる可能性のある費用も含めて請求漏れがないよう確認します。
4. 示談書にサインするリスクと注意点
一度サインしたら基本的にやり直し不可
示談書や免責証書に署名押印してしまうと、後から「もっともらえるはずだった」と気づいても基本的には覆せません。
免責証書には「本書面に記載された事項を除き、一切の請求を行わない」旨の条項(清算条項)が設けられており、示談成立=今後の追加請求権放棄を意味します。つまり示談書に書かれていない損害について後日請求することは原則できなくなるのです。
判例上、ごく例外的に「当時予見できなかった後遺症や再手術」が発生した場合のみ例外的に追加請求を認めたものもありますが、その「予見不能」のハードルは非常に高く、実務的には一度示談したら再交渉はほぼ不可能と考えるべきです。
したがってサインする前に、本当にその内容で問題ないか慎重に検討する必要があります。
示談書(免責証書)の文言に注意
示談書とは当事者同士で作成する和解契約書ですが、保険会社から送られることの多い免責証書は、被害者が署名するだけで成立する示談契約書のようなものです(加害者本人の署名を要さず迅速に取り交わしできる書面として保険会社が用いるケースが多いです)。
どちらも示談するという意味では同じで、「本件事故に関し、記載の賠償金以外は一切請求しない」旨が記載されています。署名前に示談書(免責証書)の記載内容を熟読しましょう。
早期示談のデメリット
保険会社から提示を受けると、つい早く解決したい気持ちから応じてしまいがちですが、治療途中や症状が安定しないうちに早期示談することには大きなリスクがあります。
治療継続中に示談してしまうと、その後に症状が悪化したり後遺症が判明しても追加補償を受けられません。特に後遺障害等級の認定前に示談すると、後から等級が認められるような後遺症が出ても一切の請求ができなくなります。
また、治療費や休業損害の支払いを途中で打ち切る代わりに示談金〇〇円を支払うという提案をされる場合もあります。
しかし被害者にとっては、治療を続ければ完治したかもしれないのに十分な治療機会を失ったり、後遺症が残ったのにその補償を受け損ねたりといった不利益が生じます。
症状固定前の示談は原則避け、少なくとも医師から「もう治療しなくてよい」と言われるまでは示談に応じない方が安全です。保険会社から「今回だけ特別に早期解決しましょう」と言われても鵜呑みにせず、長い目で見て損のないタイミングを選びましょう。
示談を急がせる相手の言葉に流されず、一度立ち止まって考える冷静さが必要です。
5. 弁護士に相談すべきタイミングとそのメリット
相談のタイミング
弁護士への相談は「早いほど良い」のが一般的です。
具体的には、保険会社から示談の提示を受けたら、サインして応じる前に一度弁護士にその金額が適切かどうか相談するのがおすすめです。後になって「やはり金額が低すぎたのでは」と思っても、前述のとおり示談後の撤回は極めて困難だからです。
弁護士に相談すれば提示額の妥当性を法律の専門家の視点で精査してもらえますし、交渉すべきポイントのアドバイスも得られます。
相談する時期としては、事故直後からでも構いません。実際には、①事故直後、②治療終了の前後、③保険会社との交渉開始時、④後遺障害等級の認定結果が出た時などが弁護士に相談する好機と考えられます。
どのタイミングであっても相談は有益ですが、できれば示談交渉が本格化するなるべく早い段階で相談しておくと安心です。
特に保険会社から示談書が送られてきたり電話で示談金額を提示されたりした段階では、一人で即答せず「検討します」と保留し、弁護士のセカンドオピニオンを仰ぐと良いでしょう。
弁護士に依頼するメリット
弁護士に相談・依頼することで得られるメリットは多岐にわたります。
メリット①
第一に、示談金の増額が期待できます。
保険会社の提示額は前述のように低めですが、弁護士が代理人として交渉に当たることで当初提案より増額できるケースがほとんどです。事実、弁護士が介入し裁判基準で算定し直した結果、示談金が2倍以上にアップした例も多数存在しています。
保険会社も弁護士が付いたとなれば安易に低い金額では済まなくなるため、結果的に被害者本人で交渉するよりも高い賠償金となる可能性が高いのです。
メリット②
第二に、交渉の負担軽減があります。
保険会社とのやり取りや書類作成は精神的・時間的負担が大きいですが、弁護士に依頼すれば煩雑な交渉を代理してもらえます。被害者は治療や日常生活に専念でき、保険会社からのプレッシャーも直接受けずに済みます。
また、法律の専門知識に基づいて主張してもらえるので、見落としがちな損害項目も含め適正な賠償額を請求できます。
メリット③
第三に、的確な戦略と安心感です。例えば過失割合の主張や後遺障害等級への異議申立てなど、専門知識が要求される局面でも弁護士なら的確に対応できます。
交渉が難航した場合に訴訟や調停に移行する判断もタイミング良く下せますし、最初から弁護士が付いていることで保険会社との対等な交渉が可能になります。
弁護士費用特約の活用
「弁護士に頼みたいが費用が心配」という方も多いですが、自動車保険等に付帯できる弁護士費用特約を利用すれば経済的な負担なく弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約とは、被害者側の保険会社が弁護士費用を補填してくれる特約で、自動車保険や火災保険、クレジットカードの付帯保険などについていることが多いです。通常は弁護士費用合計300万円、法律相談料は10万円まで保険会社が負担してくれます。
交通事故の示談で弁護士費用が300万円を超えることは稀ですから(最終的な示談金が数千万円規模にならない限りまず超えません)、多くのケースで、特約さえあれば実質自己負担ゼロで弁護士に依頼できると言えます。特約は本人の保険だけでなく家族の保険についている場合に使えるケースもあります。
したがって、加入している保険を確認し、弁護士費用特約が使えるなら積極的に活用しましょう。特約を使えばデメリットはほぼなく、費用倒れの心配をせずに専門家の力を借りることができます。
仮に特約がなく費用がかかったとしても、弁護士に依頼することで最終的に手元に残る金額が増えるケースは非常に多いです。
当事務所では初回無料相談を行っていますので、弁護士費用と増額見込額を比較し、メリットがあるか相談してみると良いでしょう。
6. 示談後に後悔しないための対応策
示談前の万全な準備
後悔しないためには、示談に入る前の段階でできる限りの準備と情報収集をしておくことが大切です。
まず必要書類を揃えることです。医師の診断書・後遺障害診断書はもちろん、診療報酬明細書や領収書、交通事故証明書、勤務先の休業証明書、収入証明(給与明細や確定申告書)、修理見積書など、請求に必要な証拠類は漏れなく入手しておきます。
これらが整っていれば示談交渉もスムーズになりますし、保険会社から過小な査定をされにくくなります。
また、示談金の相場について事前に学んでおくことも有効です。示談交渉に臨む基本姿勢として「保険会社の言うことを鵜呑みにしない」「感情的にならず冷静に、自分でも相場を調べ、じっくり考える」ことが大事だと指摘されています。
保険会社は交通事故に関する知識も豊富であることが多いです。自分でも事前に類似ケースの賠償額や計算方法を調べ、疑問点を整理しておきましょう。不安があれば示談交渉の前に弁護士の無料相談を受け、場合によっては交渉を依頼することも重要です。
交渉で不利にならないための対策
実際に保険会社との交渉に臨む際は、常に冷静で慎重な対応を心掛けることが必要です。「早く終わらせたい」「自分にも落ち度があるし…」思っても、弁護士などの助力を得て、きちんと客観的な検証を試みましょう。
先方の担当者に何を言われても、すぐ了承したりせず一旦持ち帰って考える余裕を持つことが大切です。
特に電話での口頭提示の場合、その場で「はい」と言わず「検討します」と答えるのが鉄則です。交渉の内容はできれば記録に残すためメールや書面で行い、口頭の場合もメモを残して後から確認できるようにします。
自分に有利だと言われたとしても、それが本当に妥当か疑ってみる姿勢が必要です。「今回だけ特別に限界まで有利な条件にしています」などといわれても鵜呑みにしないことも大切です。
また、不用意な発言に注意します。「だいぶ良くなりました」「生活に支障ありません」などと言ってしまうと、後で慰謝料や休業補償を減額されることになりかねません。
事実と異なることは言うべきではありませんが、聞かれたことには必要以上に詳しく答えず、慎重なコミュニケーションを心掛けましょう。
どうしても自身での交渉に不安がある場合は、途中からでも弁護士に交渉を引き継いでもらうことを検討してください。専門家に任せることで、結果的に有利な条件を引き出しやすくなります。
示談後のトラブルへの対応
万一起きてほしくないことですが、示談成立後に「しまった…」と思う事態が発生した場合の対応策について触れます。まず、示談金を受け取った後に症状が悪化したり後遺症が見つかったケースです。
この場合、原則として追加請求はできませんが、前述のように「当初は予見できなかった重大な後遺症」が後から判明したような極めて例外的状況であれば、法的には再度損害賠償を請求できる可能性も皆無ではありません(昭和43年3月15日最高裁判例)。
しかし「予見できなかった」ことの立証は非常に難しく、現実的には認められるケースはごく稀です。
したがって示談時に将来の悪化リスクも含めて考慮し、医師から「今後こうした症状が出る可能性がある」と言われていることがあれば、その分も織り込んだ金額で示談するか、症状が落ち着くまで示談を待つべきでした。
しかし、「もっと高額な賠償金を払ってもらえるはずだった」という理由だけでは錯誤無効や詐欺取消は認められないとされています。示談後に後悔しないための最大の策は、やはり示談前に慎重を期すことに尽きます。
繰り返しになりますが、示談書にサインして返送してしまえば後戻りはできません。そうなる前に「本当に適正な金額か」「見落としている損害項目はないか」を念入りに確認し、不安があれば弁護士など第三者の意見を求めることが肝要です。
準備と冷静な対応さえしていれば、きっと納得のいく示談に辿り着けるでしょう。示談成立まで気を抜かず、自分の権利を守る姿勢で臨んでください。
以上の点を踏まえて対応すれば、保険会社から示談の提案を受けた際にも慌てず対処でき、適正な賠償を受けられる可能性が高まります。不安な点は弁護士に相談しつつ、慎重に進めるようにしましょう。
対応エリア
当事務所では、大分県宇佐市だけでなく、中津市、豊後高田市、杵築市など周辺のエリアから、交通事故に関するご相談を多数頂いております。交通事故に関する初回相談は無料(弁護士費用特約がある場合は実質無料)となりますので、ご不安がある方は、ひとりで悩まずにご相談頂ければと存じます。