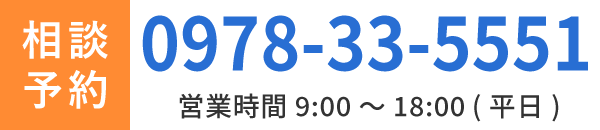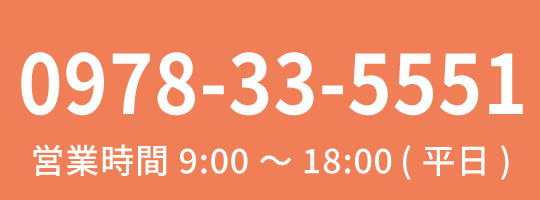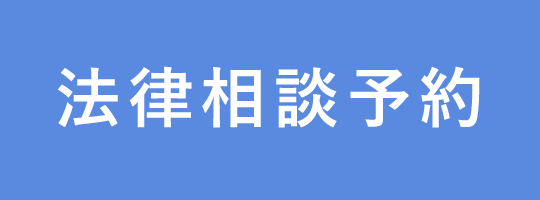このページでは、交通事故直後および治療中にすべきことをまとめています。
このページの目次
1. 事故直後の対応
警察への通報・救急対応
交通事故に遭った直後は、まず怪我人の救護と警察への通報(110番)が最優先です。人身事故・物損事故を問わず、警察への届け出は道路交通法上の義務であり、警察を呼ばないと交通事故証明書が発行されず保険金請求ができなくなる場合があります。
可能であれば救急車(119番)も手配し、負傷者の応急措置を行ってください。
明らかに負傷しているような場合は特に、警察には事故を人身事故として処理するよう伝えましょう。なお、人身事故として届出を行い、後日医師の診断書を提出することで刑事手続きが開始され、警察の捜査記録(実況見分調書)にも詳細が残ります。
物損事故扱いでは実況見分調書が作成されず、後から事故態様が争点となっても反証が難しくなることがあります。
加害者との適切なやり取り
加害者(相手方)とは冷静に対応し、氏名・住所・連絡先をはじめ車両ナンバーや保険情報などを確実に交換しましょう。最低でも名刺や電話番号をもらい、後日連絡が取れるようにします。相手の加入する自賠責保険・任意保険会社名も確認しておくと、保険手続きがスムーズに進みます。
会話の中で加害者の発言(過失の認め方など)も記録できれば有益ですが、自分の発言には注意が必要です。事故直後は動揺して「大丈夫です」と言ってしまいがちですが、後から症状が出ることもあるため安易な発言は避けましょう。
また、その場で示談に応じるよう求められても絶対に応じてはいけません。事故直後は痛みを感じなくても数時間後や数日後に症状が悪化することも珍しくなく、現場で示談してしまうと後から治療費や慰謝料の請求ができなくなるからです
。示談書や免責証書に一度サインしてしまうと原則撤回・やり直しはできず、約束した内容を後から変更することは困難になるため注意しましょう。
事故現場の記録
可能な限り交通事故現場の証拠を残すことも重要です。まず、事故車両を安全な場所に移動させて二次被害を防いだ後、スマートフォン等で写真撮影を行います。自車と相手車両の損傷箇所や位置関係、道路のブレーキ痕、ガードレール等の破損状況、信号機の色などを記録しておきましょう。
警察も現場状況を記録しますが、必ずしも詳細ではなく写真も不鮮明なケースがあるため、自分でも記録を残すことが大切です。
保険会社への連絡
現場対応が一段落したら、できるだけ早くご自身の加入する保険会社に連絡しましょう。自身の任意保険に対人賠償保険が付いていれば、相手からの治療費支払いが滞った場合でも先に保険金の支払いを受けられます(一括対応といいます)。
また、弁護士費用特約(弁護士特約)が付いているかも確認します。弁護士特約に加入していれば、弁護士費用が原則保険で賄われるため、費用負担を気にせず早期に弁護士へ相談しやすくなります。なお、通常、1事故あたり300万円まで弁護士費用が保険で支払われることが多いです。
一方で加害者側には、自身が加入する保険会社(任意保険)へ事故発生を速やかに報告するよう求めます。相手の保険会社への連絡が早ければ、治療費の支払い対応が早期になされやすくなるからです。
2. 医療機関での対応
事故後に適切な診察を受ける理由
事故の直後は痛みがなくても、必ず病院で診察・検査を受けることが望ましいとされています。
というのも、むち打ちなどの場合、交通事故から時間が1週間~2週間程度経って症状が出るケースも多く、早期に医師の診断を受けておかないと「交通事故で負傷した」ことを後から証明できなくなるおそれがあるからです。
時間が経過してしまうと、交通事故との因果関係が証明できないと相手保険会社から治療費や慰謝料の支払いを拒まれる可能性があるため、事故当日か遅くとも数日以内に受診しましょう。
特に、警察へ人身事故扱いにしてもらいたい場合は医師の診断書の提出が必要で、提出が遅れると人身事故として扱われなくなってしまいます。交通事故発生後、できるだけ早く病院に行き、診断書を取得して警察に提出することで、正式に人身事故として扱ってもらえます。
なお、交通事故後しばらくしてから痛みが出た場合でも、早期に受診していれば事故との関連性を証明しやすくなるため、自己判断で我慢せず医療機関にかかることが重要です。
病院・診療科の選び方
交通事故で怪我をしたら、症状に合った適切な診療科のある医療機関を選んで受診します。
たとえば骨折やむち打ち等体の痛みがある場合は整形外科、頭を強く打った疑いがある場合は脳神経外科、といった具合に専門科で診てもらうのが望ましいです。
他にも、目の異常は眼科、耳鳴りやめまいは耳鼻科など、必要に応じて専門医の診察を受けたり、最近は痛みが減らない場合はペインクリニックを紹介される場合もあるようです。
複数箇所に症状が及ぶ場合や全身検査が必要な場合は、整形外科・脳神経外科・耳鼻科など複数の診療科が揃った総合病院で一通り検査を受けるのが適切です。
また、交通事故によるむち打ちの治療では、少なくとも週2~3回程度の頻度で継続的にリハビリ通院する必要が生じますし、治療後に痛みや障害が残れば後遺障害診断書を作成してもらう必要も出てきます。そうした意味でも、無理なく通院を続けられる病院を選ぶことが大切です。
診断書の取得方法と重要性:
診察後、医師に依頼して交通事故の診断書を作成してもらいましょう。
通常、病院の窓口で申し出れば所定の書式で診断書を発行してもらえます(発行手数料は自己負担です)。この診断書は警察提出用と保険会社提出用に使われ、非常に重要な証拠書類です。
また、保険会社との交渉においても診断書は怪我の程度や治療期間を示す基本資料となり、慰謝料増額を裏付ける根拠として要求されます。適切な診断書を確実に入手し、複数部コピーを保管しておきましょう。
なお、診断書の提出が遅れると人身事故証明書(交通事故証明書に人身事故であることが記載されたもの)が発行されず、保険金請求の際に手続きが煩雑になることがあります。
治療中の注意点(通院頻度・リハビリなど)
怪我の治療中は、医師の指示に従った頻度で通院を継続することが重要です。
必要がない限り毎日通院する必要はありませんが、慰謝料算定の観点からは週2~3日程度の通院が適切とされています。無理に毎日通うことで慰謝料が最大になるわけではなく、逆に「治療のために必要な通院」以上に通うと不自然な長期加療とみなされリスクが生じる場合もあります。
また、重傷の場合(例:骨折でギプス固定中など)は月1回程度の診察になるケースもあります。
大切なのは自分の判断で通院を中断・中止しないことです。症状が残っているのに自己判断で治療をやめてしまうと、後日痛みが再発しても事故との因果関係を疑われたり、保険会社に治療打ち切りを主張され不利になるおそれがあります。
そのため、医師から「治癒」あるいは「症状固定」(これ以上治療しても大きな改善が見込めない状態)と判断されるまでは、指示されたペースで根気強く治療とリハビリを続けましょう。
また、リハビリの受け方にも注意が必要です。仕事や家庭の都合で整形外科に通いにくく、整骨院・接骨院・整体など病院以外でのケアを希望する人もいますが、弁護士の見地ではリハビリ治療はできる限り整形外科(病院)だけで受けるべきだといえます。
整骨院等での施術は医師による治療ではないため、症状が残った場合の後遺障害認定で不利になりやすく、保険会社から治療として十分認められない可能性もあります。
さらに、訴訟になった際も、医師からの指示がないことを理由に否認されたり、大幅に減額された結果、治療費が事後的に自己負担になった事例もあります。
どうしても整骨院などに通う場合も、並行して整形外科で定期的に検査・診察を受け、医師の管理下で治療するようにしましょう。複数の医療機関に同時に通院する場合は、診療科や治療内容が異なる範囲であれば問題ありませんが、同じようなリハビリを複数で受けると治療の長期化を疑われ保険会社が治療費支払いを打ち切るきっかけになり得ます。
したがって、主治医と相談しながら適切なリハビリ計画を立て、治療経過をきちんと残すことが大切です。
3. 保険会社との手続き
自賠責保険・任意保険への連絡と手続き
交通事故に遭ったら、被害者・加害者それぞれの保険会社への連絡が必要です。
すなわち、被害者として交通事故直後に行うべきことは、自身の任意保険会社への事故報告(前述のとおり)と、加害者側に対し自賠責保険および任意保険への事故届出を促すことです。
仮に、加害者が任意保険に加入していれば、通常その保険会社が被害者への損害賠償対応(治療費の支払いや示談交渉)を行います。加害者側保険会社から連絡があったら、以降の窓口は基本的にその担当者になりますので、治療状況や損害額についてやり取りしていきます。
万一、加害者が任意保険未加入の場合や、保険会社との交渉が難航する場合には、被害者自らが加害者加入の自賠責保険に直接請求(被害者請求)する手続きも可能です。
もっとも、自賠責保険への被害者請求を行うには所定の請求書に必要書類を添えて提出する必要があり、例えば支払請求書兼支払指図書(保険金の振込先等を指定する書類)、交通事故証明書、事故発生状況報告書、医師の診断書および診療報酬明細書、勤務先の休業損害証明書、通院交通費の明細書、印鑑証明書などが求められます。
自賠責への直接請求は、加害者の協力が得られない場合でも被害者が最低限の補償(治療費・慰謝料等120万円まで)を受け取れるメリットがありますが、提出書類が多く手続きが煩雑です。
通常は加害者側の任意保険会社が自賠責分も含めて一括対応してくれるため、被害者請求は任意保険が使えない場合の手段と考えると良いでしょう。いずれにせよ、事故後は速やかに双方の保険会社に連絡し、指示に従って必要な手続きを進めることが大切です。
保険会社との示談交渉時の注意点
損害が確定し治療が一段落すると、加害者側の保険会社から示談金の提示があります。
しかし、提示された金額を十分に精査せず安易に示談に応じるのは危険です。
保険会社からの示談提案は、被害者にとって最低限のラインであることが多く、実際に弁護士が介入しただけで賠償金額が大幅に上がったという例も珍しくありません。
保険会社は被害者が法律の専門知識を持たないことを前提に、自社に有利な基準(いわゆる「保険会社基準」や自賠責基準)で賠償額を算出してくる傾向があります。一方、弁護士が交渉すれば裁判基準(裁判所が認める相場)での請求が可能となり、保険会社提示額から増額できる余地が大いにあります。
また、一度示談が成立すると原則としてやり直しはできないため、提示内容に納得がいかない場合は焦らず弁護士に相談しましょう。
特に後遺症が残る可能性があるケースでは、症状固定後に後遺障害等級が認定されてからでないと正当な賠償額が算定できません。治療中にもかかわらず保険会社から早期の示談を持ちかけられた場合は、「症状固定していないので示談できない」と断るのが賢明です。
保険会社との交渉では、時効(損害賠償請求権は原則事故から3年で時効)にも注意しつつ、必要に応じて示談交渉を弁護士に代理依頼したり、ADR機関の利用や民事調停・訴訟提起も検討します。過度に紛争を長引かせる必要はありませんが、被害者が正当な賠償を受け取れるよう、慎重に示談交渉を進めましょう。
保険金請求に必要な書類と提出の流れ
適正な賠償金を受け取るためには、請求に必要な書類を漏れなく揃えることが重要です。主な必要書類としては、以下のようなものがあります。
- 事故関係資料: 「交通事故証明書」(警察への届出後、自動車安全運転センターから発行される事故証明)や、事故状況を示す図・メモ、現場や車両の写真など。
- 医療関係資料: 「診断書」(医師が作成した診断証明書)および「診療報酬明細書(レセプト)」や病院の領収書。治療費明細には治療期間や内容が記載され、慰謝料計算や自賠責請求に必要です。
- 後遺障害関係資料: 後遺症が残った場合は「後遺障害診断書」および「後遺障害等級認定結果通知書」(自賠責の等級認定票)など。
- 収入・休業関係資料: 事故前の収入を証明するための「給与明細書(事故前3ヶ月分)」「源泉徴収票」や自営業の場合は確定申告書の写し等。休業損害を請求する場合は勤務先に作成してもらう「休業損害証明書」も必要です。
- その他経費領収書: 通院に要した交通費の明細・領収書、松葉杖や装具代、入院中の雑費、介護費用など実費が発生したものがあればその領収書一式。
- 保険会社提出書類: 保険金請求書(示談書)や委任状など、保険会社から案内される所定の書類。
まず警察発行の交通事故証明書を取り寄せ(電話・ネットや郵便で申請可能)たうえで、病院や勤務先から必要書類を集めます。
保険会社との示談の場合、基本的には保険会社が損害額明細を作成して提示してきますが、被害者側でも上記書類の控えを手元に揃えておくと交渉を安心して進められます。
「証拠書類をしっかり揃えて主張すれば、適切な金額での示談解決が期待できる」ため、提出が必要な書類はあらかじめコピーを取って保管し、抜け漏れのないよう準備しましょう。
4. 事故後の法律相談
弁護士に相談するタイミング
交通事故の被害に遭ったら弁護士への相談は早ければ早いほどメリットが大きいです。
法律上は、病院での初診後であれば示談成立前までいつでも相談・依頼が可能で、治療開始直後からサポートを受けることができます。特に、相手保険会社との示談が成立する前の段階であれば、弁護士は治療期間中から介入して一貫した方針で損害賠償請求のサポートをしてくれます。
事故直後から弁護士に依頼すれば、適切な治療や検査のアドバイス、主治医との連携、保険会社との交渉代行、後遺障害等級取得のサポートなど幅広いメリットが得られます。
一方、示談成立後(加害者との和解契約を交わした後)に相談に来られても、原則として示談内容の撤回や再交渉はできません。
そのため「保険会社の提示する示談金額が適正かわからない」「後遺症が残りそうだがどう請求すれば良いか」など少しでも不安があれば、示談書にサインしてしまう前に弁護士に相談することを強くお勧めします。タイミングとしては、治療が完了し損害が確定する前に相談しておくのがベストです。
なお、被害が軽微な物損事故だけの場合などは弁護士費用倒れ(費用が賠償額を上回ってしまうこと)のリスクもありますが、後述の弁護士費用特約があれば費用負担を気にせず依頼できるため、まずは無料相談などで弁護士の意見を聞いてみると良いでしょう。
なお、当事務所では、交通事故については弁護士費用がない場合でも初回30分無料で法律相談が可能です。
損害賠償請求の流れ(項目と手続き)
交通事故の損害賠償は、大きく治療→症状固定→示談交渉→合意(または訴訟)という流れで進みます。
治療期間中は治療費等の支払方法を保険会社と調整し、治療終了(または症状固定)後に最終的な損害額を算定して賠償請求を行います。
損害賠償の内訳として被害者が請求できる主な項目は、①積極損害(事故により発生した実費損害)、②消極損害(事故に遭わなければ得られたはずの利益の喪失)、③慰謝料(精神的苦痛への補償)に分類できます。
積極損害には、治療費・投薬費、入院費、通院交通費、付き添い看護費、入院中の雑費、車いす等の購入費、死亡事故の場合の葬儀費用などが含まれます。
消極損害とは休業損害や逸失利益のことで、事故のせいで働けなかった期間の収入減(休業損害)や、後遺障害により将来働けなくなる分の収入減(逸失利益)などが該当します。
そして慰謝料とは交通事故による精神的苦痛への補償で、入通院期間に応じて支払われる入通院慰謝料(傷害慰謝料)と、後遺障害が残った場合に支払われる後遺障害慰謝料に大別されます。
例えばむち打ち等で一定期間通院した場合はその期間に対する慰謝料を、後遺症が残って等級認定された場合は等級に応じた慰謝料と逸失利益を請求できます。
これらの損害項目をすべて合算し、過失相殺(当事者の過失割合に応じた減額)等を考慮して最終的な賠償額が決まります。示談交渉では被害者・加害者間で損害額について合意し、合意内容を示談書にまとめて双方署名押印すれば示談成立です。
その後、加害者側(実務上は保険会社)から示談書・免責証書記載の金額が支払われ、事件が解決となります。もし示談がまとまらない場合は、調停や裁判に移行して決着を図ります。いずれにせよ、適正な損害賠償を受け取るには治療の経過・内容を的確に証拠として残し、先述の必要資料を揃えたうえで請求手続きを踏むことが重要です。
弁護士費用特約の活用方法
自動車保険の「弁護士費用特約」(弁護士特約)は、交通事故の被害に関して弁護士に相談・依頼するときの費用を保険会社が負担してくれる特約です。多くの保険会社で1回の事故につき上限300万円までの弁護士費用が補償され、法律相談費用も10万円程度までカバーされます。
通常、弁護士費用は特約の補償範囲内のため、ほとんどのケースで自己負担なく弁護士に依頼可能です。ただし、重度後遺障害や死亡事故の場合は、全体の損害賠償額が大きくなるため、弁護士費用が上限を超えることもあります。
特約を使っても保険の等級(ノンフリート等級)や翌年以降の保険料に影響はありません。そのため、「弁護士に頼みたいが費用が心配」という方も、特約に加入していれば遠慮なく活用すべきです。
利用方法は、まず自身または同居の家族が加入している自動車保険に弁護士費用特約が付いているか確認し、付いていれば保険会社に弁護士特約を使いたい旨を連絡します。
保険会社から所定の手続きを案内され、弁護士との契約後に発生した費用を保険会社が支払うか、あるいは一旦被害者が支払った後で保険会社に請求(立替払いの精算)する流れとなります。
特約は事故直後から示談成立前までいつでも利用可能で、相談のみでも適用される場合があります。万一、自分に特約が付いていなくても家族の契約やクレジットカード付帯保険に同種の特約があれば使えることがあるので、弁護士に相談すれば一緒に保険内容を確認してもらえます。
弁護士費用特約を上手に活用し、費用負担を気にせず専門家のサポートを受けることで、結果的に増額される賠償金を丸ごと受け取れるメリットが期待できます。
相談時に準備すべき資料
弁護士に交通事故の相談をする際は、手元にある事故関係の資料を可能な限り持参すると相談がスムーズです。
具体的には、警察発行の交通事故証明書、事故状況を示すメモや現場・車両写真、医師の診断書、診療報酬明細書や薬局の領収書、保険会社から送付された書類一式(支払い案内や示談提示書類等)、そして収入関係の資料(直近数ヶ月分の給与明細や源泉徴収票、自営業なら確定申告書など)が挙げられます。
また、後遺障害がある場合は後遺障害診断書や認定通知書も必要です。
これらを揃えておけば、限られた相談時間内でも状況把握が的確に行え、弁護士側も見通しを立てやすくなります。
特に賠償金の増額交渉を依頼したい場合、事故前の収入証明や治療費の明細は欠かせません。また、保険証券(ご自身の自動車保険契約内容)が手元にあれば弁護士費用特約の有無も確認できます。
そして、事前に資料を整理し、時系列で経過をまとめたメモを用意しておくと、聞き漏らしや伝え忘れを防げるでしょう。
相談時にこれら資料を提示しながら状況を説明すれば、弁護士から具体的なアドバイスや見通し(見積もり)を示してもらいやすくなり、その後の正式依頼に向けた判断材料にもなります。準備を万全にして臨むことで、法律相談の効果を最大限に引き出すことができます。