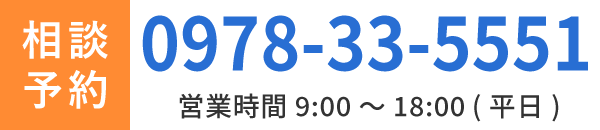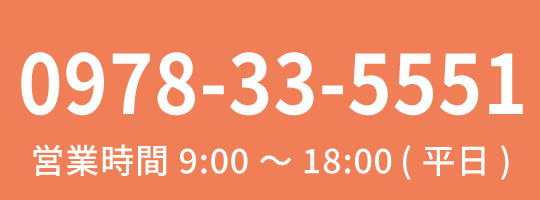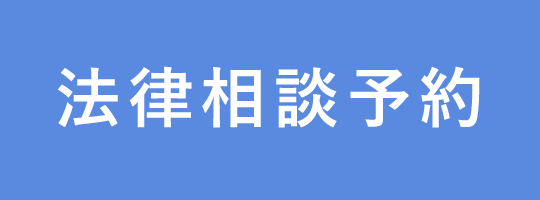このページは、交通事故でご家族をなくされた方が、相手や保険会社の対応でできること・すべきことをまとめています。
突然のご不幸に、ご遺族の皆様は驚き、大きな悲しみに襲われていることと思います。まだ現実のこととも受け止められず、どうしていいか分からないかもしれません。しかし、相手方の保険会社からの連絡がきて、流されるままに対応してしまうと、本来請求できたはずの内容を伝えられず、後悔する結果になることもあります。
そのようなことにならず、ご家族が残してくれたものをきちんと受け取れるよう、本ページから情報を受け取っていただければと存じます。
このページの目次
遺族が請求できる損害賠償の内容
慰謝料(死亡慰謝料)
被害者が死亡したことによる精神的苦痛に対する賠償金です。慰謝料額は算定基準によって大きく異なります。
例えば、自賠責保険基準では被害者本人分として約400万円(※2020年4月以降の事故。それ以前は350万円)と定められ、遺族の人数に応じて550~750万円が加算され、被扶養者がいればさらに200万円加算されます。
一方、任意保険基準(加害者側保険会社の社内基準)は公表されていませんが、自賠責より多少上乗せされる程度で、裁判基準より低めとされています。任意保険基準の目安としては、被害者が一家の支柱の場合で1,500~2,200万円程度、専業主婦・配偶者で1,300~1,800万円程度、子供や高齢者で1,100~1,700万円程度といった水準であることが多いです。
裁判所(弁護士)基準では慰謝料額がさらに高額になり、被害者が一家の支柱であれば約2,800万円、配偶者や母親であれば約2,400~2,500万円、その他(独身者の成人や子供・高齢者など)の場合でも2,000~2,200万円程度が認められることがあります。
裁判基準の死亡慰謝料には、亡くなった本人の精神的苦痛だけでなく、遺族固有の慰謝料(遺族の方々の悲痛に対する賠償)も含まれており、遺族(被害者の父母・配偶者・子)であれば民法711条に基づき固有の慰謝料請求権が認められます。近親者固有慰謝料の相場感は、一人当たり200万~300万円程度と言われることが多いです
逸失利益(死亡による逸失利益)
被害者が亡くならなければ将来得られたはずの収入の損失分です。
計算方法は「基礎収入 × (1-生活費控除率) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数」で算出するのが一般的です。
基礎収入は事故前の年収等を基にし、給与所得者だけでなく主婦(主夫)など家事従事者でも相当額の収入(賃金センサスの平均賃金など)を基礎に認めます。
生活費控除率とは、被害者が生存していれば自身の生活費に充てただろう分を控除する割合で、被扶養者の有無や被害者の属性によって異なります。
典型的には一家の生計を支えていた男性で扶養家族が複数いる場合は30%(扶養家族1人の場合は40%)、女性(主婦や独身女性、子供を含む)の場合は30%、独身の男性や扶養者のいない場合(子供含む)は50%程度とされています。
就労可能年数(働けたはずの年数)は原則として18歳から67歳までとされ、事故時の年齢がそれより若ければ67歳までの残年数が、すでに高齢で67歳未満の期間が短い場合はその実残存期間が採用されます。
ただし職業や健康状態によっては67歳を超えて働けた可能性があるとして延長が認められるケースもあります。
逸失利益算定では将来の収入を現在価値に引き直すため、中間利息控除としてライプニッツ係数(一定の利率にもとづく割引係数)が用いられます。死亡事故では労働能力喪失率は当然100%となり、生涯にわたる収入喪失を計算します。
その結果、被害者が高収入だった場合や若年で将来の働く期間が長い場合、逸失利益が1億円を超えるような高額に及ぶこともあります。
葬儀関係費用
被害者の葬儀に要した費用も損害賠償の対象となります。
自賠責保険では葬儀費は100万円を上限に支払われます。
任意保険基準では概ね120万円以内を目安に支払われることが多いとされます。
裁判基準(弁護士基準)では原則150万円までが葬儀費用として認められる上限額です。
実際の葬儀費用が150万円未満であればその実費相当額が賠償認定されます。150万円を超える高額の葬儀費用がかかった場合でも、それが社会通念上相当であれば裁判で150万円を超える賠償が認められた例もあります。
なお、葬儀関係費用に含まれる具体的な項目としては火葬料、祭壇費、通夜・告別式当日の費用、初七日までの法要費用、墓石・仏壇の購入費などが含まれるとされます。反対に、墓地の購入費や永代供養料、香典返しの費用、年忌法要の費用、戒名料などは通常は葬儀費用の賠償には含まれません。
裁判例によっては、仏壇・仏具や墓碑建立費、遺体搬送費などを葬儀費とは別に必要費用として認めたケースもあります。
その他請求可能な損害
上記のほかにも、事故によって生じた様々な二次的費用や経済的損害が請求可能です。
たとえば、被害者が死亡に至るまでに治療を受けていた場合はその治療費(事故との因果関係がある限り実費全額)や、入院中の雑費、付添看護費、療養中の交通費なども請求できます。事故から死亡までの間に被害者が休業を余儀なくされた期間がある場合は、その休業損害も認められます。
また、被害者が即死だった場合でも、救急搬送費用や遺体の搬送費、現場清掃費等、死亡事故処理に伴う実費が発生していれば損害項目に含めることができます。
さらに、死亡事故の損害賠償を裁判で請求し勝訴した場合には、判決で認められた賠償額の約10%相当が弁護士費用相当額として上乗せされるのが通例です。これは、被害者遺族がやむを得ず専門家に依頼した費用の一部を加害者側に負担させる趣旨で、裁判上認められるものです(示談交渉の段階では通常考慮されません)。
また、裁判になれば事故日(または死亡日)の翌日から年3%の遅延損害金(利息)が加算されます。
これら弁護士費用相当額や遅延損害金も含め、遺族は適法に発生した一切の損害について加害者に賠償請求することが可能です。
死亡事故における過失割合の決定基準
過失割合の決定方法
交通事故では加害者が常に100%悪いとは限らず、被害者側にも一部過失(不注意)が認められる場合があります。
交通事故当時の状況・双方の行動を踏まえ、「加害者と被害者それぞれの事故に対する責任の割合」を算定したものを過失割合といいます。
過失割合の判断は、過去の裁判例を集積した基準(いわゆる判例集や参考図表)や交通ルールに照らして行われます。実務では『判例タイムズ』別冊などに掲載された典型事例の過失割合表や、保険会社間で共有される基準を参照しつつ、交通事故の具体的事情(信号の有無、見通し、速度、当事者の回避措置の可能性など)を考慮して決定されます。
基本過失割合は類型ごとにある程度決まったパターンがありますが、天候や時間帯、道路状況、当事者の違反の有無といった個別事情で修正されることもあります。
過失割合の協議は示談交渉でも重要な論点になりやすく、話し合いで折り合いがつかない場合は最終的に裁判所が過去の判例に基づき判断することになります。
具体的な過失割合の事例
過失割合の典型例をいくつか紹介します。
事例①
まず、自動車同士の事故では優先道路や信号の遵守状況によって割合が分かれます。
例えば、信号機のない交差点で直進車と対向右折車が衝突した場合、直進車が優先されるため右折車の方が過失が重く、基本の過失割合は直進車:右折車=20%:80%とされるのが原則です。双方青信号での交差点でも、直進車優先の原則から直進車:右折車=20:80程度に設定されます。
また、一方の車両が赤信号を無視したような場合は、信号無視をした側の過失が極めて大きくなり、過失割合は無視した側がほぼ100%(もう一方はほぼ0%)に近い扱いとなります。
事例②
次に、自動車と歩行者の事故では、歩行者保護の観点からドライバー側の過失が大きく認定されるケースが多いです。
歩行者が横断歩道を青信号で渡っていた場合は歩行者に過失はなく、基本的に加害車両側の過失100%(被害者側0%)となります。横断歩道のない道路を歩行者が横断中だった場合、歩行者にも安全確認義務違反等の過失が認められ、基本過失は歩行者10~30%:車両70~90%程度とされることが多いです。
例えば横断歩道や信号のない場所で歩行者がいきなり飛び出した事故では、歩行者20%:自動車80%前後が一つの目安です。
ただし、夜間で歩行者が発見困難な状況(例:暗い道路上で歩行者が横たわっていた等)の場合、歩行者側の過失が大きく認定され得ます。
それでも歩行者の過失割合は上限でも7割程度が目安で、車側に少なくとも3割程度の過失は残ると考えられています(実際、夜間に道路上に寝込んでいた歩行者が轢かれた事故の裁判例では基本過失が歩行者50%:車50%とされ、幹線道路だった事情を加味して歩行者過失が最終7割まで修正された例があります)。
事例③
最後に、自動車と自転車の事故では、自転車は車両の一種ですが身体の保護がない点で歩行者に準じる扱いも受けます。ルール違反の内容によって双方の過失が決まりますが、例えば対向方向から進行してきた自転車と右折車が衝突したケースでは、基本的に右折車の過失が大きく、自転車:自動車=1割:9割(10%:90%)と認定された裁判例があります。
このように、事故の形態ごとに典型的な過失割合の基準がありますが、実際の適用にあたっては現場状況や当事者の過失内容に応じて微調整されることになります。
過失相殺が損害賠償額に与える影響
被害者に過失が認められる場合、過失相殺により損害賠償額が減額されます。
算出方法は、まず被害者の全損害額を積算し、そこから被害者過失の割合分を差し引くというものです。
たとえば損害総額が2,000万円で過失割合が加害者70:被害者30の場合、加害者から受け取れる賠償金は2,000万円×(1-0.3)=1,400万円となります。過失相殺により、被害者側の過失が大きいほど最終的な賠償取得額は大幅に減ってしまいます。
極端なケースでは、被害者の過失が50%であれば賠償金は半減し、被害者過失が70%にもなると賠償金は3割程度(原損害の30%相当)しか受け取れません。
適正な損害賠償額を得るには、過失割合を適切に認定してもらうことが重要であり、被害者側過失を不当に高く主張されないよう注意が必要です。示談交渉や裁判では、この過失割合を巡って双方が争うことも多いため、過失相殺について専門知識を持つ弁護士に相談しながら進めることが望ましいでしょう。
示談交渉の流れと注意点
示談交渉の流れ
死亡事故では、まず警察による事故状況の調査や加害者に対する刑事手続き(起訴・不起訴の判断、起訴時の刑事裁判)が進みます。遺族側の損害賠償交渉(民事の示談交渉)は、通常は葬儀や初七日・四十九日など一連の弔い行事が終わった頃から本格的に始まります。
加害者側の任意保険会社から連絡が入り、保険担当者との間で賠償金額についての話し合いを行うのが一般的です。
死亡事故の場合、受け取るべき損害の内容(慰謝料・逸失利益・葬儀費用など)は被害者死亡後比較的早期に確定し得るため、四十九日の法要後あたりで示談交渉を開始されることが多いとされています。
この時点で遺族に弁護士がついている場合は、まず遺族側で損害額の見積もり(逸失利益計算や必要経費の集計など)を行い、請求額を保険会社に提示します。保険会社は社内基準に沿った示談金の提案を行い、金額や過失割合について双方で折衝します。お互いの主張がまとまれば示談書を作成して署名押印し、示談成立となります。
死亡事故では後遺症の経過観察などが不要な分、重傷事故よりも示談交渉の開始が早く、速やかに合意できれば事故から半年以内に示談が完了することもあります。示談書に双方が署名捺印すれば示談成立となり、通常はその後2~4週間程度で保険会社から指定口座に示談金が支払われます(支払い時期は示談書に明記されます)。
こうして民事上の和解が成立すると、加害者に対する賠償請求は最終的に解決となります。
示談交渉のポイントと注意点
遺族が示談交渉を進める際にはいくつか注意すべき点があります。
ポイントと注意点①
第一に安易に早期示談に応じないことです。
保険会社から示談金の提示があると、早く解決したい一心で合意してしまいがちですが、提示額は先方の基準(自賠責や任意保険基準)に沿った最低限の金額である場合が多いです。裁判所基準で計算すれば遥かに高額になるケースでも、被害者側がその基準を知らないまま示談に応じてしまうと適正額との差額が獲得できないおそれがあります。
特に死亡慰謝料について十分な知識がないまま交渉すると、本来請求できるはずの額より大幅に低い金額で妥結してしまうリスクがあります。保険会社の担当者は被害者側に有利な「裁判基準」での支払いには消極的であるため、提示額に納得がいかなければ増額交渉を行うことが重要です。
必要に応じて弁護士に交渉を依頼することも検討すべきといえます。弁護士は裁判所基準を踏まえた適正な賠償額を算出し、専門知識をもって保険会社と交渉してくれます。実際、弁護士が代理人に就くことで示談金が大幅に増額した例も多数あります。
ポイントと注意点②
第二に、加害者の刑事処分確定前の示談は慎重に、という点があります。
特に過失割合が争いになっている場合、確定刑事記録を取得すると、事故状況などについて遺族側に有利な情報が書いてあることがあります。交通事故の事案においては情報が多ければ多いほど有利に交渉を進められるという場合もあるため、刑事処分の確定を待って示談交渉をするというケースもよくあります。
ポイントと注意点③
第三に、過失割合に留意することです。
先ほども説明したとおり、過失割合ひとつで最終的な受取額が大きく変わるため、事実関係に即した公平な割合を主張し、不当な過失相殺を受けないよう交渉します。
保険会社提案の過失割合に納得できない場合は、過去の判例データなど根拠を示して交渉し、必要なら弁護士に相談して修正を求めましょう。
ポイントと注意点④
最後に、示談交渉は基本的に一度きりである点も重要です。
示談書・免責証書には「今後一切異議申立てや追加請求をしない」旨の条項が盛り込まれるのが通常で、示談成立後に「やはり賠償金が足りないので追加で請求したい」と思っても原則として認められません。
したがって、将来発生しうる費用や請求漏れがないか慎重に確認し、適正な補償額かどうか見極めた上で示談に応じる必要があります。特に葬儀直後など遺族が深い悲しみの中にいる時期は冷静な判断が難しいため、十分に時間をかけて検討することが望ましいでしょう。
保険会社とのやり取りや示談内容に不安がある場合、早めに専門家に相談してサポートを受けることをおすすめします。
示談金の受け取りまでの期間
示談交渉開始から解決までの期間はケースバイケースですが、一般的な人身事故では交渉開始から2~3か月程度で合意に至ることが多いとされています。
死亡事故の場合、治療期間の終了を待つ必要がないため比較的早期に交渉に入れる分、事故発生から示談成立まで6か月前後で完了する例もあります。
もっとも、過失割合や金額でもめて交渉が難航すれば1年以上かかることもありますし、逆に加害者側が早期解決を強く望んで高めの金額を提示するような場合には、四十九日明けから数週間で示談がまとまるケースもあります。
示談成立後、保険会社から示談金が支払われるまでの手続き自体は迅速で、示談書を取り交わしてから支払いまでは1~4週間程度です。銀行営業日などの都合がありますが、多くの場合は示談書に記載した支払期日までに一括で指定口座に振り込まれます。
なお、示談金の受領にあたっては所得税などは課税されません(慰謝料・賠償金は非課税)。
示談交渉が成立しなかった場合は、遺族側は民事訴訟(裁判)に移行して賠償金を請求していくことになります。示談不成立から裁判準備・提訴に入るまでさらに時間を要するため、交渉決裂時には弁護士と相談し速やかに次の手続きを進めることが望ましいです。
死亡事故が裁判に発展するケースとその流れ
示談が成立しない場合の裁判への移行
加害者側の提示額と遺族側の求める賠償額に大きな隔たりがあり示談がまとまらない場合、最終的な解決手段として民事裁判(損害賠償請求訴訟)を提起することになります。つまり、示談交渉が決裂した状態は「当事者間の話し合いで解決できない法的紛争」が生じているということなので、裁判所に判断を仰ぐほかありません。
まず、遺族(原告)は加害者(被告)を相手取り、管轄の裁判所に訴状を提出して訴訟を提起します。通常、被告は事故を起こした運転者やその使用者(会社の車で業務中だった場合など)、必要に応じて自賠責保険会社も被告に加えます。
そして、訴状には請求金額や事実経緯、法的主張を記載し、証拠書類(事故証明書、収入資料、計算書など)を添付します。訴状が受理されると裁判所から被告に送達され、以後は口頭弁論(双方が主張を出し合う裁判期日)と書面準備を重ねて審理が進みます。
通常は1か月~2か月おきに期日が設定され、争点や証拠の整理が行われます。双方の主張が出尽くすと、裁判官が和解による解決が可能と見れば途中で和解案を提示し、当事者の合意が得られれば訴訟上の和解で終了する場合もあります。
和解が成立しなければ最終的に判決となり、裁判所が過失割合や損害額について判断を下します。死亡事故の民事裁判は地方裁判所で行われるのが通例で、判決までの期間は概ね半年~1年程度、長くても1年半~2年ほどで解決するケースが一般的です。
ただし事案が複雑で争点が多い場合や、証人尋問・鑑定などを要する場合はさらに長期化する可能性もあります。
裁判になった場合の損害賠償請求の進め方
裁判では遺族側(原告)が損害賠償請求権を立証していく形になります。
具体的には、「被告の過失によって被害者が死亡し損害が生じたこと」「その損害額はいくらか」を主張立証します。過失の有無や程度については、刑事記録(実況見分調書や供述調書など)や目撃証言、事故現場の写真、ドライブレコーダー映像等の証拠を示して立証します。
損害額については、前述の慰謝料・逸失利益・葬儀費等の各項目ごとに資料を揃えます。
例えば逸失利益なら被害者の収入を証明する源泉徴収票や給与明細、職業によっては確定申告書などを提出し、計算書を示します。また、葬儀費用の領収書、各種支出の領収書類も証拠書類となります。
被告側(通常は加害者加入の保険会社の代理人弁護士)は、原告の主張金額が高すぎると考えればそれぞれの項目について反論します。典型的には「被害者の収入見込みはそんなに高くない」「就労可能年数は○年ではなくもっと短い」「慰謝料も相場は○○万円程度だ」といった形で争ってきます。
また過失割合についても被告側がより被害者に過失があると主張してくることが多く、原告と被告の主張が食い違えば主要な争点となります。
裁判では最終的に裁判官が双方の主張と証拠を検討し、妥当な賠償額を算定します。
死亡事故の場合、後遺障害等級の認定などは問題になりません(死亡によって後遺障害の問題自体が消滅するため)が、事故から死亡までに長期間治療期間があったような場合には、その間の傷害部分(入通院慰謝料や後遺障害が残った期間の逸失利益等)が別途検討されることもあります。
基本的には過失割合と損害額算定の2点が裁判での主な争点となりやすいでしょう。
近年の裁判実務では、死亡慰謝料額について裁判官が相場から大きく外れた判断をすることは少なく、多くは裁判基準(一家の支柱2,800万円等)に沿って認定されています。むしろ争いになるのは逸失利益の基礎収入や就労年数、被害者側過失の有無・程度といった点です。
和解期日では裁判所が示す一定の落とし所(例:過失割合や金額の中間点)が提示され、それを受け入れれば和解調書が作成されて訴訟が終了します。和解がまとまらなければ判決となり、裁判所が判断を示します。
裁判での主な争点と留意点
死亡事故の損害賠償訴訟で典型的な争点は上述のとおり過失割合と損害額の内訳です。
まず過失割合について、被告側(保険会社)は自社の支払額を減らすため被害者の過失をできるだけ大きく主張してきます。
原告側としては、事故態様から見て不当に被害者過失が盛られていないか注意し、必要なら専門家による現場分析なども活用して適正な割合を主張します。それを受けて、裁判官は過去の判例だけでなく個別事情を踏まえて判断することになります。
次に損害額では、逸失利益の算定をめぐる争いがよくあります。
被害者の年収が不明確な場合や、職業的将来性が議論になる場合など、原告はできるだけ高い逸失利益を、被告は低めに抑えようとします。
例えば主婦の逸失利益について「女性平均賃金を基礎に算定すべき」とする原告に対し、被告が「実際に収入がないのだから基礎収入ゼロにすべき(逸失利益なし)」などと争う場合があります。しかし判例上、主婦にも家事労働の価値が認められ逸失利益算定されるのが原則ですので、そのような点を主張立証していきます。
同様に、年少者(子ども)の将来収入は男女平均賃金を基にするのが通例ですが、「高校卒相当」「大卒相当」等学歴による差異を主張されたり、高齢者の場合に「平均余命までは働かないから就労年数を減らすべき」と争われることもあります。
慰謝料については前述のように裁判所の相場がある程度固まっており、過失相殺以外で大幅に減額されることはあまりありません。ただ、被告側が「遺族が加害者を処罰感情で酷訴しているから慰謝料は低くてよい」など感情論的な反論をすることも稀にありますが、裁判所は客観的な基準で判断します。
その他、葬儀費用の妥当性(著しく高額なときに全額認めるか)や、死亡と損害との因果関係(持病があった場合に逸失利益をどう見るか)などが論点となる場合もあります。
原告側としては、請求する損害項目それぞれについて法律上・事実上の根拠を示し、漏れなく賠償が認められるよう主張していく必要があります。
当事務所の対応エリア
当事務所では、大分県宇佐市だけでなく、中津市、豊後高田市、杵築市など周辺のエリアから、被害者の方が亡くなられた交通事故に関するご相談を頂いております。交通事故に関する初回相談は無料(弁護士費用特約がある場合は実質無料)となりますので、ご不安がある方は、ひとりで悩まずにご相談頂ければと存じます。