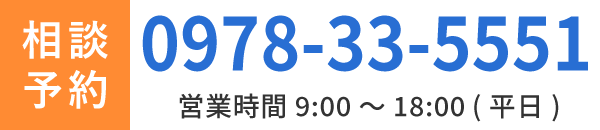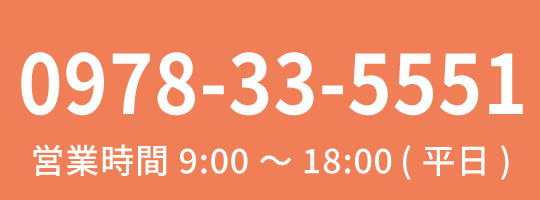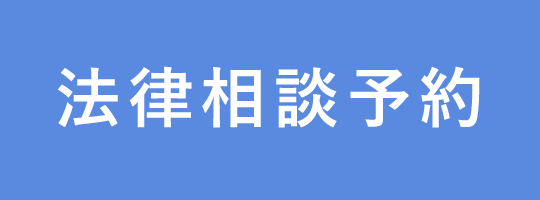このページでは、後遺障害(後遺症)についての説明をしています。
後遺障害の有無は、交通事故の紛争でも争点になることが多いです。後遺障害の認定を受ける前に示談をしてしまうと、適切な賠償をが受けられない可能性があるため、後遺症が残りそうなときは、弁護士への相談を行う必要があります。
このページの目次
交通事故における後遺障害の基礎知識とポイント
後遺障害の定義と認定基準
「後遺障害」とは、交通事故で負ったケガが十分治療しても完全には治らず、労働能力が低下する障害が残った場合で、その障害が自賠法施行令で定める等級に該当するものを指します。
一般に「後遺症」と呼ばれるものの中でも、医学的に事故との因果関係が証明され、症状固定(これ以上治療しても改善しない状態)後も残存し、身体機能の障害により労働能力の喪失・低下が認められるものだけが法律上「後遺障害」と認定されます。例えば、事故による痛みが残っていても労働や日常生活に支障がない軽微な症状は後遺障害には該当せず、賠償請求の対象になりにくいので注意が必要です。
後遺障害が認定されるか否かは、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の基準に則って判断されます。
自賠責保険と労災保険の後遺障害認定基準は基本的に同じで、1級~14級まで共通の等級表に準じます。裁判所は自賠責や労災の認定に法的に拘束はされませんが、実務上はそれらの等級を参考に損害額を算定するのが通常です。
ただし裁判では提出された証拠に基づき独自に後遺障害の有無・程度を判断でき、自賠責で非該当でも裁判で後遺障害ありと認定された例もあります。
総じて、後遺障害の認定には医学的要件(事故による障害が医学的に裏付けられること)と労働能力喪失の有無(障害により働けない・働きにくい状態になっていること)が重要なポイントとなります。
後遺障害等級(1級~14級)の詳細と認定条件
後遺障害等級は症状の重さ・深刻さに応じて1級から14級まで定められています。数字が小さいほど障害の程度が重く、賠償額も大きくなります。
特に1級および2級については介護を要する後遺障害(常時または随時介護が必要な重度障害)か否かで区分され、それ以外の後遺障害は1級~14級に分類されます。後遺障害等級は種類別に細かく定義されており、全部で35系列・140項目以上の認定基準があります。以下に主な等級の概要と代表的な認定条件を挙げます。
1級(最重度)
日常生活のほとんどに介護が必要となるような重度の障害です。例として、脳や脊髄の重傷で遷延性意識障害(植物状態)に陥った場合や、四肢麻痺で身の回りのことが自力でできない場合などが該当します。また、常時介護を要しない場合でも両目が失明したケースや、両腕を肘関節以上で失ったケースなどは1級○号として認定されます。
1級に認定されると労働能力喪失率は100%とみなされ、一生涯にわたり働けないものとして損害賠償額が算定されます。
2級
1級に次いで重い障害です。両目の視力がごくわずか(片眼失明かつ他眼の視力0.02以下)になった場合や、高次脳機能障害により常時の介護は不要でも意思疎通や身辺処理が著しく困難な場合などが該当します。両上肢を手首以上で失ったケース(両前腕切断)も2級に分類されます。労働能力喪失率は原則100%と扱われます。
3級~5級
重度の障害で労働能力の大部分を失うものの、介護までは不要なレベルです。例えば片目が失明し他眼も重度視力低下(0.06以下)の場合は3級1号、片腕を肩関節から失った場合は5級3号、片腕を手関節以上で切断した場合は5級4号、といった具合です。
また一耳の聴力を完全に失い、他耳も日常会話が困難なレベル(他耳の聴力が40cm以上の距離で普通の話声を聞き取れない)になった場合は6級相当になります。このレンジでは労働能力喪失率はおよそ56%~79%(5級で79%、4級で92%、3級で100%)と設定されています。
6級~10級
中程度の障害です。両耳の聴力が大幅に低下し、耳元で大声を出されないと聞き取れないような場合は6級3号、片耳が完全失聴し他耳も日常会話に支障がある場合は7級相当になります。
また、足の指を全部失った場合が7級、片足を足首以上で切断した場合が5級に該当するのに対し、足の一部(例:足指の一部)を失った程度であれば10級や13級など軽い等級にとどまります。
脊椎の圧迫骨折による変形障害などは症状に応じて8級~12級あたりに認定されることがあります。労働能力喪失率の目安は7級で56%、8級45%、9級35%、10級27%です。
11級~14級(比較的軽度な障害)
一見して重大ではないものの、何らかの機能障害や症状が残るケースです。両耳の軽度難聴(小声だと1m離れると聞こえない程度)は11級5号、嗅覚を全て失った場合は12級相当、鎖骨などが変形して凸凹が残った場合は12級5号に分類されます。
局部に神経症状を残すもの、いわゆるむち打ちなどで痛み・痺れが残っているケースは他覚所見(MRI画像などで神経圧迫等の証拠)があれば12級13号、客観的な異常所見に乏しい場合は軽いものとして14級9号に認定されることが多いです。また、指の一部を失った場合(指の関節の欠損・機能障害)は13級または14級に該当します。
14級は後遺障害の中で最も軽い等級ですが、それでも労働能力喪失率は5%と評価され、将来収入の5%相当を失うものと扱われます。もっとも、むち打ちの場合は労働能力の喪失期間が5年程度と考えられる場合が多いです。
なお、自賠責の後遺障害非該当となるケースも多く、例えばむち打ちで数ヶ月の治療後に痛みが多少残存する程度では、「後遺障害とは認められない」と判断され14級にも該当しないことがあります。
等級別の慰謝料・逸失利益の目安
等級に応じて後述する慰謝料や逸失利益の金額が概ね決まっています。
自賠責保険では各等級ごとに定額の保険金が定められており、例えば14級なら自賠責の後遺障害慰謝料は32万円です。一方、裁判基準(弁護士基準)では14級の慰謝料相場は約110万円とされており、自賠責基準額との開きがあります(任意保険基準の慰謝料は自賠責よりは高いものの、裁判基準よりかなり低めです)。
以下に一例として主要な等級の慰謝料目安(自賠責基準と裁判基準)を示します。
- 14級: 自賠責慰謝料32万円、裁判基準慰謝料は約110万円。労働能力喪失率5%で、逸失利益は収入の5%が就労可能年数分失われる計算になります。
- 12級: 自賠責慰謝料94万円。裁判基準の慰謝料相場は約290万円前後とされています(12級は労働能力喪失率14%)。
- 9級: 自賠責慰謝料249万円。裁判基準では慰謝料約690万円程度が目安です(労働能力喪失率35%)。
- 5級: 自賠責慰謝料618万円。裁判基準では慰謝料およそ1,400~1,500万円が相場です(労働能力喪失率79%)。
- 1級: 自賠責慰謝料1,150万円(要介護でない場合)。裁判基準の慰謝料は約2,800~3,000万円と非常に高額になります(労働能力喪失率100%)。※1級要介護の場合は別途介護料を含む増額あり。
このように、等級が重くなるほど金額が大きくなり、また算定基準によっても慰謝料額は大きく異なります。等級ごとの具体的な金額は後述する「慰謝料の計算方法」の項目でも説明します。
後遺障害慰謝料の計算方法
後遺障害が認定された場合、被害者は後遺障害慰謝料(後遺障害による精神的苦痛に対する賠償)を加害者に請求できます。慰謝料の金額は前述の等級によって異なりますが、実際の支払い額はどの算定基準を適用するかによって大きく変わります。日本では一般に次の3つの基準が使われます。
自賠責基準(任意保険会社も最低限ここに準拠)
被害者救済のために法律で定められた強制保険の基準で、必要最小限の補償にとどまります。等級ごとに定額の慰謝料が定められており、例えば1級(要介護なし)で1,150万円、14級で32万円といった具合です。
自賠責保険では後遺障害慰謝料と逸失利益を合わせた支払限度額も決まっており、たとえ被害者の損害がそれを超えても自賠責からは上限までしか支払われません。
任意保険基準
加害者側の保険会社が独自に定める社内基準です。かつては損保各社共同の「旧任意保険基準」がありましたが現在は公開されていません。しかし実務上は自賠責基準よりやや高い程度で、裁判基準の半分以下であることが多いとされています。
被害者が弁護士に依頼せず保険会社と直接示談すると、この低い任意保険基準で提示されることが多く、適正額の1/3~1/2程度に抑えられるケースもあります。例えば後遺障害10級の場合、自賠責基準の慰謝料は190万円、弁護士基準では約550万円ですが、保険会社提示額はその中間かそれ以下(200~300万円台)にとどまることが少なくありません。
裁判基準(弁護士基準)
裁判所が過去の判例をもとに定めた基準で、「赤い本」「青本」と呼ばれる書籍にまとめられています。被害者が弁護士を通じて請求する場合や訴訟になった場合に適用される最も高い基準です。等級ごとの慰謝料相場は自賠責基準のおおよそ2~3倍に上り、例えば後遺障害14級なら約110万円、9級なら約600~700万円、5級で1,400万円前後などとなります。
裁判基準はあくまで目安ですが、実際の示談交渉でも弁護士が介入すればこの基準に近い金額まで増額交渉できることが多いです。もっとも、訴訟でではなく示談交渉の場合は、この裁判基準の金額より一定程度減額することがほとんどです。
慰謝料の具体的な算定方法
自賠責基準では等級ごとに定額なので計算は単純です。
一方、裁判基準では後遺障害慰謝料は一律の計算式というより等級に応じた表に従って請求します。被害者側に過失がある場合はその割合だけ減額(過失相殺)されます。
また、後遺障害慰謝料とは別に入通院慰謝料(ケガの治療期間中の精神的苦痛に対する慰謝料)も発生している場合は、それも加算して総額の賠償金を決定します。
例えば、むち打ちで14級が認定されたケースを考えると、自賠責基準の後遺障害慰謝料は32万円ですが、弁護士基準なら110万円が目安となります。さらに治療期間に応じた入通院慰謝料も別途加わるため、最終的な示談金額は被害者と加害者の過失割合や他の損害項目も含めて総合的に計算されます。以下は簡単な算定例です。
算定例(14級むち打ちの場合)
30歳会社員(年収500万円)が交通事故でむち打ちとなり、症状固定後に後遺障害14級9号が認定されたとします。この場合、裁判基準での後遺障害慰謝料は110万円程度です。
逸失利益は後述の計算式で求めますが、14級の労働能力喪失率5%で5年間の労働能力喪失期間とすると、約500万円×0.05×ライプニッツ係数4.5797=1,144,925円の逸失利益が発生します(法定利率3%の場合)。
したがって後遺障害による慰謝料と逸失利益を合わせ、約2,244,925万円が後遺障害による損害額となります(ここから過失相殺や既払金控除、裁判外での示談交渉であることを踏まえた減額などを経て最終的な賠償額が決まります)。
もちろん収入額や年齢によって逸失利益は増減しますので、これは一例に過ぎませんが、弁護士基準で請求することで自賠責基準(14級では慰謝料32万円+逸失利益数十万円程度)に比べ大幅に増額できることがわかります。
後遺障害による逸失利益の算出方法
逸失利益とは、後遺障害が残ったことにより将来に失われる収入(利益)のことです。事故さえなければ将来得られたはずの収入を補償する趣旨で、後遺障害慰謝料と並ぶ重要な賠償項目になります。逸失利益は次の計算式で算出します。
逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
基礎収入
被害者の事故前の年収を基礎とします。
給与所得者の場合は事故前年度の源泉徴収票等から算出し、家事従事者(主婦)の場合は賃金センサスの女性平均賃金などを基準に置き換えます。無職者でも将来働く可能性があれば平均賃金を基礎収入とすることがあります。一方、高収入の人は実収入ベースで計算します。
労働能力喪失率
後遺障害等級に応じて定められた労働能力の喪失割合です。裁判実務で用いられる一般的な基準では、1級~3級は100%、4級92%、5級79%、6級67%、7級56%、8級45%、9級35%、10級27%、11級20%、12級14%、13級9%、14級5%とされています。例えば14級の場合は労働能力の5%を失ったものと評価し、基礎収入の5%相当が逸失利益として認められる計算になります。
就労可能年数
後遺障害によって労働能力を失う期間、つまり事故後から原則引退時期までの年数です。一般的には被害者が67歳になるまでの年数が採用されます(裁判基準による場合。近年の裁判例では定年を考慮して65歳とすることもありますが、67歳が原則です)。
被害者が高齢の場合は少し特殊で、事故時の年齢と平均余命から合理的な就労年数を算定します。具体的には、67歳までの残年数と平均余命の半分を比較して長い方を就労可能年数とする方法が用いられます。
例えば60歳の方なら、67歳まで残り7年と平均余命の半分(たとえば平均余命20年なら半分の10年)のうち長い10年を就労可能年数とします。若年者の場合は基本的に67歳までフルに計算されます。
ただし、むち打ちなどの場合は、症状が鈍麻することを踏まえ、14級では5年手程度、12級では10年程度とみることがほとんどです。
ライプニッツ係数
将来の収入を一括前払いすることによる利息分を控除するための係数です。簡単に言えば「中間利息控除」のための掛け目で、裁判では法定利率などに基づき定められます。2020年4月の民法改正以降は法定利率3%が適用されるため、それに対応したライプニッツ係数で算定します。
係数は就労可能年数により異なり、年数が長いほど大きな数字になります(例えば就労年数10年の場合は約8.53、20年の場合は約14.88、30年の場合は約19.60)。
以上を当てはめて計算された金額が逸失利益となります。
裁判所はこの算定式による金額をベースに、被害者の実情に応じて増減を判断します。増減要因としては、被害者の年齢・性別・職業・技能などが挙げられます。例えば後遺障害によって現在の職業を続けられなくなる場合や、昇進・昇給の機会が絶たれた場合には、通常の労働能力喪失率以上に収入減少が見込まれるとして期間や率を上積み評価することがあります。
一方で、実際には収入が減っていない場合(後遺障害が残っても同じ職場で同じ給与を得ている等)には、逸失利益が否定されたり労働能力喪失期間を短めに認定されたりすることもあります。
もっとも裁判実務では、形式的には上記算定式で機械的に算出しつつ、事情によって期間を制限するなどして調整するケースが多いです。例えば高齢者や障害の程度が軽微な場合、「就労可能年数の全部ではなく一部の期間のみ労働能力喪失が続く」と判断されることもあります。
しかし基本的には若年~中年層で労働意欲がある場合、67歳までの満額を認めることが一般的です。
なお、専業主婦の後遺障害逸失利益については、家事労働の価値が失われるものとして女性労働者の平均賃金等を基礎収入にみなして算定されます。また子供(学生)の場合も、将来就職して得られたであろう収入を想定して計算するのが通例です。
このように逸失利益の算定は被害者の属性に応じて個別性がありますが、計算の基本は「基礎収入×喪失率×期間×係数」であり、後遺障害等級さえ適切に認定されれば機械的に金額を導けるようになっています。
後遺障害認定の申請手続きと必要書類
後遺障害の等級認定を受けるには、治療先の医師に「後遺障害診断書」(後遺症の状態を詳述した所定の様式)を作成してもらい、これを保険会社経由または自賠責保険会社に直接提出する必要があります。具体的な申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2通りがあります。
事前認定
加害者側の任意保険会社に後遺障害診断書などを提出し、保険会社を通じて自賠責の等級認定手続きを行う方法です。保険会社は被害者への示談金支払い前に後遺障害等級を確認する必要があるため、この事前認定制度を利用します。
被害者にとっては保険会社に書類を渡すだけで手続きが完了する利点がありますが、一方で保険会社任せになるため資料提出が不十分となるリスクがあります。保険会社は必要最低限の書類しか提出しないこともあり、症状が軽視されて不利な認定結果(等級非該当や低い等級)につながるケースがあるので注意が必要です。
もっとも、症状が明らかで等級がほぼ確実な場合は事前認定でも問題ない場合もあります。
被害者請求
被害者自身(または代理人の弁護士)が自賠責保険会社に対して直接後遺障害等級の認定申請を行う方法です。この場合、被害者側で必要書類をすべて揃えて自賠責保険の損害調査事務所に送付しなければなりません。手間はかかりますが、自分で提出書類を精査・追加できるため有利な資料を漏れなく提出できるメリットがあります。
また、被害者請求を行うと自賠責からの保険金(等級に応じた法定金額)を被害者が直接受け取ることが可能で、示談前でも先取りできる利点もあります。デメリットは提出書類収集の負担や専門知識のハードルですが、弁護士に依頼すれば代行してもらえます。
必要書類
被害者請求で提出すべき書類は多岐にわたります。主なものは以下の通りです。
- 自賠責保険金請求書(所定の請求書式)
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターで取得)
- 事故発生状況報告書(事故の状況を被害者が記載)
- 診断書(初診時等の診断書)および後遺障害診断書(症状固定時に医師が作成)
- 診療報酬明細書(治療費の明細。健康保険を使用した場合は健康保険組合等から入手)
- 後遺障害に関する検査結果(レントゲン・MRI画像フィルムや検査報告書など)
- 施術証明書(整骨院等に通院した場合)・通院交通費明細書・休業損害証明書 など必要に応じて
これらを揃えて自賠責保険会社に郵送等で提出すると、損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所で審査が行われます。審査は提出書類の書面審査が基本で、医師の面談や現地調査などは通常行われません。認定結果は「○級○号」または「非該当」といった形で通知され、自賠責保険金が支払われます。
認定までの流れと注意点
後遺障害の等級認定手続は、治療が終了(症状固定)してから速やかに行う必要があります。認定申請が遅れるとその間に症状が悪化・改善したり、必要な証拠が散逸したりするおそれがあるためです。
また、提出する後遺障害診断書の内容が極めて重要です。医師が障害の状態を的確に記載していないと正当な評価が受けられません。必要に応じて主治医に症状の経過や現在の具体的な支障を詳細に伝え、診断書に反映してもらうことが大切です。
認定結果に納得がいかない場合の異議申立て手段は後述しますが、初回申請時に十分な資料を出しておく方が圧倒的に有利です。
異議申し立ての方法と成功事例
自賠責の後遺障害認定に不服がある場合、「異議申立て」という制度で再審査を求めることができます。異議申立ては初回の認定とは別の機関で行われ、各損保会社を統括する自賠責保険・共済紛争処理機構(現在は自賠責保険審査会)が担当します。
この審査会は弁護士・医師・学識経験者からなり、通常の調査事務所より専門的かつ客観的な審査が行われます。異議申立ての手続きは主に書面で行い、被害者は異議申立書とともに新たな証拠資料を提出します。
初回と同じ資料しかない場合、再検討しても結果が覆る可能性は低いため、異議申立てでは「なぜ非該当(または低い等級)と判断されたのか」を分析し、その不足点を補う証拠を揃えることがポイントです。
異議申立ての流れ
まず認定結果通知書に記載された理由を確認します。
例えば「症状が医学的に裏付けられないため非該当」などと書かれていれば、次の異議申立てではその医学的裏付けを示す資料(MRI画像や神経学的検査結果など)を新たに提出する必要があります。
異議申立書に「○年○月○日付認定結果に対し異議を申し立てます。理由:○○」と簡潔に記載し、追加資料を添えて自賠責保険会社に提出します。すると紛争処理機構で再審査が行われ、結果が通知されます。
審査期間は数ヶ月程度ですが、新証拠の収集に時間がかかる場合もあるため、異議申立ての検討は早めに始めることが大切です。
なお、異議申立てには回数制限はありませんが、その都度新たな証拠が求められるため、漫然と何度も申し立てても認められません。十分な材料が揃わないまま異議申立てをするのは避け、可能ならば後遺障害に詳しい弁護士に相談して戦略を立てることをお勧めします。
専門家であれば医学論文や専門医の意見書を用意したり、認定基準に即した法律的主張を展開したりして、認定機関を説得できる資料作成が可能です。
成功事例
異議申立てによって後遺障害等級が上がったケースも存在します。例えば、むち打ち症で症状固定後に自賠責では後遺障害非該当とされた事案で、被害者がMRI検査での頚椎の椎間板ヘルニア所見や非常に強い投薬を受けていたことが分かる資料を新たに提出したところ、異議申立てにより14級9号が認定されたケースがあります。
万一、異議申立てでも納得いく結果が得られない場合、訴訟を提起して裁判所に後遺障害の有無・等級を判断してもらう手段も存在はします。裁判では先述の通り裁判官が独自に後遺障害を認定できますので、保険機関で非該当でも裁判で等級が認められる可能性があります。
もっとも、後遺障害の認定結果が出ている場合は、まずそれが判断の基礎になることも多いため、やはり事前に交渉外認定を受けていることは重要です。
むち打ちについての詳細な解説
むち打ち(頚椎捻挫・挫傷)は、交通事故で首が急激に振られることで生じる軟部組織の損傷で、交通事故の後遺障害として最も多く見られる傷病です。主な症状は首の痛みやこり、肩背部の痛み、頭痛、めまい、腕や指先のしびれなどで、レントゲンでは異常が映らないことも多くあります。
軽症の場合、多くは治療とともに症状が改善しますが、一部のケースでは症状固定後も痛みやしびれ等の神経症状が残存し、後遺障害等級の認定対象となります。
むち打ちで認定される等級:
むち打ち症による後遺症は、その他覚的所見(客観的証拠)の有無と程度により等級が分かれます。自賠責の後遺障害等級では、該当する項目は「局部に神経症状を残すもの」です。具体的には次の2つが代表例です。
14級9号「局部に神経症状を残すもの」
MRIやレントゲンなどで明確な神経圧迫所見はないが、事故後に頑固な痛みやしびれが残っているケースです。他覚所見に乏しいむち打ちの典型例で、一定期間治療しても症状が残存し日常生活に支障がある場合に認定されます。
14級は後遺障害の中で最も軽い等級ですが、それでも「後遺障害がある」と認められた意味は大きく、慰謝料や逸失利益の請求が可能になります。
12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」
画像診断などで明確な神経系の異常所見が確認できる場合のむち打ちです。例えば頚椎の椎間板ヘルニアによる神経根圧迫がMRIで写っており、それに対応した知覚麻痺や筋力低下が残っているようなケースが該当します。
「頑固な」という文言がついており、14級より重い症状であることを示します。他覚的に証明できるむち打ち後遺症がある場合、12級が認定され労働能力喪失率14%として逸失利益も大きく認められます。
なお、むち打ち症状でも、痛みやこり、痺れなどの症状が軽度で日常生活や労働にほとんど影響がないと判断される場合は等級非該当となることもあります。特に治療期間が極端に短かったり、症状の一貫性が乏しかったりすると認定は厳しくなる傾向があります。
むち打ち後遺障害認定のポイント
むち打ちで適正な後遺障害等級を得るには、以下の点に留意する必要があります。
治療期間と経過
明確な根拠はないものの、むち打ちの場合、少なくとも6ヶ月程度は継続して整形外科等で治療を受けることが望ましいとされています。短期間で治療を打ち切ってしまうと「症状固定時に後遺症が残るほどの傷病ではなかった」と判断され、非該当になりやすいです。
医師が治療の必要性を認めており、症状が続く限りは医師の指導どおり治療を継続しましょう。
他覚的所見の有無
可能であればMRI検査等を行い、神経の圧迫や椎間板の変性などの所見を確認しておくことが重要です。明確な異常が写れば12級認定の有力な根拠になります。「他覚的所見が全く無い」と判断されると等級が非該当になるリスクが高まりますので、「所見が無いとは言えない」状態に持っていくことがポイントです。
医師に相談して必要な検査(MRI, 神経伝導速度検査など)を受けておくと良いでしょう。
症状の一貫性・整合性
症状固定までの間、症状が良くなったり悪くなったりといった不自然な経過を辿っていないかも見られます。事故直後から一貫して首・腰の痛みがあり、治療を続けても完全には消失しなかったというストーリーが整合的であれば、後遺障害と認められやすいです。
途中で長期間通院を中断していたり、事故からしばらく経って初めて痛みを訴え出たりすると、因果関係や症状の信用性に疑義が生じます。
通院頻度・治療内容
適切な頻度で通院していることも重要です。むち打ちの場合、症状固定まで週2~3回程度は継続して通院するのが望ましいと言われています。あまりに通院間隔が空いていると「その期間はさほど痛くなかったのでは」と推測されてしまいます。
また、病院(整形外科)での治療と並行して整骨院・接骨院に通う場合は、必ず病院の医師に報告して指示を仰いだ上、病院での経過観察も定期的に受けておくべきです。整骨院の施術証明書だけでは医学的裏付け資料とみなされないため、必ず病院での診察記録を途切れさせないようにしましょう。
なお、一般論でいえば、病院だけの通院をするのが最も望ましいと言われています。
事故態様の重大性
事故の衝撃の大きさも間接的に考慮されます。追突事故でもごく軽いバンパー接触程度の物損軽微な事故だと、重い後遺症が残るとは考えにくいため認定に慎重になります。逆に車両が大破するような大事故であれば、むち打ち症状にも信憑性が増します。
認定審査では事故の資料(実況見分調書や車の修理費用、損傷写真など)も参考資料となり得ます。可能であれば車両の損傷写真や修理見積書を提出し、事故の規模が小さくないことを示すと良いでしょう。
以上を踏まえ、むち打ちによる後遺障害が非該当と判定されないためには、早期から適切な検査・治療を受け、症状経過と証拠を整えておくことが肝要です。
どうしても他覚所見が得られない場合でも、診断書に神経学的検査所見(腱反射の減弱や知覚鈍麻の分節など)を詳しく記載してもらう、痛みの部位や程度を本人が記録しておくなどして、症状の存在を客観的に示す工夫が必要です。
また、保険会社が途中で治療費打ち切りを打診してきても、症状が残っているうちは健康保険を使ってでも治療を継続し、症状固定のタイミングは医師と十分相談して決めるようにしましょう。不十分な状態で症状固定としてしまうと、その後の等級認定で適正な評価が得られなくなってしまいます。
まとめ
以上、後遺障害の基礎から等級別の内容、損害額算定、手続き面、異議申立て、そして頻発するむち打ち症について整理しました。適切な後遺障害等級の認定を受けることは、最終的な賠償額に直結する非常に重要なプロセスです。
事故直後から症状固定後まで一貫して注意を払い、必要に応じて弁護士のサポートを受けながら進めることで、正当な補償を受けられる可能性が高まります。
当事務所では、大分県宇佐市だけでなく、中津市、豊後高田市、杵築市など周辺のエリアから、交通事故に関するご相談を多数頂いております。交通事故に関する初回相談は無料(弁護士費用特約がある場合は実質無料)となりますので、ご不安がある方は、ひとりで悩まずにご相談頂ければと存じます。