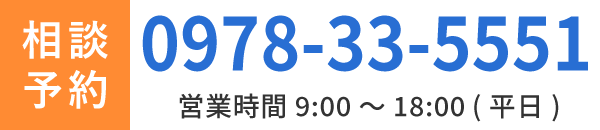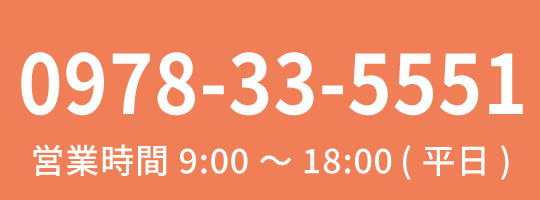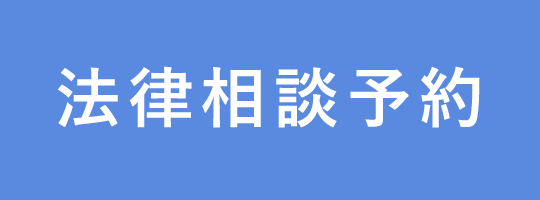このページでは、交通事故の民事事件で争点となることも多い、「休業損害」について説明しています。
このページの目次
1. 休業損害の定義と計算方法
休業損害の定義
交通事故による怪我で働けず減った収入の補償のことです。
簡単に言うと、「交通事故の治療のため仕事を休んだことで得られなかった収入」を指し、加害者側の保険(自賠責保険や任意保険)から支払われる損害賠償項目の一つです。
実際に収入がある人だけでなく、専業主婦(主夫)でも、交通事故で家事に支障が出た場合には経済的損失があったとみなし請求が可能です。また、学生であっても、交通事故によって就職するはずだった日に稼働することができなければ、請求ができることがあります。
基本的な算出方法
原則として「1日あたりの収入(基礎収入) × 休業日数」で計算します。例えば事故前の月収や日給を基に日額を出し、仕事を休んだ日数を掛け合わせる形です。
とりわけ、休業日数には有給休暇を使った日も含まれます(有給を消化せざるを得なかったこと自体が損失と考えられるためです)。ただし実際の収入額や就労状況に応じて調整が入ることがあり、日額は必ずしも単純な給与日割りとは限りません。
また、交通事故の損害賠償には自賠責基準・任意保険基準・弁護士(裁判)基準と呼ばれる算定基準がありますが、休業損害についても基準ごとに日額算定に差があります。
自賠責基準では一律日額6,100円×休業日数で計算され、これが基本上限額となります(※令和2年4月以降の事故。以前は日額5,700円が基準でした)。もっとも、被害者の収入がそれ以上である証拠を提出すれば、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2にしたがって上限に引き上られることがあります。
一方、任意保険基準は保険会社により多少異なるものの、自賠責基準と同程度かそれを少し上回る水準で計算されるのが一般的です。弁護士基準(裁判基準)では被害者の実収入に基づき算出するため最も高額になりやすく、基本的に事故前の収入実績から日額を計算します。
職業別の算出方法の違い
休業損害の計算方法は被害者の職業や収入形態によって細かな違いがあります。
会社員(給与所得者)やアルバイトの場合
交通事故前の給与額を基に日額を算定します。
給与が毎月固定であればその額を基準にしますし、月収変動がある場合は事故前数ヶ月(通常3ヶ月)の総支給額を平均して日額を出す方法が用いられます。
例えば直近3ヶ月の給与合計が75万円なら、弁護士基準では実際に働いた日数(稼働日数)で割るため日額12,500円になるということになります。有給を使った場合や交通事故によりボーナスが減った・残業代等が減少した場合も、交通事故との因果関係が認められればその分も休業損害に含めて請求できます。
アルバイトやパートも基本的な考え方は同じで、交通事故前の収入(日給や時給ベースの収入)から日額を計算し休業日数を乗じます。
自営業者・個人事業主の場合
交通事故による休業で売上や所得が減った場合に請求できますが、収入が不定期だったり証明が難しい点で会社員よりハードルが高いです。算定方法は、前年の確定申告所得を基に日額を算出するのが一般的です。
具体的には「事故前年の確定申告書に記載された所得額 ÷ 365日」で日額を出し、休業日数を掛ける方法などがあります。
さらに、自営業者の場合は休業中も支払い続けた固定経費(店舗家賃や従業員給料、保険料など)があれば、それも損失として日額算定時に加算できることがあります。例えば売上が途絶えていなくても、休業中に必要かつやむを得ない固定費支出があればそれも損害と認められるのが裁判基準です。
一方で、交通事故後も従業員などの働きで収入減が生じなかった場合には「現実の減収がない」ため休業損害は認められないことに注意が必要です。収入証明としては確定申告書控えが重要です。申告をしていなかったり過少申告の場合、立証のハードルは上がりますが、通帳や帳簿類で収入を立証したり、裁判では過去の賃金センサス(厚労省の平均賃金統計)を基に基礎収入を推定して認定する例もあります。
実際の裁判例でも、申告上の所得が不自然に低い場合に証拠から実収入を算出し直したり、平均賃金を適用して基礎収入を定め直したケースがあります。
主婦(主夫)・家事従事者の場合
本来収入を得ていなくても、交通事故で家事労働ができなかった期間については「経済的価値のある労働を休んだ」とみなされ、主婦休業損害(主婦休損)として請求できます。
裁判実務では、専業主婦(夫)の基礎収入は厚生労働省の「賃金センサス」による女性労働者の平均賃金で代替されるのが一般的です。例えば令和3年の女性全年齢平均賃金から算出される1日あたり金額は約10,804円と報告されています。
したがって、専業主婦が交通事故で家事不能だった日数については「日額×休業日数」の休業損害を受け取れる計算になります(※保険会社は自賠責基準の日額6,100円で示談提示してくることもありますが、弁護士交渉により平均賃金ベースの日額に引き上げることが可能です)。
もっとも、休業日数については争点となることが多く、治療期間全てについて100%の休業が認められることはあまりありません。実通院日数を基礎にパーセンテージで判断したり、最初の1か月目100%、2か月目50%、3か月目25%などというように、時期によって休業の度合いを変化させる場合もあります。
兼業主婦の場合は実収入と家事労働の二面がありますが、実収入が先述の平均賃金より低い場合は専業主婦と同様に平均賃金を基礎として計算し、実収入が平均賃金より高い場合はその人の収入を基に計算する方が有利なので実収入ベースで算出することがあります。
なお、事故によって家事ができず家政婦等を雇った場合、その実費も必要性が証明できれば休業損害として認められることがありますが、主婦休損との二重取りはできず、必ずしも認められるとは限りません。
上記以外のケース
学生や就職内定者などは基本的に事故当時収入がないため通常は休業損害はありません。ただし、アルバイト収入がある学生はアルバイト分については会社員と同様に請求できますし、就職内定者が事故で入社時期が遅れ収入に影響が出た場合などは、その期間の減収を請求できる可能性があります。
また、会社役員の場合は役員報酬のうち労務提供の対価部分のみが休業損害の対象です(出勤しなくても得られる利益配当的な部分は対象外)。
2. 休業損害請求の手続き
請求の流れ
休業損害を受け取るには、まず交通事故の加害者側保険会社に対し必要書類を提出して請求します。保険会社は提出資料を基に休業損害額を算定し、他の損害項目と合わせて示談金額を提示してきます。被害者はその金額を確認し、必要に応じて増額交渉を行います。
示談がまとまれば、示談書の締結後に休業損害分も含めて賠償金が支払われます。
必要書類
被害者が「交通事故の怪我で実際に仕事を休んだこと」と「それによって収入が減少したこと」を立証する書類を用意する必要があります。職業や状況に応じて求められる主な書類は以下の通りです。
共通書類
必ず必要となるものとして医療記録(医師の診断書または診療報酬明細書)があります。これは、怪我の内容や治療期間、働けなかった期間を示す基本書類です。休業指示や就労制限の有無も明記してもらうと有利です。
また、保険会社所定の休業損害証明書(書式)も共通して重要です。会社員やアルバイトであれば勤務先に記入してもらい、休業した日数や期間、支給された給与の有無などを証明するものです。後述の給与所得者用書類に含まれますが、自営業者等でも保険会社から様式を入手して提出すると手続きがスムーズになります。
給与所得者(会社員・公務員・アルバイト等)
休業損害証明書(勤務先に作成依頼)および事故前年分の源泉徴収票(または直近の給与明細や所得証明)が必要です。
休業損害証明書には、事故発生日以降の出勤状況(欠勤・有給取得・早退遅刻等)が日付ごとに記載され、これに基づき休業日数と減収額を算定します。源泉徴収票は事故前の収入水準を確認する資料です。会社員で副業がある場合は、副業先それぞれから証明書を出してもらい全収入について減収を立証します。
自営業者・個人事業主
確定申告書の控え(事故前年分)が必要です。事業所得者はこれが収入証明の基本となります。必要に応じて帳簿、売上台帳、預金通帳の写し等も提出します。
また、自営業者用の休業損害証明書(事業内容や交通事故後の営業状況を報告する書類)を保険会社から取り寄せて提出することもあります。会社の代表者で役員報酬を得ている場合も基本は自営業者と同様ですが、役員報酬の内訳が分かる決算書類(損益計算書など)も併せて求められます。
専業主婦(主夫)・家事従事者
住民票(世帯全員の記載があるもの)を求められることがあります。被害者が家庭で家事労働を担っている立場であることを示すため、同一世帯の家族構成が分かる住民票をもって証明します。兼業主婦の場合は上記に加えて自身の収入関係書類(源泉徴収票や休業損害証明書)も必要です。
無職・求職中だった人
求職活動をしていたことを証する書面や内定通知書が必要となることがあります。交通事故当時職に就いていなくても、交通事故前後に就職活動中で具体的な内定があった場合などは、内定取消しや就労開始延期による収入逸失として休業損害が認められる可能性があります。そのための証拠として、ハローワークの求職受付票や面接日時の記録、企業からの内定通知などを提出します。
これらの書類提出時には、記載漏れや誤記に注意しましょう。特に勤務先に作成してもらう休業損害証明書では、事故後に取得した有給休暇の日も含め漏れなく休業日として記載されているか、欠勤・遅刻・早退などが正しく反映されているかを確認する必要があります。
仮に記載が不十分だと、本来請求できるはずの日数が認められないおそれがあります。不明点があれば勤務先に再確認・訂正してもらうことが大切です。
保険会社との交渉や示談のポイント
休業損害の支払いについては、保険会社から提示された金額や日数が妥当かどうかを被害者側でチェックする必要があります。以下に主なポイントを挙げます。
休業日数の認定
保険会社は原則、医師の意見や通院実績をもとに「この期間は働けなかった」と認められる日数を計算します。通常、通院や入院した日が中心ですが、複数箇所の骨折などによって全く外出ができない場合など、怪我の程度によっては通院日以外の安静療養日も含まれることがあります。
ケースによっては通院日数しか認めないという対応もあり得ますが、医師の指示で自宅療養が必要だった日については診断書にその旨記載がある場合に、これを主張するなどします。
逆に、軽傷なのに長期間休んだような場合、「その期間本当に働けなかったのか」を疑われ減額が争点となることもあります。適正な休業日数を主張するには、医師に就労制限の期間を明確に示してもらうことが重要です。
保険会社の提示額の基準
保険会社は自賠責基準(6,100円/日)をベースに低めに計算して提示してくる傾向があります。そして仮に、被害者の収入がそれ以上であっても、自主的に証明しない限り基準額しか支払われないということがあります。
提示額が自分の計算と大きく異なる場合は、提出書類が十分か確認するにようにししましょう。また、必要であれば源泉徴収票や確定申告書を再提出したり、追加資料を保険会社に問い合わせることもあります。例えば、ボーナス減少分や副収入の減少分など、見落とされがちな損失も含めて主張すると良いでしょう。
保険会社からの打ち切り・拒否
治療が長引くと、保険会社が途中で「もう働けるはず」「症状固定したはず」などとして休業損害の支払い打ち切りを通告してくるケースがあります。
しかし、医師がまだ治療の継続が必要と判断しているのに保険会社判断で打ち切られそうな場合は要注意です。こうした主張に対しては、医療照会や面談において、主治医の意見書や医療記録から、「まだ就労困難である」ことを証明する対応がありえます。
なお、症状固定(治療の打ち止め)時期をめぐる争いは休業損害に限らず起こり得ますが、基本的には医師の判断が尊重されます。したがって、治療中は医師と相談のうえ無理に仕事復帰せず、必要な治療を続けている事実をきちんと記録・報告しましょう。
示談交渉での留意点
休業損害は被害者にとって生活に直結する重要な損害です。保険会社との話し合いで金額に納得がいかない場合、感情的にならず客観的資料に基づき主張することが大切です。必要があれば弁護士に相談・依頼するのも有効です。
弁護士は裁判所基準で適正額を算定し直し、保険会社に増額交渉します。特に自営業者や主婦休損など証明が難しいケースでは、弁護士の助言により適切な書類を揃えて主張を裏付けることができます。
示談交渉全般のポイントとして、退職や副業といった特殊事情で因果関係を疑われそうな場合はあらかじめ根拠資料や説明を準備しておくと良いでしょう。
3. 休業損害に関する判例や基準
認定の基準(原則)
裁判所は休業損害について、「交通事故が原因で収入がどれだけ減ったか」という「現実の損害額」を重視します。
原則として、交通事故発生から症状固定日までの現実に休業した期間の収入減が賠償の対象です。その額が明確に算出できる場合(例えば休業中無給になった給与額がはっきりしている場合)はその実額が認められます。一方、正確な減収額が分からない場合(自営業でどれだけ売上が落ちたか不明瞭な場合など)は、前述した基礎収入(日額)×休業日数で推計します。
また、休業日数についても、基本は実際に仕事を休んだ日数ですが、怪我の程度や仕事内容から「本当は働けたはず」と認定される場合には、たとえ休んでいてもその分の損害賠償が認められないことがあります。
例えば、軽傷にもかかわらず過度に長期間休職したような場合や、医師の意見に反して自己判断で休業を延長したようなケースでは、裁判所が休業の必要性を吟味し、一部期間の休業損害を否認・減額する可能性があります。
逆に言えば、休業の必要性が医学的・客観的に裏付けられる限り、その期間の減収は全額が損害として認められることが多いです。
症状固定後の休業損害
休業損害が認められるのは原則として症状固定日までです。
症状固定とは、治療してもこれ以上良くならないと医師が判断した時点で、以後は治療継続による改善が見込めないため、法律上はその時点で治療が一区切りとなります。
したがって、症状固定後に仕事を休んでも「治療のために休業した」とは言えなくなるため、通常は休業損害の対象外です。症状固定後に後遺障害が残り、労働能力が落ちた場合は、将来の減収は「逸失利益」として別途賠償を受ける仕組みになります。逸失利益を請求するには後遺障害等級の認定が必要で、その等級に応じた労働能力喪失率と就労可能年数に基づき、一時金として将来分を受け取る形です。
ただし例外的に、症状固定後であっても定期的なリハビリ治療や手術のため勤務を休まざるを得ない場合には、その都度の休業について休業損害が認められた裁判例も多くはないものの存在します。
このように、症状固定の扱いは重要な争点で、症状固定日を早めに設定できればその後の治療費・休業損害を払わなくて済むため、保険会社は症状固定時期を繰り上げようと主張しがちですが、裁判所は原則として主治医が認定した症状固定日を採用しています。被害者側としては、症状固定に異議を唱えられないよう適切な治療経過を踏み、医師と相談しながら時期を見極めることが大切です。
まとめ
以上、交通事故における休業損害の基本知識と手続きについて、整理しました。
適正な休業損害を確保するには、早い段階から証拠資料を整備し、必要に応じて弁護士の助言を得ることが重要です。被害者として自分の主張できることを正しく理解し、適切な補償を受けられるよう対応しましょう。