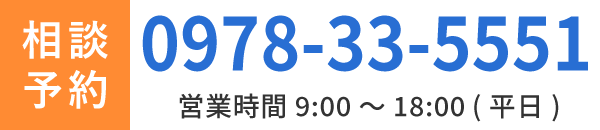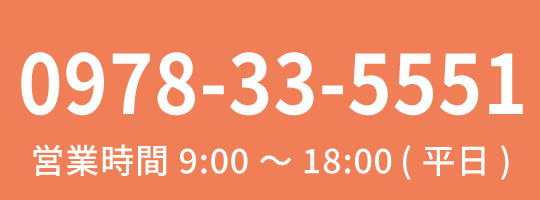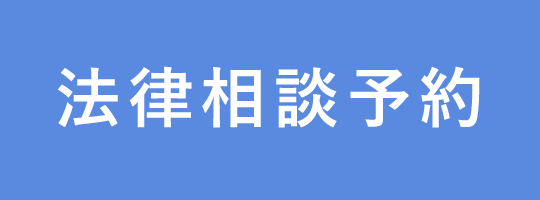このページの目次
はじめに
遺産相続において「特定の相続人には遺留分を渡したくない」と考えるケースがあります。
たとえば、親の介護や家業を献身的に支えてきた長女に全財産を相続させ、長年音信不通だった長男には遺留分すら渡したくない、といった状況です。しかし遺留分は法律で保障された権利であり、基本的には遺言などで排除することはできません。本ページでは、被相続人(遺言者)の立場と、遺産を多く取得した相続人の立場の双方から、遺留分を渡さなくてもいい方法と、どうしても支払う場合にできるだけ減額する方法を詳しく解説します。法的根拠や判例にも触れつつ、具体例を交えて遺留分対策のポイントを説明します。
遺留分とは何か
遺留分(いりゅうぶん)とは、法律上 「兄弟姉妹を除く法定相続人に保障された最低限の相続割合」 を指します。
遺言によっても奪うことのできない相続人の取り分であり、被相続人が生前贈与や遺贈で他者に財産を譲っていても、一定の相続人はその一部を取り戻す権利を持ちます(民法1042条~1046条)。遺留分制度は、残された家族の生活保障のために設けられたものです。
遺留分権利者と割合
遺留分を請求できるのは被相続人の配偶者・子(直系卑属)・父母など直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分権が認められません(民法1042条1項)。遺留分の割合は相続人の構成によって異なります。
民法1042条によれば:
- 直系尊属のみが相続人の場合: 遺産全体の1/3が遺留分となります。たとえば被相続人に配偶者や子がおらず、親のみが相続人の場合、親の遺留分は遺産額の1/3です。
- 上記以外の場合(配偶者や子が相続人の場合): 遺産全体の1/2が遺留分となります。配偶者・子がいれば総体的遺留分は原則1/2となり、各人の遺留分は法定相続分に応じ按分されます。たとえば「配偶者と子1人」が相続人なら、遺留分は配偶者1/4・子1/4(合計で遺産の1/2)です。子2人と配偶者なら配偶者1/4・各子1/8ずつ(合計1/2)となります。
以上のように、遺留分とは相続人に最低限保障された取り分であり、遺言で「遺産を一切渡さない」と指定されていても、遺留分権利者である限り請求する権利があります。ただし、後述する特別な手段を講じた場合や、請求する側に落ち度がある場合には、遺留分を渡さなくてもいい場合もありえます。
遺留分を完全に渡さない方法
遺留分は原則として必ず保障される権利ですが、「遺留分を渡したくない」という強い事情がある場合に、法律上考えられる手段が二つあります。それが相続人の廃除と遺留分の生前放棄です。どちらも条件が厳しく、簡単には認められませんが、要件を満たせば遺留分を渡さずに済む方法となりえます。以下、それぞれの方法について要件や手続、判例を解説します。
相続人の廃除(民法892条)
廃除とは
廃除(はいじょ)とは、特定の推定相続人について、その者の相続権および遺留分権を剥奪する制度です。被相続人が生前または遺言で家庭裁判所に請求し、認められればその相続人は相続から除外されます(民法892条)。廃除された者は初めから相続人でなかったものとみなされるため、その人に対しては遺留分を一切渡さなくてよくなります。
廃除が認められる要件
民法892条は廃除事由として、被相続人に対する次のような行為を定めています。
- 被相続人に対する虐待(肉体的・精神的な酷い扱い)。
- 被相続人に対する重大な侮辱(著しく無礼で名誉を傷つける行為)。
- その他、被相続人に対する著しい非行(上記に準じる重大な背信行為)。
これらは単なる不仲やわずかな非行では足りず、「社会通念上、推定相続人の遺留分を否定することが正当であると評価できる程度に重大なもの」である必要があります。例えば被相続人を暴行・傷害し、深刻な精神的苦痛を与えたような場合は該当しえますが、些細な暴力や侮辱では認められません。
廃除の手続き
廃除するには被相続人が家庭裁判所に廃除審判を申し立てる必要があります。生前に手続きするほか、遺言書に「○○を廃除する」旨を記載しておけば、遺言執行者が代わりに家庭裁判所へ申立てを行うこともできます(民法893条)。審判で廃除が認められれば、その相続人は相続人の資格を失い、遺留分も請求できなくなります。逆に審判が認められなければ廃除は不成立で、遺留分を請求される可能性が残ります。
廃除の成功例と判例: 廃除が認められるのは極めて例外的ですが、過去の裁判例では以下のようなケースで廃除が認められています。
- 被相続人の財産を無断で自分名義に書き換えるなどの悪質行為: 被相続人である父の死期が近いと知り、父の預貯金等を父の意思に反して自分や妻子名義に変更するなどして父に精神的苦痛を与えた息子について、家庭裁判所は「相続的協同関係を破壊する著しい非行」に該当すると判断し、廃除を認めました(熊本家裁昭和54年3月29日審判)。息子は相続人から除外され、結果として父の遺留分を一切受け取れなくなりました。
- 被相続人への暴力・虐待が長期にわたり反省も皆無: 親に対する長年の暴力や虐待行為について、他のきょうだいからの度重なる忠告にも従わず反省もない長男に対し、裁判所が廃除を認めた例があります。このように、親族間の修復不能なほどの深刻な揉め事がある場合には廃除が成立しうるのです。
一方で廃除が認められなかった判例もあります。例えば、被相続人である妻が、生前夫による経済的・精神的な圧迫を理由に夫の廃除を求めたケースでは、夫婦間に確執はあったものの約5年間の間の出来事に過ぎず、夫が遺産形成に貢献した事情も考慮すると「遺留分を否定するほど重大な非行とは言えない」として、最高裁が廃除不許可の判断を示しました(最高裁令和3年3月25日判決)。このように、裁判所は遺留分剥奪の是非を慎重に判断します。
廃除の効果
廃除が確定すると、その相続人は初めから相続人でなかったものとみなされ(民法891条ただし書)、当然に遺留分権も失います。また、廃除された人に直系卑属(子や孫)がいる場合、代襲相続も認められません(民法893条)。つまり廃除された人の子が代わりに遺留分を請求することもできなくなります。廃除は遺留分を渡したくない場合の究極の方法ですが、立証が難しく、現実にはハードルが非常に高いと言えます。万一廃除事由に該当するほどの事情がある場合は、証拠を揃えた上で専門家に相談するとよいでしょう。
遺留分の生前放棄(民法1043条)
遺留分の生前放棄とは
もう一つの遺留分を渡さない方法が、相続人に遺留分を事前に放棄させることです。これは推定相続人が自ら将来の遺留分権を放棄する制度で、家庭裁判所の許可を得て行います(民法1043条1項)。
被相続人が「遺留分を放棄してほしい」場合、推定相続人本人が生前に申立てをし、裁判所の許可審判を経れば、遺留分侵害額請求をする権利自体が消滅します。遺留分の生前放棄が許可されれば、その相続人には遺留分を渡さなくて済むことになります。
遺留分放棄の手続き
遺留分の放棄は、推定相続人が被相続人の存命中に家庭裁判所へ申立てを行い、「遺留分を放棄する事由があること」の許可を得る必要があります。申立てに際しては、放棄を望む理由を明らかにし、本人の真意に基づくことを示す必要があります。家庭裁判所は、遺留分放棄が本人の自由な意思によるものであり、かつその放棄によって著しく不当な結果とならないかを審査します。許可が下りればその者は将来にわたり遺留分請求権を失います(民法1043条2項)。
許可が下りるケースと裁判例
遺留分放棄の許可基準は明文化されていませんが、実務上は以下のような事情があると認められやすいと言われます。
- 相続人が被相続人から十分な生前贈与や扶養を受けており、将来の遺留分を放棄しても生活に支障がない場合。
- 被相続人と相続人との関係が希薄で、相続争いを避けるため互いに遺留分放棄に合意している場合。
- 放棄する相続人自身が財産を望んでおらず、特定の相続人に全財産を譲ることに納得している場合。
例えば、長年疎遠だった実父の財産について、実父が自分以外の者に全財産を譲りたいと望んでいるケースで、子が「相続に関わりたくない」と感じているような場合があります。実際に、家庭裁判所が一度は許可しなかった放棄申請を、東京高裁が許可した例(東京高裁平成15年7月2日決定)があります。
この事案では、父と長年交流のなかった子が遺留分放棄を申請し、原審(水戸家裁)は「放棄の代償を何も得ていない」こと等を理由に不許可としました。しかし、高裁は「放棄を許可しても遺留分制度の趣旨に反する不当な結果とならない」ことを認め、子の遺留分放棄を許可しています。このように、事情次第では生前放棄が認められることもあるのです。
一方、遺留分放棄の失敗例として多いのは、家庭裁判所の許可を経ずに私的な合意だけで放棄させようとするケースです。例えば被相続人が、生前に推定相続人へ「遺留分は請求しません」という念書を書かせても、家庭裁判所の許可がなければ法的効力はありません。
なお実際の裁判例で、遺産分割の裁判上の和解で「遺留分を今後請求しない」旨を約していたにもかかわらず、家庭裁判所の許可がないまま相続発生後に遺留分請求された事案で、裁判所が「許可なき放棄合意は効力がないが、その後の請求は信義則に反する」として請求を認めなかった例があります(東京地裁平成11年8月27日判決)。このケースでは結果的に遺留分は支払われませんでしたが、極めて例外的な判断です。基本的には許可のない事前放棄は無効であり、推定相続人が放棄に合意していても後から請求されてしまうリスクが高いので注意しましょう。
遺留分放棄の注意点
遺留分の生前放棄は一旦許可されると原則撤回できません。ただし、民法上は「家庭裁判所は職権で放棄許可の審判を取り消せる」旨の規定があり(家事事件手続法78条)、放棄許可後に事情が著しく変化した場合に取り消しが認められた例もあります。
例えば、放棄した後に被相続人との関係が改善し著しい扶養を受けるようになった場合などが考えられます。ただ、このような取消しは稀であり、基本的には一度放棄すれば覆らないと考えることが多いです。したがって、遺留分放棄を依頼する側(被相続人)は、放棄の代償として何らかの見返り(生前贈与や金銭等)を用意することも検討することになるでしょう。推定相続人に十分に納得してもらい、自発的な申立てを促すことが重要と言えます。
遺留分を減額する方法
上記の廃除や生前放棄はハードルが高く、「完全に遺留分を渡さない」ことができるケースは限られます。そこで現実的には、遺留分を請求されても渡す額をできるだけ減らす対策を講じることになります。被相続人が生前にできる生前対策と、相続開始後に相続人ができる防御策に分けて説明します。
生前に遺留分額を減らす対策
生前贈与の活用
被相続人が生前に財産を移転しておくことで、死亡時点の遺産額を減らし、結果として遺留分額を減らす方法です。遺留分算定の基礎財産には、原則として「相続開始時の財産+一定期間内の生前贈与財産」が含まれますが、法律上計算に入らない贈与もあります(民法1044条)。
具体的には:
- 相続人以外への贈与: 相続開始前1年以内にした贈与が遺留分算定の対象です。逆に言えば、死亡の1年以上前に第三者へ行った贈与は原則として遺留分計算に参入されません。ただし、被相続人と受贈者が遺留分権利者に損害を加える目的で贈与した場合は1年より前でも含まれるので注意が必要です(民法1044条1項但書)。
- 相続人への贈与: 相続人(子や配偶者など)に対する贈与については、相続開始前の10年間にしたものが遺留分算定の対象となります。つまり、10年以上前に子や配偶者へ与えた財産は、遺留分の計算に入らない可能性があります。たとえば事業承継の場合、後継者となる子に十分な株式や財産を11年以上前から計画的に贈与しておけば、死亡時の遺産額を抑えられ、他の相続人の遺留分額も相対的に減らせます。なお、相続人への贈与でも結婚や生計の資本としての贈与は除外される場合があります(民法1044条3項但書)。
以上をまとめると、「早めの生前贈与」が遺留分対策として有効です。ただし、相続人に十分な財産を贈与しすぎると、それ自体が「特別受益」として持戻し計算の対象になり遺留分に影響する点にも注意が必要です。また、生前贈与には贈与税の問題もあるため、税務面も含めた計画が大切です。
生命保険の活用
財産を現金で持っていると遺産に含まれますが、生命保険金は受取人固有の財産と扱われ、遺産そのものではありません。そこで、遺留分を渡したくない相手がいる場合、資産を預貯金ではなく生命保険に変えておき、指定受取人を渡したい人にしておく方法があります。例えば預金1,000万円を死亡保険金1,000万円に換えて子Aを受取人にしておけば、子B(遺留分権利者)はその保険金に直接は手を付けられません。もっとも、保険金も「みなし相続財産」として遺留分算定の考慮要素にはなり得るため、過度に偏った保険契約は無効のリスクがあります。保険金活用は遺留分対策として一定の効果がありますが、バランスに配慮する必要があります。
家族信託の利用
近年注目の家族信託(民事信託)も遺留分対策として語られることがあります。家族信託では、財産の名義を受託者に移し、受益者のために管理運用します。被相続人(委託者)が亡くなっても、信託契約に従って財産は受託者や次の受益者へ引き継がれ、遺産分割の対象になりにくい特徴があります。「信託を使えば遺留分を請求されないのでは?」と期待する向きもありますが、実際には注意が必要です。
信託財産そのものは遺産ではありませんが、信託受益権(受益者が有する権利)は遺留分算定の対象に含まれる可能性が高いとされています。裁判例でも、遺留分を潜脱する目的で設計された信託契約の一部を無効と判断したケースがあります。東京地裁平成30年9月12日判決では、二男に家産を集中承継させるため母の遺留分を無視した受益者連続型信託契約の条項が「公序良俗違反」で無効とされました。つまり、信託を用いて一方的に遺留分権利者の取り分を奪おうとすれば、裁判で否認されるリスクがあるのです。
もっとも、家族信託自体は財産管理や認知症対策に有効な手法であり、信託を活用しつつ遺留分請求に備えることも考えられます。例えば、信託で事業承継をしながら、遺留分請求された場合に備えて予め現金や保険を用意しておく、といった複合的対策です。信託は万能ではありませんが、他の対策と組み合わせることで遺留分問題に対応できる可能性があります。
遺留分侵害額請求への防御策(相続開始後)
相続開始後、遺留分権利者から遺留分侵害額請求(旧・遺留分減殺請求)を受けてしまった場合、受遺者や多く相続した側の相続人は、できる限り支払額を減らすか、請求を退けるための対応を検討します。以下に主な防御策を挙げます。
遺産評価を争い、遺留分額自体を減らす
遺留分額は遺産の評価額によって決まります。遺産に不動産や非上場株式など評価が難しい財産がある場合、評価額を低く見積もる根拠を示すことで遺留分額を抑えられる可能性があります。例えば不動産について、相手方が高い評価額を主張してきたら、自分側は別の不動産鑑定評価書を用意して低額を主張する、といった戦略です。また、債務がある場合は遺産から債務を控除できますから、被相続人の負債を見落とさず計上することも重要です。
特別受益や寄与分を主張する
請求者が過去に被相続人から生前贈与(特別受益)を受けていた場合、その分は遺留分算定上すでに取り分を得ていることになります。また、自分(受遺者側)が被相続人の財産形成に特別の寄与をしていた場合は、寄与分減殺の主張で遺留分額を調整できる可能性があります。こうした主張で実質的な不公平の是正を図り、支払う遺留分額を減らすことが考えられます。
権利濫用・信義則違反の抗弁
きわめて例外的ですが、遺留分権利者による請求自体が権利濫用または信義則違反と認められる場合、請求が斥けられることがあります。判例上、以下のような特殊な事情でこの抗弁が成功した例があります。
- 長年にわたり被相続人を介護・扶養した相続人に全財産を譲るとの合意が家族間でなされていたケース: 他の相続人もその趣旨に同意し、被相続人も遺言で介護者に全遺産を相続させたにもかかわらず、一部の相続人が後から遺留分を主張した事案で、「遺留分減殺請求権の行使は信義誠実の原則に反する」として請求が棄却されました(東京高裁平成4年2月24日判決)。約21年間母親を献身介護した娘に全財産を譲るという兄弟間の了解を反故にした兄弟の請求が、権利の濫用と見なされた例です。
- 相続人同士の訴訟で遺留分を請求しない和解をしていたケース: 前述のとおり、裁判上の和解で遺留分放棄を約束しながら許可を得ずに遺留分請求が行われた事案で、「請求は著しく信義に反する」として遺留分請求が認められなかった例があります(東京地裁平成11年8月27日判決)。裁判所は形式的には放棄が無効でも、和解成立までの経緯から見て後日の請求は許されないと判断しました。
これらはいずれも特殊な事例であり、簡単に認められるものではありません。しかし、請求者に極端に非難すべき事情がある場合や、当初の約束を翻して遺留分を要求してきたような場合には、一応権利濫用の抗弁を検討する余地があります。
調停での減額交渉
遺留分請求は、いきなり訴訟に入る前に家庭裁判所での調停手続きが利用されるのが原則です。調停の場で、受遺者側と請求者側が話し合い、一定の減額合意を図ることも多く見られます。たとえば本来の遺留分満額を請求されていても、「一括でなく分割払いにする代わりに少し減額して和解する」「不動産を代物弁済に充て評価額を調整する」などの妥協案を提示し、調停成立を目指す方法です。裁判になれば双方コストや時間がかかるため、調停での早期解決を図ること自体が結果的に遺留分減額につながることもあります。
時効を主張する
遺留分侵害額請求には時効・除斥期間があります。相続開始および侵害を知ってから1年、または相続開始から10年で権利は消滅します(民法1048条)。請求者がこの期間を過ぎて請求してきた場合、時効消滅を主張して支払いを免れることができます。実際、被相続人が亡くなった後に遺留分権利者が長期間請求せず放置していた場合、消滅時効で請求を退けた例もあります。相手が権利を行使できる期間を徒過していないかもチェックポイントです。もっとも、相続開始を知らなかった場合は起算が遅れることもあるため、確実な策とは言えません。
具体例を交えた解説
最後に、遺留分を渡したくないケースの具体例をいくつか紹介しながら、これまで述べた対策の実際をイメージします。
(ケース1)一般家庭における遺留分対策
Aさんには長男Bさんと長女Cさんがいます。Aさんは高齢となり、同居するCさんが献身的に介護をしてくれましたが、Bさんとは何年も疎遠で連絡もありません。このためAさんは「遺産は全て長女Cに相続させ、Bには渡さなくてもいい方法を取りたい」と考えました。Aさんが検討した具体策は次の通りです。
- 遺言書の活用: Aさんは公正証書遺言で「全財産を長女Cに相続させる」と明記しました。加えて付言事項に「長男Bには長年音信不通で扶養も受けていないため、一切財産を渡さない」旨を記載し、Bさんが遺留分請求しないよう強く求めました(付言事項に法的拘束力はありませんが、意思表示として残しました)。
- 生前贈与・保険: 自宅不動産はCさんとの共有名義に変更し、預金の一部はCさんへ贈与しました。また死亡保険に加入し、受取人をCさんにして財産の一部を保険金化しました。これにより、死亡時の名義上の遺産を圧縮し、Bさんの遺留分額を減らす工夫をしました。
- 長男Bへの働きかけ: AさんはBさんに連絡を取り、「Cに全て譲りたいので遺留分を放棄してくれないか」と相談しました。Bさん自身もすでに自立しており父の財産は当てにしていない様子だったため、Aさんは放棄の代償として現金をBさんに渡し、家庭裁判所での手続きを提案しました。Bさんは熟慮の末に申立てを行い、家庭裁判所の許可のもと遺留分を放棄しました(幸運にも許可が下りたと仮定します)。
これらの対策により、Aさんの死後に長男Bさんが遺留分を請求してくる可能性は低減しました。仮に請求されても、遺産の大半がCさん固有の財産や保険で占められているため、Bさんの遺留分額はごく僅かなものとなります。またBさんが生前放棄していれば請求権自体がありません。結果として、Aさんは意図したとおり「遺留分をほとんど渡さず」に長女Cさんに財産を承継させることができました。
(ケース2)事業承継における高額遺産のケース
会社経営者のDさんは、自身が創業した会社を長男Eさんに継がせたいと考えています。二男Fさんと三男Gさんは事業に関与しておらず、それぞれ別の道を歩んでいます。Dさんの保有する会社株式や不動産はかなり高額で、相続財産全体も多額です。Dさんは「会社の株は全て長男Eに渡し、他の子にはできれば遺留分も渡したくない。会社経営に口出しさせたくない」という希望を持っています。この場合の対策例は次のとおりです。
- 株式の計画的贈与: Dさんは早い段階から長男Eに持株を贈与し始めました。毎年少しずつ株式を譲り、相続開始の10年以上前には株式の大部分をEさんに移しています。これにより、民法1044条の規定でそれら古い贈与分は遺留分算定の基礎に入りません。結果、Dさん死亡時点で遺産に含まれる株式はごく一部となり、FさんGさんの遺留分額は大幅に抑えられます。
- ホールディング信託と契約: Dさんは自社株をEさんに信託し、Eさんを受益者兼受託者とする家族信託契約を結びました。契約には「二男Fと三男Gには信託財産からの給付をしない」旨を盛り込みました。ただし遺留分への配慮として、別途FさんGさんに一定額の金銭を支払う合意書を締結しました。信託自体が遺留分権利者(F・G)の権利を完全には遮断できないことを踏まえ、事前に和解的な合意をしておいたのです。このように、信託で事業承継の形を整えつつ、潜在的な遺留分争いは金銭で解決する枠組みを用意しました。
- 遺言と付言事項: Dさんは公正証書遺言に「長男Eに全財産を相続させる」と明記しました。そのうえで付言事項で「二男・三男には会社経営に関与しておらず、多額の遺産分配は会社存続に悪影響を及ぼすため、遺留分についても極力配慮願いたい」旨を残しました。法的拘束力はないものの、FさんGさんに対するメッセージとしています。
Dさん死亡後、やはり二男Fさんと三男Gさんは遺留分侵害額請求を検討しました。しかし、相続財産に占める会社株式はごく僅かで評価額も議論の余地があり、また生前贈与や信託の存在など法的争点が多く、訴訟は長期化しそうでした。結局、Eさんは事前の合意通りF・Gにそれぞれ遺留分相当額の半分程度の金銭を支払い、両者は遺留分請求を放棄する形で和解しました。結果として、会社株式はほぼ長男Eさんが維持し、FさんGさんには最低限の金銭を渡すだけで済んだのです。Dさんの望んだとおり、事業承継は円滑に進みました。
(ケース3)判例に見る遺留分トラブル
上記のような個別事情のケース以外にも、遺留分に関する有名な判例がいくつかあります。
- 「親子の絶縁と遺留分放棄事件」: (東京高裁平成15年7月2日決定) 前述した、生母と長年断絶状態だった子が遺留分の生前放棄を申請し、高裁で許可された例です。家庭裁判所は当初「代償なく放棄するのは不当」として却下しましたが、高裁は親子の関係状況などを考慮し許可しました。この決定は、生前放棄の判断基準に関する貴重な例となっています。
- 「長男廃除事件」: (熊本家裁昭和54年3月29日審判) 長男による被相続人父への財産横領・改ざん行為が問題となり、父が長男の廃除を申立てたケース。家庭裁判所は長男の行為を「著しい非行」と認定し廃除を許可しました。長男は相続人の資格を失い、遺留分も主張できませんでした。廃除が実際に認められた数少ない例として引用されます。
- 「家族信託無効確認事件」: (東京地裁平成30年9月12日判決) 前述のように、遺留分を度外視して組成された家族信託契約の一部条項が無効と判断された事案です。裁判所は「信託を悪用して他の相続人の遺留分権を実質的に奪うことは許されない」と指摘しました。この判決以降、信託を使う際には遺留分への配慮がより一層求められるようになったと言われます。
これらの具体例・判例からも分かるように、遺留分を巡る争いは事前対策の有無や当事者の事情によって結果が大きく異なります。共通して言えるのは、「遺留分を渡したくない」場合であっても法の制約があるため、完全に排除するのは容易ではないということです。しかし早めの対策や専門知識の駆使によって、結果的に遺留分支払いを減殺した事例も存在します。各家庭の事情に合わせ、合法的かつ適切な手段を講じることが重要です。
弁護士に相談するメリット
遺留分を渡したくない場合の対策は高度に専門的であり、また実行には慎重な判断が求められます。そこで心強いのが相続に詳しい弁護士のサポートです。弁護士に相談・依頼するメリットをまとめます。
- (1)最適な対策プランの提案: 弁護士は遺留分に関する法律知識と豊富な事例経験を持っています。廃除や放棄、生前贈与や信託など様々な手段の中から、依頼者の事情に適した遺留分対策プランを立案してくれます。「遺留分を渡さなくてもいい方法はあるか?」「生前対策は何をすべきか?」といった相談に対し、法律の範囲内で最大限有利になる方策をアドバイスしてくれるでしょう。
- (2)交渉・調停・訴訟の代理: 相続開始後に遺留分請求を受けた場合、弁護士が代理人として相手方との交渉や家庭裁判所での調停に臨んでくれます。法律のプロが交渉することで、感情的対立を避けつつ冷静に主張を展開でき、適切な和解による減額解決が期待できます。調停が不成立で訴訟になっても、弁護士が裁判で有効な反論(例えば評価額の争いや特別受益の主張)を行い、依頼者の利益を守ります。
- (3)証拠収集と主張立証: 廃除を申立てるにせよ、権利濫用を主張して遺留分請求に反論するにせよ、客観的な証拠や法的根拠を揃えることが決定的に重要です。弁護士は調査力を活かして、日記・診断書・第三者の陳述書など有用な証拠の収集を助けてくれます。また判例や条文の知識を駆使して、裁判所を納得させる主張を組み立てます。専門家ならではの立証活動により、難しい事案でも道が開ける可能性が高まります。
- (4)メンタル面・事務手続きの負担軽減: 遺留分の紛争は親族間の争いとなりがちで、当事者は大きな精神的ストレスを抱えます。弁護士に依頼すれば、直接のやり取りを代理してもらえるため心理的負担が軽減します。また煩雑な書類作成や期限管理も任せられるため、依頼者は日常生活を保ちながら手続きを進められます。これは大きなメリットです。
- (5)トータルな相続対策: 遺留分対策は他の相続税対策や財産管理とも絡みます。弁護士は必要に応じて税理士や司法書士とも連携し、総合的な相続対策を提案できます。例えば生前贈与による遺留分対策と同時に贈与税の試算を行ったり、信託契約と遺言作成を組み合わせたりといった具合です。一括して相談できることで、各分野の手続きがスムーズに進みます。
まとめ
遺留分を巡る問題は、法律上の制約と親族関係の感情が絡み合う難しいテーマです。「遺留分を渡したくない」と考える場合、廃除や生前放棄といった手段が理論上存在しますが、実現には厳しい条件があります。現実的には、生前から贈与・信託などで備えたり、相続後の交渉で減額を図ったりするアプローチが重要です。いずれの場合も専門的な判断が必要となるため、早めに弁護士等の専門家に相談し、自身の状況に合った最善の対策を講じましょう。適切な対策とサポートにより、家族の事情に即した円満な相続の実現を目指したいものです。