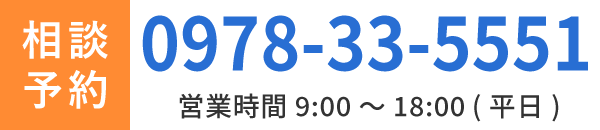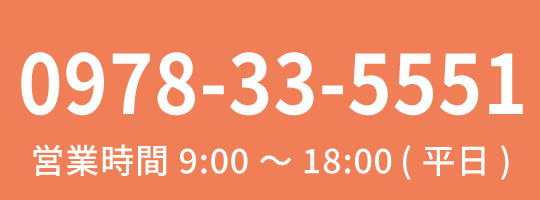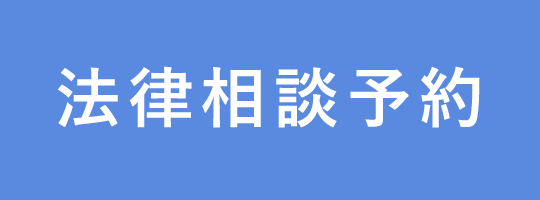相続で不公平な遺言や生前贈与があっても、一定の相続人には最低限の取り分(遺留分)が法律で保障されています。
本ページでは、遺留分が侵害された際に認められる遺留分侵害額請求について、要件から手続き、調停・訴訟の流れ、生前贈与との関係、時効、判例、計算方法まで包括的に解説します。相続トラブルに直面する相続人が適切に権利を行使できるよう、弁護士の視点から実務上のポイントも交えて説明します。
このページの目次
遺留分侵害額請求の要件と手続き
遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、被相続人(亡くなった人)の遺言や生前贈与によって法定相続人の遺留分が侵害された場合に、その不足分の金銭支払いを求める請求です。
2019年7月の民法改正で、それまでの「遺留分減殺請求(原則として現物請求)」から金銭による支払い請求に制度変更されました。まず、遺留分侵害額請求の基本要件と手続きを確認します。
請求できる相続人の範囲
遺留分権利者となれるのは、配偶者、子(代襲相続人を含む)および直系尊属(親など)に限られます。兄弟姉妹には遺留分が認められません。
例えば被相続人に配偶者と子がいる場合、配偶者と子が遺留分を持ちますが、被相続人の兄弟姉妹は請求権者にはなりません。
遺留分が侵害される典型例
遺言で特定の相続人や第三者に遺産の大部分を与えた場合、生前に特定の者へ多額の贈与をした場合などに、他の法定相続人の遺留分が侵害されます。
例えば「全財産を長男に相続させる」という遺言があれば、長男以外の相続人(妻や他の子)の遺留分が侵害される典型例です。不動産や預貯金の大半を特定の子や孫に生前贈与していた場合も、相続時に他の相続人の取り分が減少し遺留分侵害の問題となります。
権利行使の方法と手順
遺留分を侵害された相続人は、相続開始および遺留分侵害を知ったときから1年以内に権利行使しなければなりません。まずは内容証明郵便で相手方(遺産を多く受け取った相続人や受遺者・受贈者)に対し、遺留分を請求する意思表示を行います。
この通知によって時効の進行を止めつつ、請求の具体的内容(誰にいくら請求するか)を明確に伝えます。話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額請求の調停を申し立てます。遺留分請求は法律上まず調停で話し合うことが原則(調停前置)とされており、調停でもまとまらなければ初めて裁判所での訴訟に移行します。
家庭裁判所での調停
調停では調停委員が間に入り、当事者同士の合意を図ります。話合いが成立すれば調停調書に合意内容が記載されます。不成立の場合、調停は終了し、遺留分侵害額請求訴訟を提起することになります。訴訟の管轄は請求額によって異なり、140万円を超える場合は地方裁判所、140万円以下なら簡易裁判所が管轄します。
必要書類と証拠準備
調停申立てには、申立書(相手方の人数分の写し添付)のほか、以下のような書類を用意します。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)
- 全相続人の現在戸籍謄本
- 被相続人の子(および代襲者)で既に死亡している者がいる場合、その者の出生から死亡までの戸籍謄本
- 遺言書の写し、または検認調書謄本の写し
- 遺産に関する資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金残高証明書や証券の写し、被相続人の債務があればその資料)
これらによって相続関係と遺産の全体像を明らかにします。調停申立て時には、収入印紙1,200円分(申立手数料)と所定の郵便切手を納付します。
調停・訴訟での主張立証
調停では当事者の主張を調停委員が整理し、合意点を探ります。
他方、訴訟では原告(遺留分権利者)が遺留分権利者であること、遺留分額およびその侵害額を具体的に主張立証し、被告(遺産を受け取った側)に支払いを求めます。
遺産総額や生前贈与額、その評価について双方が争うことも多く、必要に応じて不動産鑑定評価書や預金の取引履歴など証拠を提出します。特に遺産の評価額は遺留分算定の根幹ですので、専門家の鑑定や評価証明を活用して主張を裏付けます。
遺留分が侵害された場合の法的救済手段と流れ
遺留分を侵害された相続人は、自身の取り分を回復するためにさまざまな法的手段を講じることができます。中心となるのは遺留分侵害額請求訴訟ですが、訴訟前後に資産の保全措置をとることも重要です。主な救済手段とその流れを説明します。
内容証明郵便による請求通知
遺留分請求の意思は、まず内容証明郵便で相手に通知します。この文書で請求額や根拠を明示し、正式な権利主張の証拠とします。通知を受けた相手方が無視・拒否すれば、次の調停・訴訟手続きに移行します。
家庭裁判所での調停
調停手続きでは、調停委員が双方の言い分を聞き取り、和解案の提案など解決に向けた仲介を行います。調停は非公開で柔軟な合意形成が可能なため、多くの場合まず調停が試みられます。ここで減額支払いや分割払いなどについて話し合い、合意に達すれば調停成立です。不成立の場合は速やかに訴訟へ移ります。
遺留分侵害額請求訴訟
調停で解決できないときは、地方裁判所または簡易裁判所(請求額に応じ管轄)に訴訟提起します。
裁判では遺留分の額や計算方法、遺言や贈与の有効性、各相続人の特別受益の有無など法律問題も絡めて主張・立証し、最終的に判決で支払い額が確定します。判決で認められた支払義務は法的強制力を持ち、履行しない相手には後述の強制執行が可能となります。
財産の仮差押え(保全措置)
訴訟前後に、相手方の財産を一時的に差し押さえる仮差押えを申し立てることもできます。これは債権回収を確実にするための保全処分で、遺留分侵害額請求のような金銭請求権でも利用できます。
例えば相手方が相続で得た不動産や預貯金に仮差押えを執行すれば、訴訟中に処分されるのを防ぎ、将来判決取得後にそこから回収しやすくなります。仮差押えには裁判所への申立てと担保提供(保証金の供託)が必要ですが、現在は保証会社の保証状を活用して担保金を立て替える制度も整備されており、申立人の負担が軽減されています。相手方が財産隠しに出る恐れがある場合、仮差押えを検討すべきです。
証拠収集と調査
遺留分侵害額を算定・立証するには、被相続人の遺産の範囲と価値、生前贈与の事実を把握する必要があります。遺産については、不動産登記や銀行口座の残高証明、証券会社の取引残高などを調査します。生前贈与については、贈与契約書や過去の送金記録、被相続人の税申告書などから探ります。訴訟では、裁判所を通じて相手方に資料提出を求める文書提出命令や、関係者への尋問で情報を引き出すことも可能です。専門家の協力を得ながら必要な証拠を収集し、自らの遺留分侵害額を裏付けていきます。
以上が遺留分権利者が取り得る主な救済手段です。次に、逆に遺留分侵害額請求を受けた側の対応策を説明します。
遺留分侵害と生前贈与の関係
生前贈与は遺留分算定に密接に関わります。被相続人が生前に特定の人へ財産を譲っていた場合、その分遺産が減り他の相続人の遺留分が侵害されやすくなるためです。
ただし2019年の相続法改正により、遺留分算定の対象となる生前贈与は相続開始前の10年間に行われたものに限定されました。また事業承継を円滑にするための遺留分に関する特例も設けられています。以下、生前贈与と遺留分の関係を整理します。
「10年ルール」:生前贈与の遡及期間制限
改正民法1044条により、相続開始前10年以内の生前贈与だけが遺留分算定の基礎財産に持ち戻されることになりました。それ以前の贈与は原則として考慮しません。
改正前は、相続人に対する贈与には期間制限がなく何年前でも特別受益として参入し、相続人以外への贈与は1年以内(または遺留分権利者に損害を与える目的があった場合)に限り算入というルールでした。改正によって大幅に単純化され、基本は10年間となったのです。
例えば、被相続人が15年前に長男へ自宅を贈与していても、原則その価額は遺留分算定に含めません。一方、5年前に次男へアパート資産を贈与していれば、その価額は遺留分算定に含められます。なお、この10年ルールは遺留分計算の場合のみで、遺産分割における特別受益には適用されない点にも注意が必要です。
事業承継における遺留分特例
家業や中小企業の承継では、後継者に株式や事業用資産を集中承継させる代わりに他の相続人の遺留分が問題となるケースがあります。
改正法では、遺留分に関する民法特例(除外合意・固定合意)が創設されました。
除外合意とは、先代経営者が後継者に生前贈与・遺贈した自社株式等について、推定相続人全員の合意と家庭裁判所の許可により、その価額を遺留分算定の基礎から除外できる制度です。これにより、合意対象財産について後から遺留分請求される心配がなくなります。
固定合意は、後継者が取得した事業資産の価値について、将来遺留分を計算する際に一定の評価額で固定する合意です(家庭裁判所の許可が必要)。例えば事業用不動産の価値が今後上昇しても、合意時の評価額で計算すれば後継者の遺留分負担額が読めるようになります。これらの特例は事前の家族合意と裁判所許可が必要ですが、事業承継に伴う遺留分トラブルを予防する強力な手段となります。
親族間の無償譲渡と遺留分
親が特定の子に生前大きな援助や無償譲与をしていた場合、それも生前贈与として扱われます。改正後は相続開始前10年以内のものだけが遺留分計算に参入しますが、実務では「被相続人・受贈者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知っていた贈与」は10年より前でも考慮されうるとの指摘があります。
もっとも、立証は容易でなく、基本はルール通り10年と考えて差し支えありません。なお、相続人に対する少額の贈与や日常的援助は特別受益とみなされない場合もありますが、住宅購入資金や多額の学費援助などは特別受益として遺留分計算に加算されることがあります。
以上より、生前贈与は遺留分に直接影響しますが、「10年ルール」の導入で事前の相続対策が立てやすくなりました。例えば遺留分対策として早めに贈与を行い10年以上生存することや、遺留分放棄の許可を被相続人存命中に家庭裁判所で得ておく方法なども検討されます。大規模な生前贈与や事業承継を計画する際は、遺留分権利者となる親族への十分な説明と合意形成が不可欠と言えるでしょう。
遺留分侵害額請求の時効と留意点
遺留分侵害額請求には消滅時効と除斥期間という期間制限があります。期間を過ぎると法的手段で請求できなくなるため、注意が必要です。また、時効の起算点や権利行使にまつわるトラブルについて判例上の判断も出ています。この章では遺留分侵害額請求の時効と、その留意点を解説します。
消滅時効(1年)
遺留分侵害額請求権は「相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時」から1年間で時効消滅します。
つまり、被相続人が亡くなり遺言の内容や贈与の存在を知り、自分の遺留分が侵害されていると認識してから1年以内に請求しないと権利が消えます。例えば遺言書を開示された日から1年以内に請求をする必要があります。期間内に内容証明郵便で請求の意思表示をしておけば時効は中断されますが、何もせず1年経過するともう請求できなくなります。
除斥期間(10年)
相続開始の時から10年を経過すると、遺留分侵害額請求権は消滅します。この10年は権利者が侵害に気づいていなくても進行し、満了すれば請求は認められません。例えば、被相続人の死亡から10年以上経って初めて遺留分侵害を知った場合でも、もはや権利行使はできないということです。
時効に関する実務上の注意
遺留分は相続開始後しばしば遺産分割協議などで揉めているうちに1年が過ぎるケースがあります。しかし単に遺産分割協議を申し入れただけでも、遺留分請求の意思表示とみなされ時効完成を阻止できる場合があります。
最高裁判所は、遺産分割協議の申入れが遺留分減殺請求(現在の遺留分侵害額請求に相当)を含む意思表示だと認めた判例があります(最高裁平成10年6月11日判決)。このケースでは、遺留分を主張せず遺産分割を提案していた相続人にも権利行使があったとみなされ、消滅時効の主張が退けられました。
もっとも、このように裁判所が解釈してくれる保証はなく、安全策として必ず内容証明郵便で明示の請求をすることが望ましいでしょう。もし時効期間が過ぎてしまった場合、法的請求権は消滅します。その場合は任意の話合いで救済してもらうほかなく、相手が応じなければ遺留分相当額を取り戻すことは困難です。
遺留分侵害に関する判例と実務上のポイント
遺留分侵害額請求に関してはこれまで多数の裁判例が積み重ねられてきました。ここでは、実務に影響を与える代表的な判例をいくつか紹介します。最新の判例動向や過去の重要判例から、争点となりやすいポイントを見てみましょう。
最高裁判所第一小法廷令和5年10月26日決定(特別寄与料)
被相続人の遺言で相続分をゼロとされた相続人が遺留分侵害額請求権を行使した場合に、特別寄与料(被相続人に対する貢献に応じて相続人以外の親族が請求できる金銭)を負担するかが争われました。
最高裁は「遺言で相続分なしと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使しても特別寄与料を負担しない」と判断しました。つまり、遺産を全く受け取らなかった人が遺留分請求で金銭を得ても、その人には特別寄与料支払義務は生じないということです。令和元年施行の新設制度である特別寄与料について最高裁が示した初めての判断であり、遺留分と特別寄与の調整方法が明確化されました。
最高裁判所平成10年6月11日判決(遺産分割協議申入れと遺留分請求)
前述のように、遺産分割協議の申し入れが遺留分減殺請求の意思表示とみなされた事例です。長男に全財産を遺贈する旨の公正証書遺言があり、次男が長男に遺産分割協議を求める書簡を送っていました。
長男は時効消滅(当時は1年の除斥期間)を主張しましたが、最高裁は次男の行為は遺留分請求を含む意思表示だったと認定し、請求を認めました。この判例は、明示的でなくとも権利者の意思を広く汲み取って救済したものとして知られ、遺留分請求の実務で参考にされています。
最高裁判所平成20年1月24日判決(価額弁償に関する判例)
旧法下の遺留分減殺請求で、受遺者が現物返還に代えて価額弁償(お金で弁償)を申し出た場合、遺留分権利者がそれを請求した時点でどのような法律効果が生じるかが問題となりました。
最高裁は、遺留分権利者が価額弁償を請求する意思表示をした時に、遡及して目的物の所有権を失い、代わりに確定的な金銭債権を取得すると判示しました。この判例は旧法(現物返還主義)のもとでの判断ですが、遺留分侵害額請求(最初から金銭請求)に移行した現行法でも、金銭債権の確定時期を考える上で参考となる見解です。
遺留分侵害額の計算方法と注意点
最後に、遺留分侵害額の具体的な計算方法について説明します。遺留分の計算は、まず遺留分の基礎となる財産額を算定し、その上で各遺留分権利者の取り分を求め、実際にもらった財産との差額を算出するというステップを踏みます。評価が難しい財産の扱いや、調停・訴訟で金額を確定する際のポイントも解説します。
相続人の組み合わせごとの遺留分割合(総体的遺留分と個別的遺留分)の一覧図。配偶者と子がいる場合など、法定相続分に一定割合(子や配偶者がいる場合1/2、直系尊属のみの場合1/3)を乗じて遺留分を算定する。兄弟姉妹のみが相続人の場合は遺留分権がない。
遺留分算定の基礎財産
まず被相続人の遺留分算定の基礎財産を求めます。これは「被相続人が死亡時に有していた財産の価額 + 相続開始前1年間(※改正後は原則10年間)の贈与価額 – 被相続人の債務額」と定義されます。
債務(借金)があれば遺産総額から控除し、生前贈与は先述のルールに従い一定期間内のものを加算します。例えば、遺産総額5000万円・10年以内の生前贈与1000万円・債務500万円なら、基礎財産は5500万円(5000+1000-500)となります。この基礎財産をもとに各人の遺留分額を計算します。
遺留分割合の算定
遺留分権利者全体の取り分(総体的遺留分)は、法定相続人の組み合わせに応じて遺産の1/2または1/3です。被相続人に子や配偶者がいる場合は遺産全体の1/2、直系尊属のみ(子も配偶者もいない場合)は遺産全体の1/3が総体的遺留分となります。
例えば配偶者と子2人が相続人なら、遺産全体の1/2が遺留分の総額です。この総額を法定相続分で按分して各権利者の個別的遺留分を算出します。配偶者と子2人の例では、遺留分全体1/2をそれぞれの法定相続分割合(配偶者1/2、子全体1/2)で分けます。配偶者の法定相続分は1/2なので遺留分はその半分の1/4、子全体では法定相続分1/2の半分で1/4となり、子1人あたりではさらに1/4を人数分(2人)で割って1/8ずつが各自の遺留分となります。基礎財産5500万円の例で言えば、配偶者の遺留分は5500万×1/4=1375万円、子1人あたりは5500万×1/8=687.5万円となります。
侵害額の算定
次に、各遺留分権利者が実際に得た財産額を上記遺留分額と比較します。遺言や贈与で受け取った額が遺留分に満たない場合、その不足額が遺留分侵害額となります。例えば長男が遺言で1億円相続し、次男は何ももらえなかったケースで、次男の遺留分が2000万円なら、それが侵害額です。
一方、既にもらった額が遺留分額以上であれば侵害額はゼロとなり、請求はできません。なお複数の相手に対して請求する場合、原則として遺贈や贈与を受けた者ごとに受け取った割合に応じて負担します。誰に対していくら請求できるかは法律上定められた順序がありますが(遺贈分→贈与分の順に負担)、調停などでは支払者間で協議して負担割合を調整することもあります。
評価方法の注意点
遺産に含まれる財産の評価方法にも注意が必要です。特に不動産は、固定資産評価額と時価に差があることが多く、どの時点のどの価値を採用するか争いになります。基本的には相続開始時の時価評価が用いられる傾向ですが、当事者間で合意すれば固定資産税評価額など簡便な基準で計算することもあります。
不動産鑑定士による評価は費用がかかりますが、争いが大きい場合は鑑定を依頼することも検討します。同族会社の株式も評価が難しく、純資産価額方式や類似業種比準方式など税法上の評価方法が参考にされますが、実際の経営権プレミアなどをどう考慮するか議論があります。調停ではおおまかな評価で合意し、訴訟では専門家意見を踏まえ裁判所が判断する流れになることが多いです。
調停・訴訟での金額確定
調停では当事者の譲歩によって法的な遺留分額より少ない支払いで合意が成立することもあります。訴訟になった場合は、証拠に基づき裁判所が厳密に遺留分侵害額を算定し判決で命じます。ただし訴訟途中でも和解の機会はあり、裁判所から和解案が提示されることもあります。和解では遺留分額から多少減額されたり、分割払いが認められたりといった解決も見込めます。いずれにせよ最終的な金額確定には事実関係(遺産・贈与額)の確定と法的評価が必要であり、専門的な検討を経て導かれるという点を押さえておきましょう。
まとめ
以上、遺留分侵害額請求についてその概要と実務ポイントを総合的に解説しました。遺留分を巡る紛争は財産的利害だけでなく、親族間の感情的対立を伴うことも多いものです。早期に適切な対応策を講じることで、長引く法廷闘争を避け円満解決を図れる可能性もあります。複雑な事案や高額な遺産が絡むケースでは、個人で判断せず専門家である弁護士に相談することをおすすめします。困ったときは一人で悩まず、弁護士の力を借りて円満な相続の実現を目指してください。